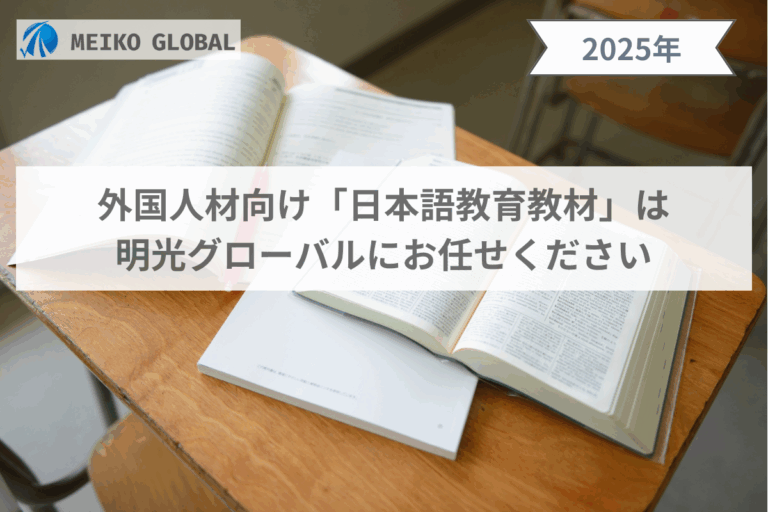近年、日本で働く外国人労働者は増加を続け、介護、外食、宿泊、製造、建設など幅広い分野で重要な役割を担っています。少子高齢化や人手不足が深刻化する中、外国人労働者の採用は企業にとって避けられない選択肢となっています。
しかし、現場では「日本語が話せず指示が伝わらない」「意思疎通が難しく作業が滞る」といった課題が発生しています。こうした状況は生産性の低下や安全管理の不備、チーム内の摩擦につながり、特に介護や建設といった安全性が重視される現場ではより大きなリスクとなります。今回は、外国人労働者と企業の双方が安心して働けるよう、日本語教育やサポートの具体策を解説します。
参照元:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(厚生労働省)
外国人労働者の日本語力の現状
日本で働く外国人労働者が増加するにつれ、彼らの日本語力に関する課題がより鮮明になっています。採用基準として一定の日本語力を確認している場合でも、実際の現場で必要とされる会話能力との間には大きなギャップが存在することが少なくありません。
まずは、現状を正しく理解することが企業にとっての第一歩となります。ここでは、その現状について解説します。
外国人労働者数の推移と受け入れ分野
厚生労働省の統計によると、日本における外国人労働者の数は過去最高を更新し続けており、すでに230万人を超えています。この背景には、慢性的な人手不足や高齢化に伴う労働力確保の必要性があります。特に製造業、建設業、医療・福祉分野では外国人労働者の比率が高まり、彼らがいなければ業務が回らない企業も増えてきました。
また分野についても、当初は製造業や建設業、農業、介護といった分野がメインでした。しかし2019年の特定技能制度創設以降、その対象分野は段階的に拡大しています。たとえば、2024年度には自動車運送業、鉄道、林業、木材産業といった新たな分野が追加され、今後も2027年を目安に物流倉庫やリネンサプライ、資源循環などの分野が候補に挙がっています。
政府はこの拡大に伴い、特定技能1号の受け入れ見込み人数を2019~2024年度の約34.5万人から、2024~2029年度には82万人へと大幅に引き上げました。こうした動きは、外国人材が単なる一部の産業の労働力補完にとどまらず、社会や生活基盤を広く支える担い手として位置づけられつつあることを示しています。
受け入れ分野の拡大に伴い、日本語を母語としない人材が現場に参画する機会も急速に増加しています。外国人労働者の存在感が強まれば強まるほど、日本語力に関する問題は避けられないテーマとなっているのです。
参照元:「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和6年10月末時点)(厚生労働省)
外国人労働者に求められる日本語のレベル
外国人労働者の在留資格や働く目的によって、求められる日本語レベルには大きな違いがあります。企業が彼らの日本語力を正しく把握するには、制度ごとの目安を理解しておく必要があります。
技能実習
技能実習制度では、技能実習1号には日本語能力試験(JLPT)でN4程度の力が求められます。JLPT N4は、基本的な日常会話や簡単な業務指示を理解できるレベルです。
たとえば、「この箱をあちらに運んでください」「10時になったら休憩です」といった指示を理解し、短い受け答えができる程度が目安です。
一方、技能実習2号に進む場合はJLPT N3程度が期待されます。JLPT N3は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解し、自分の考えを相手に伝えられるレベルです。たとえば「昨日の作業で分からなかったことを説明する」「体調が悪いので休みたいと伝える」といった、少し複雑なやりとりが可能になります。
このように、N4は「簡単な指示の理解」が中心であるのに対し、N3は「やりとりの中で自己表現ができる」点が大きな違いです。
特定技能
2019年に新設された特定技能制度では、JLPT N4以上、あるいは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上に合格することが必要です。このレベルであれば、簡単な日常会話や業務指示を理解できる力を持っているとされています。
留学生アルバイト
留学生がアルバイトとして働く場合は、事前に日本語能力試験を受けていないことも多いため、個人差が大きいのが実情です。
基礎的な会話ができる人もいれば、指示を理解するのに苦労する人もいます。そのため、企業側が採用段階で個々の日本語力を丁寧に把握することが欠かせません。
実際の現場での日本語力ギャップ
採用時に一定の日本語レベルを満たしているとされても、現場での業務遂行に必要な力とは必ずしも一致しません。たとえば、教科書的な日本語は理解できても、職場で飛び交う専門用語や方言、速いスピードでの指示には対応できないケースが多いのです。
介護の現場では「嚥下」「排泄」などの専門用語、建設現場では「足場」「墨出し」といった業界特有の表現が日常的に使われます。こうした言葉は教科書や試験勉強だけでは身につきにくく、現場での学習と経験を通じて習得していく必要があります。
また、日本人社員が自然に使う省略表現や曖昧な指示も、外国人労働者にとっては大きなハードルです。結果として「理解できていると思ったら実は誤解していた」という状況が発生し、作業ミスやトラブルにつながります。
企業にとって重要なのは、この「日本語力ギャップ」が当たり前に存在することを前提に、支援策を検討することです。採用時点で日本語能力試験の級を確認するだけでは不十分であり、実務に即した日本語力をいかに伸ばせるかが、定着や生産性向上に直結します。
日本語が話せない外国人労働者を受け入れるリスク
日本の職場で外国人労働者は増え続けていますが、日本語力の不足は避けられない課題です。言葉の壁は業務の効率や安全管理、人間関係にも影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、外国人労働者の日本語力不足が現場にもたらす主なリスクを整理し、企業が直面しやすい問題について解説します。
- 指示・作業内容が正しく伝わらない
- 安全管理・危険予知が困難になる
- チームワークや人間関係に摩擦が生じる
指示・作業内容が正しく伝わらない
外国人労働者に業務を任せる際、もっとも大きな課題となるのが「指示の伝達」です。日本語が十分に理解できないと、作業手順や注意点を正しく受け取ることができず、結果として生産性が低下します。
たとえば、製造ラインで手順を誤れば不良品が発生しやすくなり、顧客からのクレームや納期遅延につながります。外食や宿泊業においても、注文の聞き間違いやサービス内容の誤解は、顧客満足度の低下を招く原因となります。
また、日本人社員側が「伝えたつもり」でも、外国人労働者が正しく理解していないケースは少なくありません。誤解が重なると現場でのトラブルが増え、業務の効率を大きく損なう恐れがあります。
安全管理・危険予知が困難になる
特に建設や製造、介護など安全管理が重要な現場では、日本語を理解できないことが深刻なリスクをもたらします。安全に関する指示や注意事項を正しく理解できなければ、思わぬ事故や労災につながる可能性が高まります。
たとえば、建設現場で「この場所には近づかないでください」という注意が伝わらなければ、重大な事故が発生しかねません。介護現場では「転倒の危険があるので支えながら歩いてください」といった指示が伝わらなければ、利用者の安全にも影響します。
チームワークや人間関係に摩擦が生じる
言葉の壁は業務だけでなく、人間関係にも影響します。意思疎通がうまくいかないことで誤解や不満が蓄積し、職場の雰囲気が悪化することがあります。
日本人社員からすれば「なぜ指示が伝わらないのか」と不満が募り、外国人労働者側も「理解できないまま怒られる」といったストレスを抱えるようになります。
こうした摩擦は小さなものでも積み重なることで職場全体の士気を下げ、離職率の上昇やチームの分断につながります。特にサービス業や介護業のように協力が不可欠な業種では、チームワークの乱れがそのまま顧客へのサービス品質の低下に直結します。
外国人労働者が「日本語を話せない」状況が生まれる理由
外国人労働者の中には、日本語試験をクリアしているにもかかわらず、実際の職場では十分にコミュニケーションが取れないケースが少なくありません。その背景には、単なる学習不足だけではなく、採用基準と現場ニーズのずれや学習環境の制約、さらには職場特有の言語の壁など、複数の要因が存在します。ここでは、その代表的な理由を解説します。
- 採用基準と実際の日本語能力に差があるから
- 働きながら学ぶ時間・環境が不足しているから
- 専門用語・業界用語・方言の壁があるから
- 日本人社員側の「伝え方」に不足があるから
採用基準と実際の日本語能力に差があるから
多くの企業では、日本語能力試験(JLPT)の合格や履歴書に記載された日本語力を参考に採用を判断します。しかし、これらはあくまで読み書きや文法の理解を測るものであり、現場で求められる「会話力」や「即応力」を保証するものではありません。
たとえば、試験に合格していても、早口の指示や職場特有の略語を理解できないことはよくあります。この「試験での日本語力」と「実務に必要な日本語力」のギャップが、現場での混乱につながる大きな要因となります。
働きながら学ぶ時間・環境が不足しているから
外国人労働者の多くはフルタイムで勤務しており、勤務後は疲労から勉強の時間を確保することが難しいのが現実です。生活費を稼ぐ必要があるため、休日もアルバイトや副業に時間を割く人も少なくありません。
その結果、日本語を学び続ける機会が十分に持てず、日本での滞在が長くても語学力が伸び悩むケースが多く見られます。また、学習環境が整っていない職場では、実践的な日本語に触れる機会自体が限られてしまいます。
専門用語・業界用語・方言の壁があるから
業務現場では、教科書や日常会話には出てこない専門用語が数多く使われます。
たとえば、介護の現場では「嚥下(えんげ)」「排泄」といった医学的な用語が日常的に飛び交います。建設業であれば「足場」「墨出し」など、日本人でも専門知識がないと理解しづらい言葉が使われます。
さらに、地域や職場ごとの方言や独特の言い回しも理解の妨げとなり、学習した標準語との間にギャップを生みます。こうした言葉の壁は、外国人労働者が現場に適応するうえで大きなハードルになります。
日本人社員側の「伝え方」に不足があるから
外国人労働者が日本語を理解できない理由の一端は、伝える側の日本人社員にもある場合もあります。
たとえば、漢字を多用した難しい表現や抽象的な言い回しをそのまま使ってしまうと、外国人には理解が難しくなります。また、「ちょっとお願いね」「いつものように」など曖昧な指示は、文化的背景や経験が異なる外国人には解釈できません。
伝え方に工夫を欠くことで、外国人労働者は必要以上に混乱し、結果的に「日本語ができない」と評価されてしまうのです。
日本語が話せない外国人労働者との接し方
外国人労働者が職場にスムーズに適応するためには、企業や日本人社員が「伝え方」を工夫することが欠かせません。日本語力の不足を本人の努力不足と捉えるのではなく、互いに理解しやすい環境を整えることが重要です。ここでは、現場ですぐに実践できる具体的な接し方について解説します。
- やさしい日本語を使う
- 図やジェスチャーを取り入れる
- 翻訳アプリを併用する
- 指示をしたら復唱してもらう
- わからない時に聞きやすい雰囲気をつくる
やさしい日本語を使う
外国人労働者に業務を伝える際は、短くてシンプルな日本語を意識することが効果的です。
「こちらに移動してください」というより「ここに来てください」と言う方が理解されやすくなります。敬語や抽象的な表現、比喩は外国人にとって大きな負担となり、誤解を招きやすい要素です。
そのため、「なるべく簡単な言葉を使い、短く区切って話す」ことを習慣づけることが重要です。また、漢字が多い資料は平仮名やカタカナに置き換えたり、難しい語を避けたりする工夫も必要です。
こうした配慮は、相手に安心感を与え、正しく理解してもらうための第一歩となります。
図やジェスチャーを取り入れる
言葉だけでは伝わりにくい内容も、図や写真、動画などの視覚情報を加えることで理解が飛躍的に深まります。
たとえば、作業手順を文章で説明するよりも、実物を見せたり写真で示したりした方が、外国人労働者はすぐに理解できます。特に安全面に関わる内容は、図解やジェスチャーを取り入れることで誤解を減らせます。
さらに、動作を一度見せ、その後に相手に同じ動きをさせることで理解度を確認する方法も有効です。言葉に依存せず、誰が見ても理解できる情報をセットで提供することは、言語の壁を越えて確実に伝えるための重要な工夫といえます。
翻訳アプリを併用する
現場でのコミュニケーション補助として、翻訳アプリの活用は有効な手段です。
作業手順や安全に関する注意を母語で確認できるようにすれば、外国人労働者の安心感が増し、理解度も高まります。もちろん誤訳のリスクは存在しますが、ゼロから説明するよりも格段に効率的で、誤解を減らす助けになります。
特にマニュアルや安全指示書は、あらかじめ多言語版を準備しておくことで、現場での混乱を防ぐことができます。また、外国人労働者自身が翻訳アプリを使って質問できるように促すことで、双方向の意思疎通がよりスムーズになります。
指示をしたら復唱してもらう
業務指示を出した際は、一方的に伝えるだけで終わらせず、相手に復唱してもらうことが重要です。
「今から何をしますか?」と確認するだけで、誤解をその場で解消できます。これにより、後になってトラブルが発生することを防ぎ、事故や品質不良のリスクを大きく減らすことが可能です。
復唱は単純なプロセスですが、理解度を把握する効果は大きく、外国人労働者本人にとっても「自分は正しく理解できている」という安心感につながります。この小さな習慣を職場全体で徹底することで、指示の精度が高まり、チーム全体の作業効率も向上していきます。
わからない時に聞きやすい雰囲気をつくる
外国人労働者が「質問すると迷惑をかけるのではないか」と感じると、わからないまま作業を進めてしまい、トラブルの原因になります。そのため、質問しやすい雰囲気を整えることが非常に重要です。上司や同僚が「わからなければ必ず聞いてね」と日常的に伝えるだけでも心理的ハードルは下がります。
さらに、定期的に1on1の面談を設け、困りごとや疑問を吸い上げる場を作ることで、現場でのストレスや誤解を未然に防げます。安心して質問できる環境が整えば、外国人労働者の成長速度も早まり、結果的に職場全体のパフォーマンス向上にもつながります。
企業ができる外国人労働者向けの日本語教育・サポート
外国人労働者が安心して働き続けるためには、現場任せにせず企業が積極的に日本語教育や支援体制を整えることが欠かせません。入社後の成長を支える仕組みを用意することで、業務の効率化や定着率の向上にもつながります。ここでは、企業が実践できる具体的なサポート方法を解説します。
- 業務に直結した日本語研修を整備する
- 外部研修・教育サービスを活用する
- ICTツール(翻訳アプリ、AI通訳、学習アプリ)を活用する
- ピクトグラムやマニュアルを整備する
- 日本人社員向けの「やさしい日本語研修」や異文化理解研修を実施する
- 外国人同士のサポート体制をつくる
業務に直結した日本語研修を整備する
外国人労働者に必要なのは、日常会話だけではありません。現場で求められるのは「業務を遂行するための日本語力」であり、専門用語や作業指示に関する表現が理解できなければ即戦力にはなりません。
そのため、企業は自社の業務に直結する日本語研修を整備し、現場で即使える言葉を重点的に学ばせる必要があります。短期集中型の研修やOJTと連動した指導を取り入れると、実践力を効率よく伸ばすことができます。
外部研修・教育サービスを活用する
社内だけで日本語教育を完結させるのは現実的に難しい場合が多くあります。そのような場合は、外部の教育機関やオンライン日本語教育サービスを積極的に活用するのが効果的です。
専門の講師による研修は、言語だけでなく文化的背景への理解も深められる利点があります。また、オンラインサービスであれば場所や時間に縛られず受講できるため、シフト制勤務の労働者にも導入しやすいことが特徴です。
社内で教育リソースを抱え込むのではなく、外部のノウハウを柔軟に取り入れることで、効率的かつ持続可能な教育体制を実現できます。
ICTツール(翻訳アプリ、AI通訳、学習アプリ)を活用する
近年は翻訳アプリやAI通訳、学習アプリといったICTツールが急速に進化しています。これらを上手に活用すれば、外国人労働者の理解をサポートできるだけでなく、自主的な学習意欲を高める効果も期待できます。
たとえば、現場での安全指示をリアルタイムで翻訳したり、空き時間に日本語学習アプリで反復練習したりすることで、実務と学習の両立が可能になります。
企業がこうしたツールを導入・推奨することで、外国人労働者は安心感を持ちながら日本語力を高められ、結果的に業務効率と定着率の向上にもつながります。
ピクトグラムやマニュアルを整備する
文章や会話に頼らず、誰にでも理解できるピクトグラムや図解マニュアルを整備することは非常に有効です。特に安全に関する注意事項は、言語を超えて伝わる視覚的な情報の方が誤解が少なく、即時性も高いという利点があります。
作業手順書も文字だけでなく写真やイラストを組み合わせることで、外国人労働者が直感的に理解しやすくなります。さらに、ピクトグラムは一度整備してしまえば外国人労働者に限らず誰にとってもわかりやすいため、全体の業務効率や安全性の底上げにもつながります。
日本人社員向けの「やさしい日本語研修」や異文化理解研修を実施する
外国人労働者だけでなく、日本人社員への教育も欠かせません。やさしい日本語の使い方や異文化理解を学ぶ研修を取り入れることで、双方のコミュニケーションが円滑になります。
たとえば、複雑な敬語を避けて簡単な日本語に言い換える方法や、文化的な背景による行動の違いを理解することは、誤解や摩擦を防ぐ効果があります。
日本人社員が「伝わる日本語」を意識できるようになることで、外国人労働者の定着率が高まり、チーム全体の協力体制も強化されます。教育の対象を「外国人だけ」にせず、双方に広げることが企業成長の鍵となります。
外国人同士のサポート体制をつくる
同じ職場に母国語を共有できる仲間がいることは、外国人労働者にとって大きな安心材料となります。言語や文化の壁に直面したとき、気軽に母語で相談できる相手がいることで孤立感を軽減でき、精神的な支えとなります。
また、経験の長い外国人労働者が新しく入社した人を支援する「メンター制度」を導入することも効果的です。社内に小さなサポートネットワークを築くことで、外国人労働者は安心して働き続けられる環境を手に入れ、日本語学習への意欲も高まります。結果として、企業にとっても人材の定着と成長が促進されます。
外国人労働者の定着につながる仕組み
外国人労働者を採用しても、短期間で離職してしまっては企業にとって大きな損失となります。そこで重要になるのが「定着を促す仕組み」です。言語や文化の壁を乗り越え、働きやすさを実感できる環境を整えることで、外国人労働者はスキルを伸ばしながら長期的に戦力として活躍できます。ここでは、そのために企業が取り組むべき具体策について解説します。
- 日本語学習を継続できる環境を用意する
- 異文化理解研修で双方のストレスを軽減する
- 日本語力向上・キャリア形成支援を実施する
日本語学習を継続できる環境を用意する
日本語力を向上させるには、継続的な学習環境の整備が欠かせません。しかし、多忙な勤務の中で学習の時間を確保するのは容易ではありません。
そのため、企業が勤務時間内に短時間でも学習の場を設けたり、教材費や学習アプリの利用料を補助したりすることで、外国人労働者の負担を軽減できます。また、職場での実務と連動した学習機会を作ることで、学んだ内容をすぐに実践に活かせる点も効果的です。
こうした仕組みがあることで学習が習慣化し、自然と日本語力が向上していきます。
異文化理解研修で双方のストレスを軽減する
外国人労働者の定着には、本人の努力だけでなく、受け入れる日本人社員の理解も不可欠です。文化や価値観の違いを知らないまま接すると、誤解や摩擦が生じやすく、双方のストレスにつながります。
そこで有効なのが異文化理解研修です。日本人社員が相手の文化背景や行動様式を理解することで、より柔軟な対応ができ、職場全体の雰囲気も改善されます。また、外国人労働者自身も「理解されている」という安心感を得られ、働きやすさが大きく向上します。
こうした環境整備は、離職防止と職場の一体感の醸成に直結します。
日本語力向上・キャリア形成支援を実施する
外国人労働者にとって、日本語力の向上は単なる言語習得ではなく、キャリアアップの大きな鍵となります。企業が研修や昇進制度と日本語力を連動させれば、「努力すれば役割が広がる」という明確な動機づけになります。
たとえば、一定レベルの日本語検定に合格すればリーダー職に挑戦できるといった仕組みは、モチベーションを高める効果的な手段です。
さらに、キャリア形成のロードマップを提示することで、外国人労働者は自分の成長を実感しながら長期的に働く意欲を維持できます。これが結果として高い定着率につながります。
企業が実施すべき外国人労働者の日本語教育の進め方
外国人労働者の日本語教育は、思いつきの取り組みでは効果が限定的になってしまいます。必要なのは、現状を正しく把握し、優先度の高い課題から段階的に解決していく体系的なアプローチです。ここでは、企業が実際に取り組む際の具体的なステップを解説します。
- 現在の日本語力を把握する
- 優先度の高い課題を整理する
- 短期的・長期的の両輪で教育支援を実施する
- 専門的な外部サービスと連携する
現在の日本語力を把握する
教育を始める前に、まずは外国人労働者一人ひとりの日本語力を把握することが欠かせません。JLPT(日本語能力試験)などの公的な指標や、社内独自のテストを用いて「読む・聞く・話す・書く」の4技能を評価します。
さらに、現場の上司や同僚のフィードバックを組み合わせることで、実際の業務遂行における課題を明確化できます。こうして得られた情報を基に、個人ごとの学習目標や教育計画を立てることが、効率的な指導につながります。
優先度の高い課題を整理する
すべての課題に同時対応することは難しいため、業務への影響度に応じて優先順位をつける必要があります。一般的に安全管理、業務効率、顧客対応の3つは優先度が高い領域です。
たとえば、建設現場では安全指示の理解、介護では専門用語の習得、接客業では基本的な会話力の強化が重要となります。課題をカテゴリごとに整理し、緊急性の高いものから順に改善策を講じることで、現場におけるリスクを最小化しながら効果的な教育を実現できます。
短期的・長期的の両輪で教育支援を実施する
外国人労働者の日本語教育は、短期的な対応と長期的な育成を両立させることがポイントです。
短期的には、翻訳アプリや「やさしい日本語」を活用し、即効性のあるサポートを提供します。長期的には、業務に直結する日本語研修や専門用語教育を計画的に行うとともに、在留資格の変更申請も念頭に置いた教育プランとキャリアプランを設計します。これにより、段階的に日本語力を引き上げつつ、本人のキャリアの選択肢を広げることができます。
この両輪を組み合わせることで、現場での即戦力化と将来的なキャリア形成を両立させ、定着率の向上にもつながります。
専門的な外部サービスと連携する
すべてを社内で完結させようとすると負担が大きく、専門性の不足から十分な成果が得られないこともあります。そのため、日本語教育や外国人労働者支援に特化した外部サービスとの連携が有効です。
プロの講師によるオンライン研修、業種別の教材提供、生活サポートを含む包括的な支援などを活用すれば、効率的かつ質の高い教育を実現できます。企業は自社のリソースを補完しながら、安定した成長支援体制を築くことが可能になります。
外国人労働者の日本語教育は明光グローバルにお任せください
外国人労働者を採用しても、「日本語での指示が伝わりにくい」「専門用語や業務に必要な表現がなかなか定着しない」といった課題に直面する企業は少なくありません。特に、日本語を話せない外国人労働者を受け入れる場合、現場の安全性や業務効率にも大きく影響するため、企業として早急な対策が求められます。
こうした課題を解決するために重要なのが、外国人労働者の日本語教育を計画的に行うことです。単なる日常会話だけでなく、現場で必要とされる日本語や、特定技能試験合格に直結する専門日本語力の習得が不可欠です。
そのニーズに応えるのが、明光グローバルの日本語教育サービスです。40年以上の教育実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、特定技能試験対策から業界別の実務日本語研修、さらにオンライン学習ツールまで、幅広いラインナップを用意しています。外国人労働者が現場で安心して働き、長期的に定着できるよう、企業とともに伴走します。
外国人労働者の受け入れを円滑にし、即戦力として育成したい企業の皆さまは、ぜひ明光グローバルのサービスをご活用ください。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人労働者の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人労働者の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人労働者向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,300本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人労働者のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
Japanyの強み
Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。
| 実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,300本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |
| 学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |
| 管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |
日本語オンラインレッスン
日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ビジネスにおける実践力の向上 | ・各業種に対応したビジネス会話の習得 ・ビジネスメールや文書の作成指導 ・プレゼンテーションスキルの習得 |
| 業種別カスタマイズ | ・業界ごとに特化したレッスン 例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等 |
| 即時フィードバック | ・発音の細かな修正 ・自然な表現への言い換え ・ビジネスマナーの指導 |
日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。
外国人社員向け各種教育・研修サービス
明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,300本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |
| オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |
| 各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |
| 各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |
各種教育・研修サービスの強み
明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。
明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。
また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。
さらに、EPA事業を外務省から5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。
まとめ
外国人労働者の日本語力には大きな個人差があり、採用時の基準と現場で求められるスキルとの間にギャップが生じやすいのが現状です。その結果、日本語を十分に理解できないまま業務に従事すると、生産性の低下や安全上のリスク、さらにはチーム内の摩擦といった課題が発生し、企業全体の成果や職場環境に影響を及ぼします。
こうした課題を解決するには、企業が主体的に日本語教育や異文化理解研修を導入することが有効です。短期的には翻訳ツールや「やさしい日本語」の活用によって即効性のあるサポートを行い、長期的には学習環境の整備やキャリア形成支援によって着実なスキル向上を図ることが重要です。
外国人労働者の日本語力向上は、単なる語学教育ではなく、事故防止やチームワークの強化、定着率の改善といった組織全体の成果につながる投資です。教育体制の構築や運用に課題を感じている企業様は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。現場に即したサポートを通じて、外国人労働者と企業双方にメリットのある環境づくりをお手伝いいたします。