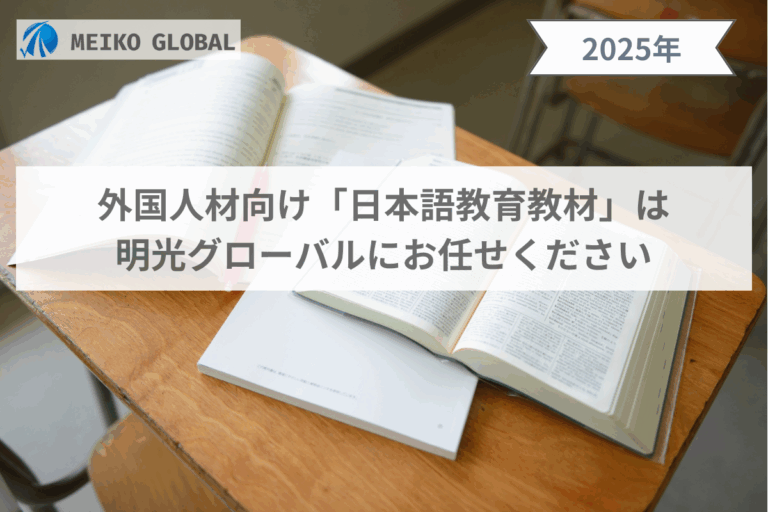外国人材の採用が加速する中で、多くの企業が直面しているのが「日本語教育」の課題です。職場で必要とされる日本語力は、日常会話だけでは不十分であり、ビジネス日本語や専門用語、そして社内コミュニケーションに適応できる実践的な力が求められます。
しかし、現場では「社員ごとに日本語レベルが異なる」「シフト勤務で集合研修が難しい」「定着支援として教育が必要だがコストと工数が重い」などといった問題が多く聞かれます。その解決策として注目されているのが、オンライン日本語講師による研修です。
オンラインであれば、時間や場所に縛られず、企業ごとの課題や業務内容に合わせた柔軟なプログラム設計が可能になります。今回は、外国人材への日本語教育が重要である理由やオンライン講師を活用するメリット、そして導入の流れや研修効果を高める方法について解説します。
外国人材の日本語力不足が引き起こす4つの課題
日本語力の不足は単なる「言語の壁」にとどまらず、業務効率や定着率、教育コストに直結する重大な課題です。採用後に「日本語力の不足による想定外の問題」が浮き彫りになり、戦力化が遅れるケースも少なくありません。ここでは、企業が特に注意すべき4つの側面について解説します。
- 業務効率の低下
- 現場社員とのコミュニケーション不足
- 定着率の低下
- 人材育成コストの増加
業務効率の低下
日本語を十分に理解できない状態で業務に取り組むと、指示の誤解や作業ミスが増加します。たとえば、製造業では「工程表の読み違い」や「安全指示の理解不足」、介護現場では「利用者への声かけの抜け落ち」などが典型的な事例です。こうした小さな誤解やミスが積み重なると、品質や安全性に直接的な悪影響を及ぼし、最終的には顧客からの信頼低下にもつながります。
また、専門用語や業界特有の言い回しを理解できなければ、作業スピードは大幅に落ちます。その結果、日本人社員が通訳や説明のフォローに回らざるを得ず、本来の業務に集中できなくなります。現場全体の生産性が下がるだけでなく、残業や納期遅延といった二次的なコストも発生しやすくなる点は見逃せません。
現場社員とのコミュニケーション不足
言葉の壁は、単なる業務上の誤解にとどまらず、職場の人間関係にまで影響を与えます。報告・連絡・相談(いわゆる報連相)が不十分になると、チーム内の意思疎通にズレが生じ、信頼関係が崩れやすくなります。たとえば、業務の進捗を正確に報告できないことでトラブルが拡大する、あるいは注意点が共有されずに再発防止が進まないといった事態は、企業にとって深刻です。
さらに、日常的な雑談やちょっとした声かけができないと、外国人材が孤立しやすくなります。表面的には大きな問題がなくても、「周囲と打ち解けられない」「職場の雰囲気になじめない」という心理的なストレスが蓄積されることで、業務への集中力やモチベーションが低下していきます。こうした要因は、離職リスクを高める温床となり得ます。
定着率の低下
外国人材の定着率を高めることは、人事だけでなく会社全体にとって重要な課題です。定着しなければ、採用やビザ取得、研修にかけたコストが短期間で無駄になるだけでなく、再採用や再教育のために追加のコストも発生します。その結果、企業の経営や事業計画に大きな影響を与えかねません。
その背景には、「日本語ができないから自分は役に立っていないのでは」という不安や自信の低下があります。業務でのミスや意思疎通の難しさが続けば、職場に居場所がないと感じやすくなります。さらに人間関係を築けず孤立してしまうと、疎外感や不安が強まり、早期退職につながるケースも少なくありません。
人材育成コストの増加
日本語力不足のまま採用を続けると、現場社員がOJT(On the Job Training)や個別指導に多くの時間を割かざるを得ません。教育担当者が本来の業務を後回しにしてまで日本語の補習を行うことになれば、部署全体の負担は想像以上に大きくなります。
特に専門知識を持たない社員が指導を担う場合、教育効果が低くなり、教える側のモチベーションも下がりやすいのが現実です。その結果、教育に割いた労力とコストが採用効果に見合わないと感じる企業も増えています。
場合によっては、「採用しても結局は定着しない」「教育コストがかさみ利益を圧迫する」といった悪循環が起こり、長期的な人材戦略に影響を及ぼします。こうした背景からも、日本語教育は社内任せではなく、外部の専門的なサポートを活用することが求められています。
オンラインの日本語講師が企業に選ばれる理由
外国人材への日本語教育は、従来の集合研修や語学学校では限界があります。そこで注目されているのが、オンライン日本語研修です。ここでは、企業がオンライン講師を選ぶ主な理由について解説します。
- 専門知識を持つ講師が指導するため教育効果が高いから
- 柔軟性が高く全国・海外拠点からでも受講できるから
- 利便性が高くシフト勤務や多国籍チームにも対応できるから
- 対面研修よりもコスト面で効率的だから
専門知識を持つ講師が指導するため教育効果が高いから
オンラインで指導にあたる講師の多くは、日本語教育能力検定に合格した有資格者や、留学生・技能実習生・特定技能人材など、多様なバックグラウンドを持つ外国人材への指導経験を積んでいます。そのため、単なる日常会話の習得にとどまらず、職場で必要とされる「業務直結型の日本語力」を育成できることが特徴です。
特に製造現場の安全確認や、介護現場での利用者への声かけ、オフィスでのビジネス文書作成など、業種ごとに異なる専門用語や実務シーンを想定した指導が可能です。一般的な語学学校ではカバーしきれない領域も、オンラインなら柔軟にカリキュラムに組み込めます。
つまり、「日本語ができる」から一歩進んで、「仕事を遂行できる日本語力」へと学習効果を引き上げられる点が企業にとって大きな価値となります。
柔軟性が高く全国・海外拠点からでも受講できるから
国内外に拠点を持つ企業にとって、教育の一元化は大きな課題です。集合研修の場合、会場の確保や交通費、社員の移動調整といった制約が必ず発生します。
オンライン研修であれば、拠点が複数に分かれていても同じプログラムを同時に展開できるため、教育の質を均一に保ちやすくなります。
さらに、海外から来日予定の社員に対して、渡航前から日本語教育を始められることも大きなメリットです。来日前に基礎を固めておけば、入社直後から現場にスムーズに入れるため、立ち上がりのスピードが格段に早まります。
移動に伴う時間的ロスやコストを削減できるだけでなく、「現地にいながらにして即戦力を育てられる」という点で企業にとって投資効率が非常に高いのです。
利便性が高くシフト勤務や多国籍チームにも対応できるから
製造業や介護業界では夜勤や交代制勤務が一般的であり、従来の対面研修は時間調整が難しいという課題がありました。オンライン研修なら、24時間どの時間帯でも受講可能な体制を整えることができ、シフト勤務の社員も自分の働き方に合わせて学習を継続できます。
また、海外拠点を持つ企業にとってもオンラインは有効です。時差があっても録画配信や柔軟な時間調整が可能で、全拠点で統一されたプログラムを提供できます。
さらに、1対1の集中指導からグループ学習まで柔軟にカスタマイズできるため、多国籍チームでも足並みを揃えやすくなります。国籍や勤務地に左右されない教育体制は、グローバル人材の定着やスキルアップを支える重要な基盤となります。
対面研修よりもコスト面で効率的だから
オンライン研修は、従来型の対面研修に比べてコスト削減効果が明確です。
まず、会場費・講師の交通費・受講者の移動費といった付帯コストが不要になります。さらに、少人数単位や短時間から導入できるため、「必要なときに必要な分だけ教育する」という効率的な運用が可能です。
また、研修を一度きりで終わらせず、継続的に実施できる点も企業にとっては大きなメリットです。継続的な研修は社員の日本語力を段階的に引き上げ、最終的には業務効率や定着率の改善につながります。
費用対効果の高い教育投資として位置づけられるため、企業の経営戦略上も「コストをかける価値がある施策」と判断しやすいのです。
企業が検討すべき日本語研修の具体的な内容
外国人材の日本語研修は、単に会話ができるようになることが目的ではありません。実際の業務や人間関係に直結する内容を取り入れてこそ、研修効果が企業に還元されます。ここでは、企業が検討すべき日本語研修の具体的な内容について解説します。
- 業務で必須となるビジネス日本語
- 業種ごとに異なる専門日本語
- 社内での人間関係を築く日常会話・雑談力
- 資格取得(JLPTなど)を目指す研修
業務で必須となるビジネス日本語
日本の職場では、日常会話よりもむしろビジネス日本語の運用力が重視されます。特に敬語の使い分け(尊敬語・謙譲語・丁寧語)は外国人材にとって難易度が高い領域ですが、上司や顧客とのやり取りに欠かせないスキルです。
また、報告・連絡・相談を正確に行う力は、チームで働く上で必須です。口頭やメールだけでなく、電話対応の練習を通じて臨機応変に対応できるようにすることで、現場での信頼度が格段に高まります。
メール文書の作成についても、フォーマットや表現の違いを理解することで、日本人社員と同じレベルで業務を進められるようになります。
業種ごとに異なる専門日本語
外国人材が活躍する業界は幅広く、それぞれの業務で必要とされる日本語は大きく異なります。そのため、研修では「共通の日本語」だけでなく「業種特化型の日本語」を組み込むことが効果的です。
介護業界
介護現場では、利用者への声かけや安全確認が欠かせません。「立ち上がりますか」「水を飲みますか」といった短いフレーズでも、正しい敬語表現を使えるかどうかが安心感につながります。
また、介護記録の記入や申し送りの日本語も重要です。専門的な表現や用語を理解することで、チーム全体の情報共有がスムーズになります。
製造業界
製造現場では、作業手順や工程管理の指示を正確に理解することが最優先です。「止める」「動かす」「点検する」など、一見シンプルな日本語でも、現場では安全性に直結する意味を持ちます。
また、安全衛生管理の用語や品質チェックの表現を理解できれば、ヒューマンエラーを防ぎ、製品品質の向上に貢献できます。
宿泊・外食
接客を担う宿泊・外食業界では、笑顔とともに自然な日本語で対応する力が求められます。
「いらっしゃいませ」「少々お待ちください」といった基本フレーズから、注文の確認、さらにはクレーム対応まで幅広い表現が必要です。言葉遣い一つで顧客満足度が大きく変わるため、現場に即したシナリオ練習を重ねることが不可欠です。
IT・技術分野
ITや技術系の現場では、専門用語やシステム仕様の説明を理解し、自ら説明できる日本語力が必要です。仕様書の読み取りや会議での発言、オンラインチャットでの業務連絡など、実務の多くが日本語で行われるため、専門的な日本語の習得が成果に直結します。
特にIT分野では、英語と日本語のバイリンガル対応が求められる場面も多く、用語の正確な理解がプロジェクトの成否を左右します。
社内での人間関係を築く日常会話・雑談力
職場で長く働き続けるためには、業務スキルだけでなく人間関係を築く力も欠かせません。その鍵となるのが日常会話や雑談力です。休憩時間やランチの場で自然に会話できると、職場の雰囲気になじみやすくなり、孤立を防ぐ効果があります。
「週末はどう過ごしましたか」「その料理はおいしそうですね」といったちょっとした雑談ができるだけで、周囲との距離が一気に縮まります。こうしたスモールトークの力は、定着率の向上やチームの一体感の醸成に直結するため、軽視できない要素です。
資格取得(JLPTなど)を目指す研修
学習の明確なゴールを設定することは、モチベーション維持に大きく役立ちます。代表的なものに、日本語能力試験(JLPT)があります。
JLPT N3やN2を目指す研修は多くの企業で取り入れられています。資格取得は社員本人の自信につながるだけでなく、企業にとっても客観的なスキル評価の指標となります。
さらに、資格を人事評価や昇進の基準に組み込むことで、学習の意欲が一層高まります。「日本語を学ぶことがキャリア形成につながる」という意識を持つことができれば、社員の定着や成長のスピードも加速します。
オンライン日本語講師を選ぶ際のチェックポイント
オンライン講師を選ぶとき、大事なのは講師やサービスの質だけでなく、企業の人材育成目標に即した選定です。ここでは、企業目線で見逃せないポイントについて解説します。
- 講師の資格・経験・指導実績
- カリキュラムが柔軟に変更可能か
- 学習進捗を可視化・レポート提出ができるか
- 法人向けのサポート体制があるか
講師の資格・経験・指導実績
オンラインであっても、日本語教育は専門性が求められる分野です。
まず注目すべきは、講師が「日本語教育能力検定試験に合格している」「420時間の日本語教師養成講座を修了している」といった、基本資格を持っているかどうかといった点です。これらは教育理論・教授法を理解している証明であり、体系的かつ効果的な指導につながります。
さらに、実務経験の有無も重要です。たとえば、ビジネス日本語を教える場合、実際に外国人材への研修を担当した経験があるか、ITや介護といった業界別の専門用語や現場特有の会話を教えられるかがポイントになります。
単なる「会話練習」ではなく、職場で即戦力となる日本語を習得させられる講師を選ぶことで、研修効果は大きく変わります。
カリキュラムが柔軟に変更可能か
外国人材の学習目的は一様ではありません。日常会話を強化したいケースもあれば、電話応対や社内文書の読解・作成といったビジネススキルを優先したいケースもあります。
そのため、講師やサービスが固定されたプログラムだけを提供するのではなく、企業ごとの課題や現場の実態に応じて内容をカスタマイズできるかどうかが重要です。
たとえば、製造現場では作業指示書や安全確認の日本語を、介護現場では利用者への声かけや記録の書き方を重視する必要があります。IT分野であれば仕様書やシステム説明に特化した表現を学ばせるべきです。
汎用的な日本語教育にとどまらず、現場で役立つ「専門特化型カリキュラム」を柔軟に提供できる講師を選ぶことが、長期的に見て投資効果を最大化します。
学習進捗を可視化・レポート提出ができるか
研修効果を確実に社内へ還元するためには、進捗状況を数値や記録として見える化する仕組みが欠かせません。出席率や小テストの成績、習熟度の推移などを定期的にデータとして提出してもらえるかどうかが、選定時の大きなポイントとなります。
特に人事担当者にとって、教育の効果を経営層や現場に報告することは大きな役割の一つです。講師からのレポートがあることで「誰がどのスキルをどのレベルまで身につけたか」が客観的に把握でき、評価や昇進、人材配置の判断にも活かせます。
また、受講者自身も成長を可視化できればモチベーションを維持しやすく、結果的に研修の継続率も向上します。
法人向けのサポート体制があるか
見落としがちなのが、法人向けの運営サポート体制です。
個人向けレッスンに強い講師やサービスであっても、企業全体の人材育成に適しているとは限りません。複数の受講者を同時に管理するシステム、専用の法人窓口、トラブル時の迅速な対応など、組織的に利用する前提でのサポートが整っているかを確認する必要があります。
特に大規模な企業や複数拠点を持つ企業の場合、受講管理システムの有無は大きな差を生みます。担当者が煩雑なスケジュール調整や進捗確認に追われない仕組みが整っていれば、研修そのものに集中でき、結果的に受講者の満足度も高まります。
長期的な教育パートナーとして信頼できる体制を備えているかどうかは、講師選定において軽視できない重要ポイントです。
オンライン日本語研修の導入プロセス
外国人材への日本語研修は、採用後の定着や業務効率に大きな影響を与える重要施策です。特にオンライン研修は、多拠点の企業や多忙な現場にとって導入しやすい手段ですが、効果を最大化するには計画的なプロセスが欠かせません。ここでは、企業が研修を導入する際に押さえておきたい主要なステップについて解説します。
- 現状課題を洗い出して学習目標を明確にする
- 受講者のレベル診断を行い最適なクラス分けをする
- 講師とカリキュラムを選定し導入準備を進める
- 受講開始後は定期的に成果を確認して改善する
- 単発で終わらせず継続的に学習機会を作る
現状課題を洗い出して学習目標を明確にする
目標を具体的に設定することで、研修内容に現実性が生まれます。たとえば、次のような目標が挙げられます。
- 会議で自分の意見を日本語で発言できるようになる
- マニュアル内容を正確に理解できる力をつける
- 顧客対応の日本語を自然に行えるようにする
- 専門用語の習得
- 実際の業務をベースとした社内外でのコミュニケーション力向上
- 社内文書作成能力の向上
- 在留資格の変更申請に向けた資格取得(JLPTや特定技能2号試験対策など)
こうした多角的な目標を組み込むことで、研修が現場の課題解決に直結し、人材育成の効果をより高めることができます。
受講者のレベル診断を行い最適なクラス分けをする
受講内容が一律では、効率も満足度も上がりません。初級者と中級者が同じクラスでは、内容についていけなかったり、逆に退屈したりするリスクがあります。
そこで、研修前にレベル診断テストを実施し、「基礎重視クラス」「ビジネス日本語クラス」など適切にレベル分けをすることが重要です。これによって、各自にとって負担もなく、かつ成長が実感できる学習体験を提供できます。
講師とカリキュラムを選定し導入準備を進める
研修の目的と受講者のレベルが定まったら、次は講師とカリキュラムの選定です。たとえば、一般的な会話力向上を狙うのか、IT業界向けの専門用語に特化するのかによって、最適な講師や教材は異なります。
さらに、研修開始前には受講スケジュールを確定させつつ、使用するオンラインツールや通信環境の動作確認も念入りに行いましょう。これらの準備を怠ると、初回から混乱し研修そのものの信用が揺らぐこともあります。
受講開始後は定期的に成果を確認して改善する
研修は実施して終わりではなく、成果を定期的に評価し、必要に応じて修正していくプロセスが重要です。たとえば、会議での発言頻度が増えているか、業務文書の理解にかかる時間が短縮されているか、日本語によるコミュニケーションで誤解が減っているかといった具体的な指標を確認することで、研修効果を可視化できます。
こうした定量・定性の情報をもとに教材の追加やカリキュラムの見直しを行うことで、研修内容を現場の実態に合った形へと進化させることが可能です。
単発で終わらせず継続的に学習機会を作る
日本語学習は一時的な衝動ではなく「習慣化」が成果の鍵です。また、母語を使う時間が長くなると日本語に触れる機会が減るため、日本語力が停滞したり低下したりするリスクがあります。そのため、次のような継続学習の仕組みを導入するのが効果的です。
- 月1回のフォローアップレッスン
- オンライン教材を使った自己学習の継続
- 社内での日本語使用機会を促す取り組み
このような取り組みで得た定着感が社員の自信となり、職場へのロイヤリティも高まります。
企業の日本語教育担当者が抱えやすい悩みと解決策
外国人材を受け入れる企業担当者が直面しがちな課題は、「理想と現実のギャップ」に起因するものが多いです。ここでは、代表的な悩みとその効果的な打ち手について解説します。
- 社員の日本語レベルがバラバラ:レベル別カリキュラムで対応
- 勤務シフトが不規則で時間が取れない:柔軟な受講時間調整
- 学習意欲の維持が難しい:定期的なフィードバックとモチベーション管理
- 成果が見えにくい:テストや上司の評価で定量・定性両面から可視化
社員の日本語レベルがバラバラ:レベル別カリキュラムで対応
日本語学習の初級者と中級者を同じクラスに配置すると、理解が追いつかない人・逆に退屈してしまう人が出てきてしまい、研修全体の効率が下がってしまいます。
この問題に対して有効なのが、レベル別カリキュラムの実施です。導入時に日本語レベルを診断し、初級・中級・業務特化などに即したクラス分けを行います。これにより、受講者一人ひとりのニーズに合った内容の提供が可能になり、モチベーションと学習効率の向上につながります。
さらに、JLPTやJFTなどの試験を参考に「業務定着に必要なレベル」を整理し、採用時や研修設計に活用する企業も増えています。
勤務シフトが不規則で時間が取れない:柔軟な受講時間調整
シフト勤務や交代制勤務のある職場では、研修への時間確保が難しく、参加率が低くなりやすい悩みがあります。こうした現場には、早朝・夜間・休日の柔軟な受講体制が有効です。
加えて、研修の録画やアーカイブを活用すれば、勤務時間の都合で参加できない社員も学習機会を逃さずに済みます。
学習意欲の維持が難しい:定期的なフィードバックとモチベーション管理
語学習得には時間がかかり、途中で挫折しやすいのも事実です。「成果が見えづらい」「努力の実感が少ない」と感じると、継続意欲が低下してしまいます。
解決策として、定期的なフィードバックと達成度の共有が有効です。テスト結果の報告や学んだ内容の確認、成長の実感を定期的に受けることで、学習者のモチベーションを高めることができます。
さらに、上司や同僚による声かけも心理的な支援となり、学習の継続につながる効果が期待できます。
成果が見えにくい:テストや上司の評価で定量・定性両面から可視化
「日本語力」は数値では測りにくいため、研修の効果を評価・報告しづらいという問題があります。
こうした状況には、定量評価(テスト結果など)と定性評価(行動変化の観察)を併用することが有効です。「会議での発言増加」「顧客対応のスムーズさ」といった具体的な成果を記録し、定期的に評価対象にすることで効果が可視化され、研修の正当性も経営層に伝わりやすくなります。
日本語教育・研修の効果を最大化するために企業が意識すべきこと
日本語研修をただの「学ぶ場」で終わらせるのではなく、職場の文化や人間関係、目的と融合させることで、「研修という機会」が「成長の糧」に変わります。ここでは、企業担当者が意識するだけで学びのリアリティと影響力が変わる4つの要素について解説します。
- 経営層・現場の理解を得る
- 外国人材本人の学習目的を明確にする
- 日本人社員も巻き込み双方向のコミュニケーションを促す
- 学習成果を実務に落とし込み「できる体験」を増やす
経営層・現場の理解を得る
研修の成果を出すためには、上層部や現場の理解と支援が必要です。プロジェクトのように推し進めるだけでなく、経営層が「人材育成こそが会社の未来だ」と腹落ちし、その価値を現場にも共有する文化を作れば、研修はただの時間ではなく「投資」になります。
こうした背後支援があるだけで、受講者は「これはあくまで学校の講義ではなく、自分たちの成長を会社が本気で支えてくれている研修だ」と感じることができ、モチベーションや参加意欲にもつながります。
心理学では「自律性と関係性」がモチベーションを高める要因とされ、研修環境もそれを反映すべきです。
外国人材本人の学習目的を明確にする
昇進や顧客対応といった、本人にとって意味のある目標が設定されている研修は、単なる「学び」ではなく「自分のキャリアを強くする時間」となります。目標が明確であれば学習意欲は高まり、日本語力の向上によって業務の生産性が上がり、キャリアの幅が広がることで昇格や昇給にもつながります。
さらに、JLPTなど資格取得の際に支援金や報酬を設けると、努力が正当に評価される仕組みができ、学習を後押しする効果も期待できます。こうした仕組みは、成人学習理論(アンドラゴジー)が示す「成人は目的意識がないと学ばない」という原則にも合致しており、本人のモチベーションを長期的に支えることができます。
日本人社員も巻き込み双方向のコミュニケーションを促す
日本語研修を外国人材だけの問題とせず、日本人社員も一緒に学んだり助けたりする姿勢を見せると、「自分だけが学んでいる」という孤独感も薄まります。たとえば、ランチタイムに受講内容を共有したり、簡単なサポートを行ったりする仕掛けを作れば、異文化理解と教え合いの風土にもなります。
こうした関係性を築くことが職場のエンゲージメントやパフォーマンスを高めることにつながります。
学習成果を実務に落とし込み「できる体験」を増やす
学習を勉強の場面だけで終わらせず、実際の業務で「会議で自分の言葉で伝えられた」「クレーム対応で自然な表現ができた」といった体験につなげることが重要です。「できた」という成功体験が積み重なることで自信が生まれ、より深い定着にもつながります。
学び中に体験を埋め込むことで学んだことが即実務に活かせられ、研修の価値もより一層高まります。
外国人材の日本語教育は明光グローバルにお任せください
外国人材を採用しても、現場では「日本語での意思疎通が難しい」「専門用語やビジネス表現が定着しない」といった課題に直面するケースが少なくありません。特に、チームにスムーズに馴染み、戦力として活躍してもらうためには、日常会話だけでなく職場で必要とされる実践的な日本語の習得が欠かせません。
こうした企業のニーズに応えるのが、明光グローバルの日本語教育サービスです。40年以上にわたる教育実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、特定技能試験対策から業界別の実務日本語研修まで幅広く対応。さらに、オンラインレッスンを組み合わせることで、国内外どこからでも受講可能となり、シフト制や多国籍チームにも柔軟に対応できます。
外国人材の採用から育成・定着までを一貫して支援したい企業の皆さまは、ぜひ明光グローバルのサービスをご活用ください。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人材向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人材のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
Japanyの強み
Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。
| 実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,400本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |
| 学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |
| 管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |
日本語オンラインレッスン
日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ビジネスにおける実践力の向上 | ・各業種に対応したビジネス会話の習得 ・ビジネスメールや文書の作成指導 ・プレゼンテーションスキルの習得 |
| 業種別カスタマイズ | ・業界ごとに特化したレッスン 例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等 |
| 即時フィードバック | ・発音の細かな修正 ・自然な表現への言い換え ・ビジネスマナーの指導 |
日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。
まとめ
オンライン日本語研修は、単なる語学教育にとどまらず、外国人材の定着や即戦力化を後押しする重要な施策です。レベル別指導や柔軟な受講時間調整、定期的なフィードバックといったオンラインならではの利点を活用することで、学習効果を高められます。
さらに、経営層や現場の理解を得て、日本人社員も巻き込んだ双方向のコミュニケーションを育むことが、研修成果を実務に直結させる鍵となります。外国人材が「日本語で自信を持って働ける」状態は、本人の成長だけでなく、企業全体の活性化にも直結します。
自社の課題や状況に合わせて適切な研修体制を整えることは、今後の人材活用に欠かせません。導入や運営に不安を感じる場合は、法人研修に豊富な実績を持つ明光グローバルのサポートを活用することで、確実に効果を上げることができます。
研修の設計から運営、成果の定着まで一貫して支援を受けられるため、限られたリソースで最大の成果を得たい企業にとって最適な選択肢となるでしょう。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。