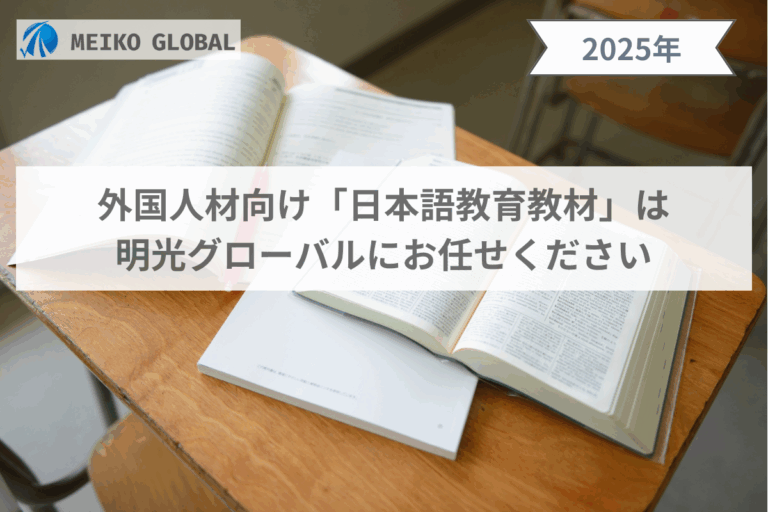日本国内の労働市場では、少子高齢化や労働人口の減少により、外国人材の受け入れが急速に進んでいます。一方で、外国人社員の「定着率の低さ」や「職場での意思疎通の難しさ」といった課題も浮き彫りになってきました。
そうしたなか、企業がいま注目しているのが「オンライン日本語教育」の導入です。特に、実践的かつ継続的に学べる仕組みとして、「オンライン日本語教師」の活用が加速しています。
今回は、外国人材に日本語教育を提供する重要性と、「オンライン型」のメリットや選定時のポイント、成功に導くための実践事例までを徹底的に解説します。
外国人材に「オンライン日本語教育」が必要な理由
外国人材の採用が一般化する中で、その受け入れ体制まで十分に整っている企業は、まだ多くありません。特に現場で課題として浮上しやすいのが、「言語の壁」と「文化の違い」によるコミュニケーションの難しさです。
これらの障害は業務の効率を下げるだけでなく、外国人材の定着にも影響を及ぼします。こうした背景から、今なぜ「オンライン日本語教育」が注目されているのか、その理由と導入の意義について解説します。
外国人材の受け入れが進む中での課題
近年、介護業・外食業・建設業・製造業など、多くの業界において、外国人労働者はなくてはならない存在となりつつあります。国内における少子高齢化や若年層の労働力不足といった構造的な問題を背景に、外国人材の採用は加速度的に進んでおり、特定技能制度や技能実習制度を活用した採用も急増しています。特に中小企業では、人手不足の打開策として、外国人材の雇用に積極的な動きが顕著です。
しかし、実際に外国人材が現場に配属されると、さまざまな課題が浮き彫りになります。たとえば、「作業指示がうまく伝わらない」「報連相が徹底されない」「日本のビジネスマナーや職場文化が理解されにくい」といった問題が日常的に発生し、結果として職場全体の生産性や安全性にも影響を及ぼすケースがあります。
これらの課題の背景には、単なる語学力の不足だけでなく、文化や価値観、労働観の違いが根底にある場合も少なくありません。日本人社員と外国人材の間に誤解や摩擦が生じることで、双方にとってストレスとなり、職場環境が悪化する要因にもなります。
その結果、外国人材本人が「職場に馴染めない」と感じてしまい、早期に離職してしまうケースも後を絶ちません。せっかく時間とコストをかけて採用した人材が、戦力化する前に辞めてしまうことは、企業にとって大きな損失となります。
こうした課題に真摯に向き合い、効果的なサポート体制を整えることが、企業に強く求められています。
語学力不足が与える業務・定着への影響
外国人材にとって日本語は母語ではないため、業務で使われる専門用語や職場特有の表現などを十分に理解できていないケースも少なくありません。こうした言葉の理解不足は、職場の安全性や業務の正確性に直結する深刻な問題となります。
たとえば、作業指示がうまく伝わらないとミスや事故の原因になり、顧客との対応で誤解が生じれば、クレームや信頼失墜につながるリスクもあります。また、職場の同僚との何気ない会話が成立しないことで、チームワークや連携の質にも影響が出てしまいます。
さらに、外国人材の本人にとっても、「自分だけ理解できていない」「会話に加われず孤立している」といった状況は、大きな精神的ストレスとなります。日本語でのやり取りに自信を持てないまま日々の業務をこなすことは、本人のモチベーション低下や職場への帰属意識の欠如につながり、最終的には離職の引き金になる恐れもあります。
このように、語学力の不足は、日常業務だけでなく職場環境や人間関係、さらには定着率にも大きな悪影響を及ぼす深刻な課題なのです。
「オンライン日本語教師」である理由
こうした現場での課題に対応する手段として、いま注目を集めているのが「オンライン日本語教育」です。特に、外国人材一人ひとりの課題やレベルに合わせて柔軟に指導できる「オンライン日本語教師」の活用は、多くの企業から高い評価を得ています。
最大のメリットは、地理的な制約を受けず、全国どこからでも受講できる点です。地方や遠隔地にある事業所でも、質の高い日本語教育を均等に提供できるため、教育格差をなくす効果も期待できます。
また、オンラインであれば受講時間の自由度が高く、シフト制勤務や多忙な現場スケジュールにも柔軟に対応可能です。就業後の夜間や、休日の一部を利用して無理なく学習時間を確保できる点は、現場にとっても受講者にとっても大きなメリットです。
さらに、職種や業務内容に即したカスタマイズ指導が可能であり、現場で必要とされる日本語表現や用語に重点を置いた実践的な内容で学習を進められます。専門性を持つ講師によるマンツーマン指導によって、受講者の理解度や進捗に応じた最適なサポートが可能であることも、オンライン指導ならではの強みです。
対面研修に比べ、移動時間や会場調整などの手間がかからないことも、企業側の負担を大きく軽減します。このように、現場の多様なニーズに応える手段として、「オンライン日本語教師」は、現代の外国人材教育における有力な選択肢となっているのです。
外国人材の成長・定着を阻むよくある失敗例とその原因
「日本語教育の重要性は理解しているものの、なかなか成果が出ない」「思ったように定着しない」と感じる企業も少なくありません。その背景には、教育内容や運用方法に改善の余地がある場合が考えられます。ここでは、外国人材の成長や定着を妨げてしまう代表的な失敗例と、その背景にある原因について解説します。
- 日本語教育を現場任せにしてしまう
- 研修は導入時のみで、その後が続かない
- 本人任せのeラーニングにしてしまう
日本語教育を現場任せにしてしまう
現場の社員が外国人材に対して日本語を教えるという状況は、実は多くの企業で見受けられます。特に体系的な教育プログラムが整っていない場合、教える側も明確な指導方法を持たず、場当たり的に指導せざるを得ないことが少なくありません。
その結果、受講者が得る知識は断片的になりやすく、言語スキルの基礎が不十分なまま業務に臨むことになりがちです。これでは実際の職場で求められるコミュニケーション能力や指示理解に大きなギャップが生じ、業務の効率化が難しくなります。
さらに、教える側の社員にとっても本来の業務と並行して教育を担当することは大きな負担となり、精神的・時間的なプレッシャーが増加します。その負担感から指導が雑になったり、教育が後回しにされてしまったりすることもあり、結果として教育の質が低下してしまうケースが少なくありません。
こうした状況は職場内のコミュニケーション不全を引き起こし、誤解やトラブルに発展することが多いため、現場任せの日本語教育は注意が必要です。
研修は導入時のみで、その後が続かない
多くの企業で見受けられるのが、入社直後に集合研修を一度だけ実施し、その後に継続的な日本語学習の機会を設けていないケースです。入社時の研修だけでは、基本的な日本語の知識を得ることはできても、職場で必要とされる実践的な言語スキルの習得には不十分であることが少なくありません。
言語習得には、反復学習と継続的な練習が不可欠です。新しい表現や業務に即した専門用語を定着させるには、定期的なレッスンやフォローアップが必要です。単発の研修で終わってしまうと、習った内容を使いこなせず、時間の経過とともに忘れてしまう恐れがあります。
その結果、現場で実際に必要な日本語レベルと本人のスキルに大きなギャップが生まれ、業務の効率が下がったり、コミュニケーションミスが増えたりすることにもつながります。さらに、外国人材本人の不安やストレスも増加し、意欲低下や早期離職のリスクが高まることも懸念されます。
したがって、日本語教育は一度の研修で完結させるのではなく、継続的な学習機会を提供し、実務に直結したスキルを段階的に身につけられる環境づくりが重要です。
本人任せのeラーニングにしてしまう
コスト削減を目的にeラーニングを導入したものの、本人任せにしておくと、実際には受講者の多くが利用していないケースがしばしば見受けられます。eラーニングは自分のペースで学べることがメリットですが、その反面、自主的に学習を継続する意欲が高い人でなければ成果につながりにくい側面があります。
多くの外国人材にとっては、仕事や生活のストレス、言語の壁などからモチベーションの維持が困難であり、計画的な学習が続かないことが少なくありません。単に教材を提供するだけでは、学習状況の把握や問題の早期発見ができず、効果的な支援が行えません。
そのため、eラーニングを活用する場合は、学習進捗を管理するシステムや定期的なフォローアップ、質問対応の体制を整えることが欠かせません。これらのサポートがないと、せっかくの教育投資が無駄になりかねず、企業の期待する語学力向上や定着率改善につながらないリスクがあります。
結果的に、本人任せのeラーニングのみで完結させるのではなく、適切な管理と支援を組み合わせた仕組みづくりが重要であると言えるでしょう。
オンライン日本語教育を導入することで得られるメリット
現場任せや本人任せの日本語教育では、日本語力の向上や職場での定着につながりにくいのが現実です。特に、教育の質や継続性が欠けていると、語学習得が不十分となり、コミュニケーションの不全や離職のリスクにもつながります。
こうした課題への対応策として、近年注目されているのが「オンライン日本語教育」の導入です。プロ講師による個別対応が可能なオンライン指導は、企業・外国人材の双方に多くのメリットをもたらします。ここでは、それぞれにとっての具体的なメリットについて解説します。
企業にとってのメリット
オンライン日本語教育を導入することで得られる企業側の主なメリットは次のとおりです。
- 外国人材の定着率の向上
- 現場業務の効率化や生産性の向上
- 全国一律の教育機会を提供
オンライン日本語教育は、単なる語学研修の枠を超えて、人材活用の最適化や経営効率の向上につながる施策として、企業にとって非常に高い導入価値を持つといえるでしょう。
外国人材の定着率の向上
まず、企業側にとって最も大きなメリットは、外国人材の定着率の向上です。
十分な日本語力が身につけば、業務内容や社内ルールの理解が深まり、コミュニケーションもスムーズになります。そういった環境は、外国人材の安心感や働きがいにつながり、結果として離職率の低下に直結します。
これは新たな人材確保や再教育にかかる採用・教育コストの削減にも寄与します。
現場業務の効率化や生産性の向上
日本語によるやりとりが正確かつ円滑になることで、現場業務の効率化や生産性の向上も期待できます。特に、指示の誤解や連携ミスによる作業の手戻りを防ぐことができ、トラブル発生率を下げる効果があります。
加えて、外国人社員が自信を持って発言・報告できるようになるため、主体的な業務参加を促すという側面もあります。
全国一律の教育機会を提供可能
オンライン形式の日本語教育は、物理的な制約を受けにくい点でも優れています。講師が来社する必要がなく、研修のたびに会場を用意する手間も省けます。移動の必要がないため、外国人材が各地の事業所に分散している企業でも、全国一律の教育機会を提供することが可能です。
外国人材にとってのメリット
オンライン日本語教育を導入することで得られる外国人材側の主なメリットは次のとおりです。
- 仕事への意欲やモチベーションの向上
- メンタル面の安定
- 日本の職場文化の学習も可能
- キャリアパスの選択肢の拡大
オンライン日本語教育は外国人材にとって、単なる語学力の向上にとどまらず、働く上での安心感・達成感・将来展望を提供する、極めて価値の高いサポートと言えるでしょう。
仕事への意欲やモチベーションの向上
まず、日本語に対する理解が深まり、会話に自信が持てるようになることで、仕事への意欲やモチベーションが向上します。これまでは指示が聞き取れなかったり、返答に戸惑ったりして消極的になっていた場面でも、語学力が上がることで積極的に関わろうとする姿勢が芽生えやすくなります。
メンタル面の安定
言葉の壁が低くなることで、職場での孤立感や不安感が軽減され、同僚との関係構築が円滑になります。これはメンタル面の安定にもつながり、結果として職場への定着率を高める効果も期待されます。
日本の職場文化の学習も可能
オンライン日本語教育では、単なる語彙や文法の学習だけでなく、日本の職場文化やビジネスマナー、報連相などの実務スキルも併せて学ぶことができます。こうした学びは、職場での信頼構築に不可欠であり、「日本で働くうえでの不安や疑問」を解消する手助けとなります。
キャリアパスの選択肢の拡大
さらに、継続的な学習を通じて「自分は成長している」という実感を得られることは、外国人材にとってキャリア形成における大きな後押しになります。日本語力の向上は、昇格や職域の拡大といったキャリアパスの選択肢を広げることにもつながります。
オンライン日本語教育教材の選び方と注意点
オンライン日本語教育は、外国人材の語学力向上と職場定着に大きな効果が期待できる一方で、選定を誤ると「効果が出ない」「継続されない」といった問題にもつながりかねません。特に法人で導入する場合は、個人向けサービスとの違いや、導入後のフォロー体制をよく見極める必要があります。
ここでは、オンライン日本語教育を導入する際に知っておきたい「個人講師と法人向けサービスの違い」と「教材・サービス選定時のチェックポイント」について解説します。
個人講師と法人向けサービスの違い
オンライン日本語教育には、フリーランスの個人講師によるレッスンから、法人向けに体系的に設計された研修プログラムまで、実にさまざまなサービス形態があります。どちらにもメリットはありますが、企業が組織として外国人材教育を導入する場合には、次のような点で明確な違いが存在します。
教材や進め方の統一性
個人講師によるレッスンでは、基本的に講師の経験や得意分野によって教材や指導方法が決まるため、内容にバラつきが出やすく、標準化や品質の均一化が難しいという課題があります。また、レッスンの進捗状況や受講者の理解度が記録されず、学習の成果を客観的に評価するのが難しい場合も少なくありません。
一方、法人向けサービスでは、企業の人材育成目標や職種に応じてカスタマイズされた体系的な教材とカリキュラムが整備されており、導入時点で教育方針とゴールが明確に設計されています。
さらに、受講者の進捗状況を可視化する管理ツールや、定期的な学習レポートの提出、個別のフォローアップ面談など、学習効果を最大化する運用体制が用意されていることも大きな違いです。
定着支援・企業ニーズへの対応力
個人講師では、一般的な日本語教育をベースにした内容が中心となることが多く、実際の職場や業務で必要とされるスキルとの間にギャップが生じることがあります。また、指導内容が講師個人の経験に依存するため、業界特有の言い回しや実務で使われる表現に対応できないケースも見受けられます。
その点、法人向けサービスでは、介護業・製造業・IT業など、業種別のニーズに合わせた専門的な日本語教育が提供されるため、現場で即活用できるスキルの習得が可能です。加えて、日本語だけにとどまらず、日本の職場文化やビジネスマナー、報連相の習慣といった、いわば「暗黙知」にも踏み込んだ指導ができる点は、定着支援という観点から非常に重要です。
こうした包括的な支援により、外国人材は語学力の向上に加え、「組織の一員として働く力」も同時に養うことができ、結果的に定着率の向上や早期戦力化にもつながります。
選定時に確認すべきポイント
オンライン日本語教育を導入する際は、「導入して終わり」にならないよう、サービス内容を多角的に検討することが大切です。特に、業務との適合性やサポート体制の有無は、教育効果や定着率に直結するため、次のようなポイントを丁寧に確認しておきましょう。
- 業種や職務に合わせた教材・カリキュラムの柔軟性
- 学習状況を把握できるサポート体制の有無
- 講師の指導経験や実績
- 受講しやすいオンライン環境と運用の柔軟性
業種や職務に合わせた教材・カリキュラムの柔軟性
外国人材が配属される職場は、製造業・介護業・IT業・飲食業など多岐にわたります。必要とされる日本語の表現や語彙もそれぞれ異なるため、一般的な日本語教育ではカバーしきれない部分が出てきます。
業種ごとに特化した教材が用意されているか、実際の業務に沿った会話練習や専門用語の指導ができるカリキュラムになっているか事前に確認することが重要です。受講者が現場で即戦力となるためには、「現場で使える言葉」が学べる教育内容であることが不可欠です。
学習状況を把握できるサポート体制の有無
教育の効果を最大限に引き出すには、「やりっぱなし」にしない仕組みづくりが欠かせません。学習の進捗や受講状況を企業側でも把握できる仕組みがあるかどうかは、非常に重要なチェックポイントです。
たとえば、定期的な進捗レポートの提出、学習記録の共有、講師からのフィードバック面談の有無などが挙げられます。こうしたサポートがあることで、受講者本人のモチベーション維持だけでなく、企業としての人材育成の計画も立てやすくなります。
講師の指導経験や実績
講師の質は、教育の成果に直結します。法人向けのオンライン日本語教育を選ぶ際は、日本語教育の資格だけでなく、実際に外国人材を対象とした研修経験のある講師が在籍しているか確認しましょう。
特に、多国籍な人材を受け入れている企業の場合は、異文化理解や多様な背景を持つ受講者への指導実績があるかどうかも重要です。また、どのような業種・企業規模での導入実績があるかといった点も、サービスの信頼性を見極めるうえで参考になります。
受講しやすいオンライン環境と運用の柔軟性
オンライン教育であっても、受講のしやすさは学習継続に大きな影響を与えます。通信環境や必要機材、使用するプラットフォームの操作性など、基本的な技術面はもちろん、受講の時間帯や予約方法の柔軟性も見逃せないポイントです。
特に、交代勤務やシフト制で働く外国人材にとっては、柔軟な受講スケジュールが確保できるかどうかが、学習の継続に直結します。受講者にとって無理のない学習環境が整っているか、実際に導入前に体験する機会があるかなど、事前に確認しておくと安心です。
オンライン日本語教育にありがちな誤解
近年、オンライン日本語教育の導入は進んでいますが、オンライン形式に不安や疑念を持つ企業も依然として少なくありません。「対面でなければ効果が出ないのでは」「ITに弱い人には無理」といった先入観が、導入をためらう理由の一つとなっています。
しかし、現在の法人向けオンライン日本語教育は、従来の一方向的な映像授業とは異なり、受講者のレベルや業務内容に合わせて柔軟に対応できる体制が整っています。ここでは、そうした不安の中でも特に多く見られる3つの誤解について、実際の状況とともに解説します。
- オンラインだと実践的な会話力はつかない
- ITに不慣れな社員だと使えない
- 費用対効果が見えにくい
オンラインだと実践的な会話力はつかない
オンライン学習に対しては、「受け身の一方通行な授業」「実践的なコミュニケーションが身につかない」といった印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、現在主流となっている法人向けオンライン教育は、講師と受講者がリアルタイムで対話しながら進める「双方向型」のスタイルが基本です。
ロールプレイ形式で指示や報連相のやり取りを練習したり、職場のシチュエーションを想定した模擬会話に取り組んだりすることもでき、むしろ対面形式よりも効率的・実践的だと評価されることもあります。
受講者の会話スキルや反応速度などに応じて即座にフィードバックが得られる点も、オンラインの大きな強みです。実務に即したやり取りが繰り返し練習できるため、現場で「使える日本語」がしっかりと身につきます。
ITに不慣れな社員だと使えない
オンライン学習=ITスキルが高くないと使いこなせない、というイメージも根強い誤解の一つです。確かに、オンライン教育にはPCやスマートフォン、タブレットといった機器の操作が必要ですが、ZoomやTeamsといった一般的なツールを使えば、基本操作のみで受講が可能です。
さらに、多くのサービスでは事前に受講者への操作説明や練習機会が設けられており、初めての方でも安心してスタートできるよう配慮されています。
重要なのは、ITの得手不得手ではなく、受講前の準備と継続的なフォロー体制です。「使えるか不安」という不安を、「これならできそう」に変えるための支援が整っていれば、ITに不慣れな方でも問題なく利用できます。
実際に、年齢層が高めの受講者やITに不慣れな外国人材でも、スムーズに受講を継続しているケースは多数存在します。
費用対効果が見えにくい
語学研修には「目に見える成果が出にくい」「投資対効果が測りづらい」といった声もありますが、実際にはさまざまな角度から効果を可視化することが可能です。
たとえば、日本語力の向上により、現場での報連相や指示の理解度が高まり、ミスやトラブルの防止につながります。また、コミュニケーションの円滑化により職場でのストレスが減少し、離職リスクも低下します。
これにより、採用後の早期離職を防ぎ、「採用→教育→離職→再採用」という負のサイクルを断ち切ることができます。
さらに、オンライン教育であれば、研修にかかる交通費・宿泊費・会場費といったコストが不要となり、全社的に見れば大幅なコスト削減にも貢献します。加えて、受講履歴のデータや講師からの評価コメント、レベルチェックテストの結果などを通じて、学習効果を定量的に追跡することも可能です。
このように、中長期的に見れば、オンライン日本語教育は非常に高い費用対効果を発揮し、企業の成長と人材定着を支える有効な投資といえるでしょう。
外国人材の日本語教育は明光グローバルにお任せください
外国人材の成長と定着には、日本語力の向上が欠かせません。しかし、ただ教科書的な日本語を学ぶだけでは、現場での活躍にはつながりにくいのが実情です。
明光グローバルは、企業と外国人材の両方に寄り添い、「現場で使える日本語」「継続しやすい教育体制」を軸に、実践的なオンライン日本語教育サービスを提供しています。多様な業種・職種に対応できる柔軟なカリキュラムと、教育現場で培った確かな指導ノウハウで、貴社の人材育成を力強くサポートします。
最後に、明光グローバルの概要と、提供するオンライン日本語教育サービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人材向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
日本語オンラインレッスン
日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ビジネスにおける実践力の向上 | ・各業種に対応したビジネス会話の習得 ・ビジネスメールや文書の作成指導 ・プレゼンテーションスキルの習得 |
| 業種別カスタマイズ | ・業界ごとに特化したレッスン 例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等 |
| 即時フィードバック | ・発音の細かな修正 ・自然な表現への言い換え ・ビジネスマナーの指導 |
日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,300本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人材のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
Japanyの強み
Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。
| 実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,300本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |
| 学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |
| 管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |
まとめ
外国人材をただ「雇用」するだけでなく、「育成」し、長期的に「定着」させるには、日本語力の向上が欠かせません。言語能力の底上げがなければ、コミュニケーションの齟齬や職場での孤立感が生まれやすく、結果として離職リスクが高まってしまいます。
オンライン日本語教育を活用することで、企業は教育の質を保ちながら、移動や時間の制約を減らし、コスト面でも効率的に学習環境を提供できます。また、受講者一人ひとりのレベルや業務内容に応じた柔軟なカリキュラムを実施できるため、実務に直結したスキルを効果的に伸ばせる点も大きなメリットです。
明光グローバルは、長年の教育実績と豊富なノウハウを持ち、多様な業種や職種に対応可能なカリキュラムと充実したサポート体制で、外国人材の成長を力強く支援します。教育効果の見える化や学習継続を促す仕組みも整っており、企業と外国人材双方にとって安心して利用できる環境を提供しています。
外国人材の日本語教育や研修に関してお困りのことがあれば、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。貴社の人材育成課題を解決し、持続可能な組織づくりに貢献します。