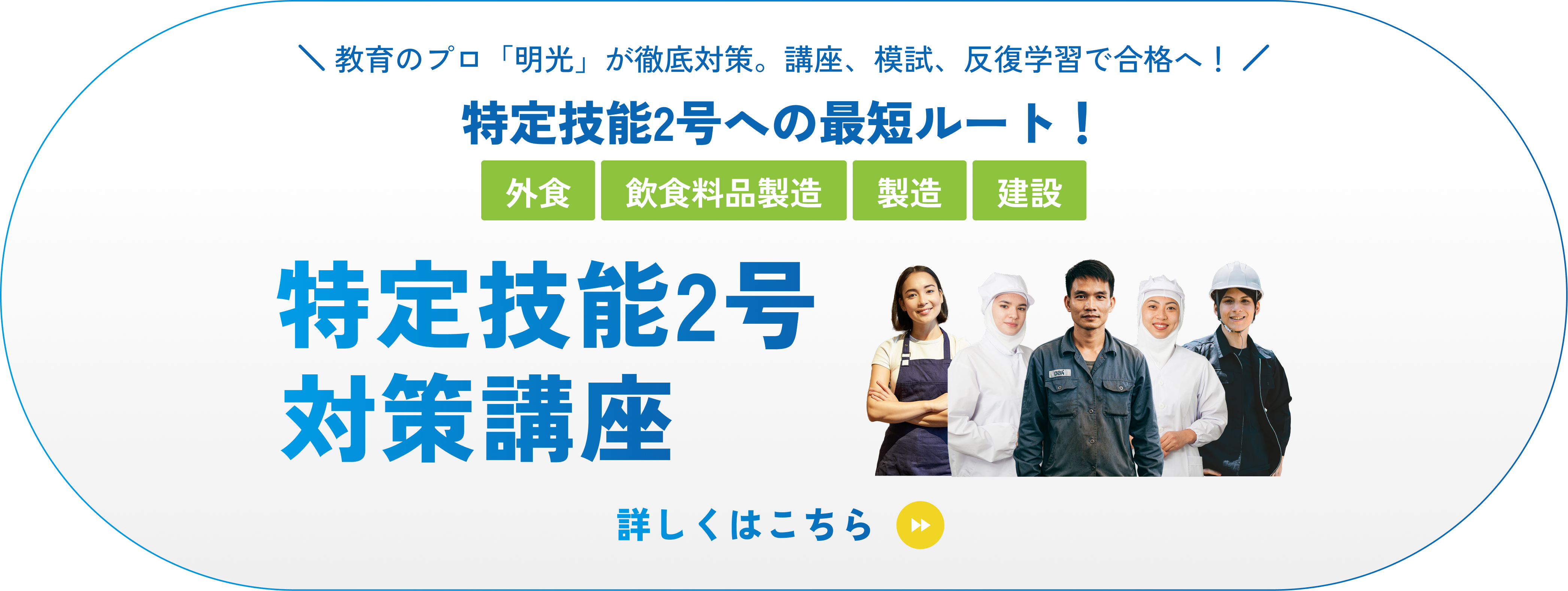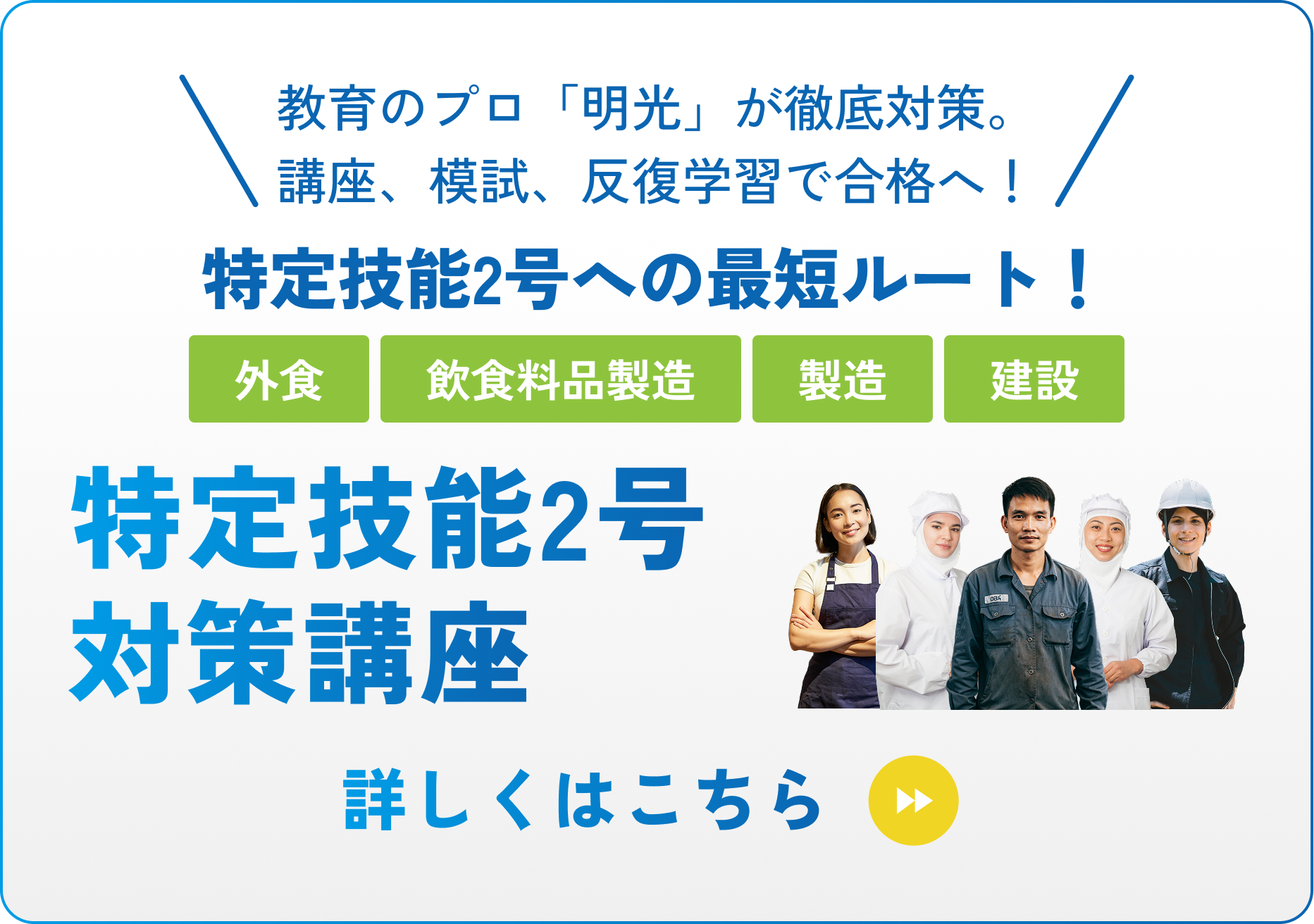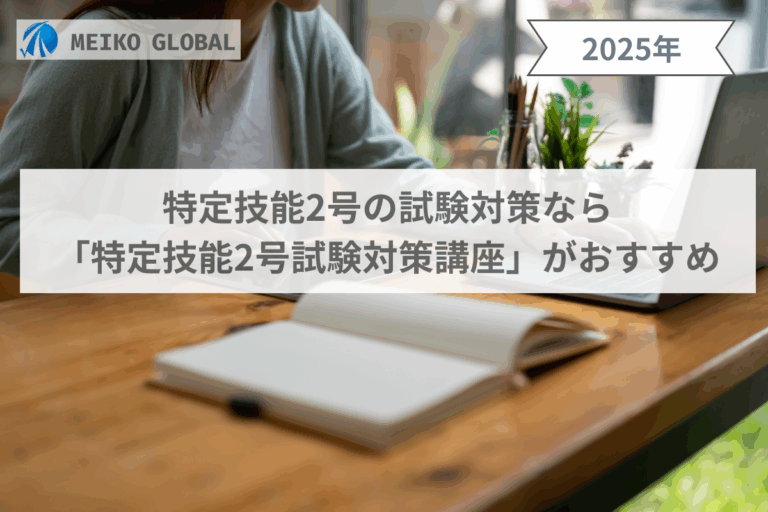特定技能2号「建設分野」の評価試験は、高度な専門知識と実務能力が求められる難関試験です。試験に合格するには、公式テキストを活用した効率的な学習と、現場経験との連携が重要です。
今回は、特定技能2号「建設分野」の概要や取得要件、試験対策に欠かせない学習テキスト(入手方法や内容、活用ポイント)などについて詳しく解説します。
特定技能2号「建設分野」の基礎知識
まずは、特定技能2号「建設分野」の制度の概要や試験内容、試験の実施状況について詳しく解説します。
特定技能2号「建設分野」の概要
特定技能2号「建設分野」は、日本の建設現場で深刻化する人手不足解消のため、熟練した技能を持つ外国人材に与えられる在留資格です。主な特徴には次のものが挙げられます。
| 3つの業務分野 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 |
| 業務上の役割 | 複数の作業員を指導し、工程管理を担う班長レベルの業務を担う |
| 在留期間 | 上限なし |
| 家族帯同 | 可能 |
この在留資格は長期的な就労が可能になる一方、難易度の高い評価試験への合格や実務経験が必要で、取得のハードルは高いです。2024年6月時点の取得者は66人とまだ少数ですが、制度の活用で、外国人材のキャリアアップと建設業界の人材不足解消が期待されています。
参照元:
取得要件
特定技能2号「建設分野」の資格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 技能試験に合格する | 以下のいずれかの試験に合格すること ・「建設分野特定技能2号評価試験」に合格すること ※一般社団法人 建設技能人材機構が主催 ・技能検定1級または単一等級に合格すること ※都道府県が主催 |
| 実務経験を有している | ・班長として0.5~3年の実務経験 ※職種によって必要な経験年数は異なる ・建設キャリアアップシステムレベル3で代替可能 |
実務経験に代替可能な建設キャリアアップシステムとは、技能者の資格や就業履歴を管理するシステムです。レベル3取得により、班長としての実務経験が短い場合でも要件を満たせます。
なお、特定技能2号取得に際しては、日本語試験の受験は不要です。
参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省・国土交通省)
取得するとできること(メリット)
特定技能2号「建設分野」を取得することで、外国人材と受入れ企業双方にメリットをもたらします。双方の主なメリットは次のとおりです。
外国人材にとってのメリット
| メリット | 概要 |
|---|---|
| 在留期間の更新上限がない | 通算在留期間に制限がなくなるため、継続的な就労が可能になり、キャリアプランを立てやすい。 |
| 家族の帯同が可能になる | 配偶者や子を日本に呼び寄せることができ、家族と一緒に生活できる(特定技能1号では原則不可)。 |
| 永住権取得の可能性がある | 一定期間の在留後、所定の要件を満たすことで、永住権を申請できる。 |
受け入れ企業にとってのメリット
| メリット | 概要 |
|---|---|
| 即戦力人材を採用できる | 建設分野に関する高度な知識・技能を持っているため、すぐに現場のリーダーとしての活躍を期待できる。 |
| 長期的に働いてくれる人材を確保できる | 在留期間の更新上限がないため、長期にわたって安定した労働力を確保できる。 |
| 幅広い業務を任せられる | 建設分野の管理、従業員の指導など、幅広い業務を任せられる。 |
| 人材定着によるコスト削減を見込める | 人材が定着すると、新たな採用コストや教育コストの必要がなくなるため、コスト削減につながる。 |
| 生産性が向上する | 専門的なスキルや経験を保有しているため、生産性の向上を期待できる。 |
このように、外国人材側・受け入れ企業側双方にとって、Win-Winの関係を築ける制度といえるでしょう。
特定技能1号との違い
特定技能1号と特定技能2号では、技能水準、在留期間、家族帯同の可否などに違いがあります。主な違いは以下の表のとおりです。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技術水準 | ある程度の実務経験と知識、技能を有している状態 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新制限なし(更新手続きは必要) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 実務経験 | 不要 | 班長として0.5~3年が必要 ※建設キャリアアップシステムレベル3で代替可能 |
| 受入れ機関または登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
| 日本語試験 | 必要 | 試験等での確認は不要 |
特定技能1号に比べて、特定技能2号は長期の在留、家族帯同の可能性など、就労条件が大幅に優遇されています。
※参照元:
- 建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について(国土交通省)
- 特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)
「建設分野」の特定技能2号評価試験の概要
建設分野の特定技能2号評価試験の概要は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受験資格 | ・班長または職長として、0.5~3年の実務経験 ・試験日当日に満17歳以上であること ※ただし、必要な実務経験を積んでいることが前提 |
| 試験科目 | 学科試験(土木、建築、ライフライン・設備) ・職長の職務 ・現場管理における職長の役割 ・安全衛生活動における職長の役割 ・職長としての図面の捉え方 ・職長としての建設業の理解 ※業務区分ごとに試験科目の内容は異なる 実技試験(土木、建築、ライフライン・設備) ・工事現場で使える工具、機械、材料、計測器の知識 ・建設現場の施工に関する知識 ・建設工事の安全 ※各業務部ごとに試験科目の内容は異なる |
| 実施方法 | 学科試験 ・実施方法:CBT方式(コンピュータ使用) ・試験時間:40問(60分) ・出題形式:4択式 ・合格基準:75%以上(30問以上正解) 実技試験(判断・計画立案試験等) ・実施方法:CBT方式(コンピュータ使用) ・試験時間:25問(40分) ・出題形式:4択式 ・合格基準:75%以上(19問以上正解) |
| 受験スケジュール | 令和7年(2025年)3月~令和8年(2026年)2月までの予定(2025年3月時点) 令和7年 ・3月:東京都、大阪府 ・4月:東京都、大阪府、栃木県 ・5月:東京都、大阪府、愛知県(詳細未定) ・6月:東京都、大阪府、北海道(詳細未定) ・7月:大阪府、広島県、東京都(詳細未定) ・8月:大阪府、東京都、福岡県(詳細未定) ・9月:東京都、大阪府、宮城県(詳細未定) ・10月:北海道、東京都、大阪府(詳細未定) ・11月:東京都、大阪府、愛知県(詳細未定) ・12月:東京都、大阪府、広島県(詳細未定) 令和8年 ・1月:東京都、福岡県、大阪府(詳細未定) ・2月:東京都(詳細未定) |
この試験は、建設現場のリーダーとして必要な知識と技能を、学科と実技の両面から総合的に評価するものです。
参照元:建設分野特定技能の評価試験情報と申込み(一般社団法人 建設技能人材機構)
「建設分野」の合格率
業務区分や実施時期によって異なりますが、特定技能2号技能評価試験の合格率は低い傾向にあります。以下の表は、令和7年(2025年)2月の試験結果です。
建設分野特定技能2号評価試験の各区分の合格率
| 試験種別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 土木区分 | 185 | 31 | 16.8% |
| 建築区分 | 274 | 67 | 24.5% |
| ライフライン・設備区分 | 52 | 9 | 17.3% |
これまでの試験結果でも、合格率は15〜30%程度に推移しており、難易度の高い試験であることがわかります。また、受験者数は建築区分が最も多く、次いで土木区分となっている一方で、ライフライン・設備区分は受験者が少ない状況が続いています。
なお、海外でも受験できますが、受験者数が極端に少なく、ほとんどが日本国内での受験となっています。
参照元:令和7年2月 建設分野特定技能評価試験結果(一般社団法人 建設技能人材機構)
特定技能2号「建設分野」の学習テキスト
特定技能2号「建設分野」の評価試験は「学科」と「実技」に分かれており、それぞれに対応したテキストが用意されています。これらのテキストは、試験範囲を網羅し、現場で必要となる知識や技能を習得できるよう構成されています。ここでは、テキストの入手方法や各テキストの内容について詳しく解説します。
テキストを入手する方法
特定技能2号「建設分野」の評価試験用テキストは、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のポータルサイトから無料でダウンロードできます。
サンプル問題や母国語に対応した翻訳テキストもあるので、ぜひご活用ください。
学科試験用テキストの内容
3つの出題範囲(土木工学、建築、ライフライン・設備)の学科試験用テキストは、それぞれ用意されていますが、内容はすべて同じです。学科試験用テキストは、次の4つの章で構成されています。
| 第1章 日本の現場で大切にしていること | ・チームワークについて ・日本の建設工事の施工体制について ・建設キャリアアップシステム(CCUS)について ・あいさつについて ・朝礼(全体朝礼、職種ごとの朝礼)について |
| 第2章 日本の減で働く上で守らなければならない法令 | ・労働関連法(労働基準法、労働安全衛生法など)について ・建設業関連法(建設業法、建築基準法など)について ・環境関連法(大気汚染防止法、騒音規制法など)について ・その他の法律(消防法、水道法など)について |
| 第3章 建設工事の種類と業務 | ・建設工事の種類(土木工事、建築工事、ライフライン・設備工事など)について ・主な専門工事(土工事、推進トンネル工事、杭工事など)について ・建設工事に必要な資格(クレーン・デリック運転者、玉掛作業者など)について |
| 第4章 建設現場で使われるあいさつ・用語・共同生活上の注意 | ・あいさつ・緊急時の呼びかけなどについて ・建設現場で使われる用語について ・共同生活上の注意について |
なお、学科試験のサンプル問題も用意されているので、テキストと併せてご使用ください。
※参照元:建設分野特定技能2号 評価試験用テキスト(JAC建設技能人材機構)
実技試験用テキストの内容
実技試験用テキストは、3つの出題範囲(土木工学、建築、ライフライン・設備)それぞれで用意されています。内容は一部重複していますが、各区分に対応した内容となっています。
また、各区分共通の実技試験用サンプル問題も用意されているので、併せてご使用ください。ここでは、各区分の実技試験用テキストの詳細を紹介します。
※参照元:建設分野特定技能2号 評価試験用テキスト(JAC建設技能人材機構)
実技試験:土木
土木区分の実技試験用テキストは、次の3つの章で構成されています。
| 第5章 工事現場で使われる工具、機械、材料、計測器の知識 | ・職種固有の工具、機械、材料、計測器について ・共通の工具、機械、材料、計測器 |
| 第6章 建設現場の施工に関する知識 | ・建設減における共通事項について ・各専門工事(土工事、推進トンネル工事、杭工事など)の施工知識について |
| 第7章 建設工事の安全 | ・建設工事における死亡災害について ・建設現場における安全活動について |
土木工事の現場で必要となる実践的な知識(工具・機械・材料、施工方法)と、安全確保のための知識などを体系的に習得できる構成になっています。
実技試験:建築
建築区分の実技試験用テキストは、次の3つの章で構成されています。
| 第5章 工事現場で使われる工具、機械、材料、計測器の知識 | ・躯体工事について ・内外装工事について ・共通の工具、機械、材料、計測器について |
| 第6章 建設現場の施工に関する知識 | ・建設現場における共通事項について ・各専門工事(とび工事、鉄骨工事、鉄筋工事など)の施工知識について |
| 第7章 建設工事の安全 | ・建設工事における死亡災害について ・建設現場における安全活動について |
建築区分の実技試験用テキストは、建設工事の現場で活躍するために必要な知識(各種工具・機械・材料の知識、施工技術)と安全管理の知識などを、バランス良く習得できる構成となっています。
実技試験:ライフライン・設備
ライフライン・設備区分の実技試験用テキストは、次の3つの章で構成されています。
| 第5章 工事現場で使われる工具、機械、材料、計測器の知識 | ・職種固有の工具、機械、材料、計測器について ・共通の工具、機械、材料、計測器について |
| 第6章 建設現場の施工に関する知識 | ・建設現場における共通事項について ・管加工の施工知識について ・冷凍空気調和機器工事について ・保温保冷工事について ・ライフラインの管工事について ・建築板金工事について ・電気設備工事について ・電気通信工事について ・築炉工事について ・消防設備工事について |
| 第7章 建設工事の安全 | ・建設工事における死亡災害について ・建設現場における安全活動について |
ライフライン・設備工事の現場で必要となる実践的な知識(工具・機械・材料、施工方法)と、安全確保のための知識などを体系的に習得できる構成になっています。
学科・実技試験用テキストを活用するポイント
特定技能2号「建設分野」の試験対策には、学科・実技両方のテキストを効果的に活用することが重要です。ここでは、具体的にどのような点に注意して学習を進めれば良いのか、学科試験と実技試験、それぞれのテキスト活用におけるポイントを解説します。
学科試験用テキストを活用するポイント
学科試験用テキストは、出題範囲を網羅的に学習するための重要なツールです。効果的に活用するための主なポイントは次のとおりです。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 全体像を把握する | ・各章のテーマを確認し、受験範囲を把握する。 |
| 用語を理解する | ・専門用語や現場で使われる言葉の意味を正確に理解する。 ・略語(例:CCUS、KY)は正式名称とセットで覚える。 |
| 繰り返し学習する | ・一度すべての内容を読み込み、2回目以降は理解が曖昧な部分を中心に学習する。 ・日本の建設現場特有の慣習を重点的に読み込む。 ・テキストの該当箇所にマーカーを引いたり、ノートにまとめたりして、弱点を克服する。 |
| 過去問を併用する | ・過去問や練習問題(サンプル問題)を解き、間違えた箇所や理解不足の箇所をテキストで復習する。 |
これらのポイントを意識し、計画的に学習することで、学科試験合格に必要な知識を効率的に身につけられます。
実技試験用テキストを活用するポイント
実技試験用テキストは、実際の建設業務に直結する内容であるため、現場での経験と照らし合わせながら学習すると効果的です。以下のポイントを意識して学習しましょう。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 実務と関連付ける | ・テキストに掲載されている事例を、自分の担当業務や過去の経験と照らし合わせ、実際の作業でどのように活かせるか具体的に考えながら学習する。 |
| 先輩や同僚に質問する | ・テキストで理解できない点や疑問点は、現場の先輩や同僚、職長などに質問し解決する。 |
| 図や写真を活用する | ・現場で実際に使用しているものとテキストの図や写真を比較し、名称、形状、使い方を覚える。 |
これらの点を実践することで、単に暗記するのではなく、実践的なスキルとして身につき、試験での応用問題にも対応できるようになるでしょう。
ただし、「建設分野」の特定技能2号評価試験の難易度は非常に高いことから、学習テキストを活用しても不安が残る場合もあるでしょう。特に特定技能2号評価試験は、専門的な知識も多く、試験範囲も広いため、効率的な学習が求められます。
そのような場合は、明光グローバルの「特定技能2号(建設分野)試験対策講座」がおすすめです。
「建設分野」の試験対策なら明光グローバルにおまかせください
特定技能2号「建設分野」の試験は、専門知識と実務経験が問われる難関試験です。独学での合格が不安な方、効率的に学習を進めたい方は、ぜひ明光グローバルの試験対策講座をご検討ください。
経験豊富な講師陣と実績に基づいたカリキュラムで、合格をサポートします。最後に、明光グローバルの概要とその強み、提供するサービス内容について解説します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の育成と就労支援を通じて、日本企業の成長に貢献する教育系人材サービスを提供しています。教育と人材の専門家集団として、外国人材の能力開発と日本企業への定着を支援するなど、質の高いサービスが強みです。
主な事業内容は、次のとおりです。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
長年の実績に裏打ちされた教育ノウハウと、外国人材に特化したサポート体制が評価され、外務省からEPA事業を5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績があります。
特定技能2号(建設分野)試験対策講座の概要
明光グローバルの「特定技能2号(建設分野)試験対策講座」は、試験の合格を強力にサポートするオンライン講座です。講座の主な特徴は次のとおりです。
| 特徴 | 概要 |
| 専門講師がカリキュラムを作成してくれる | ・建設分野の専門知識を持つ日本語講師が、全8回のカリキュラムを作成してくれる ・基礎から応用まで、試験範囲を幅広くカバーしている ・講座カリキュラムは全15課 1ヶ月目:職長、現場管理、安全衛生活動の基礎知識 2ヶ月目:図面の見方、建設業の理解 3ヶ月目:模擬試験の実施と詳細な解答・解説 |
| 模擬試験で苦手分野を 可視化してくれる | ・本番形式の模擬試験で、時間配分や弱点を把握してくれる ・わかりやすい解説で、理解度を向上させられる |
| 日本語eラーニングを併用できる | ・日本語eラーニングシステム「Japany」を無料で使える ・講座時間外も、質の高い自主学習が可能なった |
受講スケジュールは、3名未満の場合は90分コース(全15回、合計22.5時間)、4名以上の場合は120分コース(全15回、合計30時間)となっています。また、講座はオンライン形式ですが、対面希望の場合は別途交通費が必要となり、最小催行人数3名、クラス上限8名です。
建設分野の特定技能2号試験対策でお困りの場合は、明光グローバルがサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
特定技能2号「建設分野」の試験合格には、公式テキストを熟読し、内容を深く理解するとともに、現場での実務経験と結びつけた学習が重要です。
学科試験では日本の建設現場の慣習や関連法規、専門用語の知識が問われ、実技試験では工具・機械・材料の適切な使用法、施工手順、安全対策に関する実践的な能力が試されます。独学での学習も可能ではありますが、より確実に合格を目指すのであれば、専門機関のサポートも検討しましょう。
明光グローバルでは、長年の教育実績と外国人材育成のノウハウを活かし、「特定技能2号(建設分野)試験対策講座」を提供しています。専門講師によるカリキュラム、模擬試験、eラーニングの組み合わせにより、効果的な試験対策が可能です。
建設業界の人材不足解消や外国人材のキャリアアップ、企業の競争力強化を目指す企業様は、明光グローバルへお気軽にお問い合わせください。