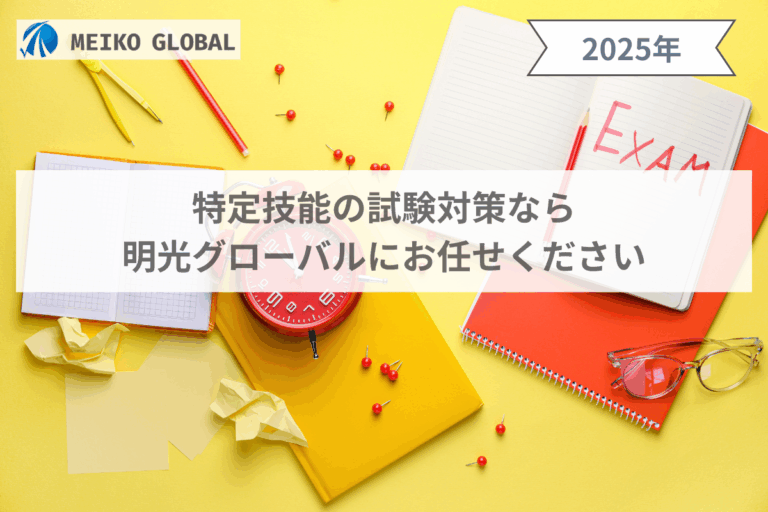介護業界の人手不足が深刻化するなか、「介護ビザを使って外国人材を採用したいけれど、制度が複雑でよくわからない」「介護の仕事を外国人材にしてもらいたいけれど、具体的にどうすれば良いのかわからない」「実際に雇用するにはどんな準備が必要?」と悩む企業担当者も多いのではないでしょうか。
外国人材の受け入れには、法制度への理解、社内体制の整備、日本語教育や生活支援など、準備すべき事項が多岐にわたります。特に在留資格「介護」は、人手不足の介護業界において長期的な人材活用を見据えた制度であり、正しい知識と実践的な対応が成功の鍵を握ります。
今回は、在留資格「介護」についてさまざまな疑問を抱える企業や採用担当者の方に向けて、2025年時点での最新情報に基づき、制度概要、申請要件、手続きの流れ、採用後の実務対応までをわかりやすく解説します。外国人介護人材を適切に受け入れるためのポイントを網羅してお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
在留資格とは
外国人材が日本で一定期間滞在し、就労や学習、生活を行うには、法務省が所管する出入国在留管理庁が定めた「在留資格」が必要です。在留資格には活動目的ごとに複数の種類があり、それぞれに認められる活動範囲や在留期間の上限、更新要件などが定められています。たとえば、「留学」「技能」「経営・管理」「永住者」などがその例としてあげられます。
介護業務に従事することができる在留資格としては、「介護」をはじめ、「特定技能(介護分野)」「技能実習(介護職種)」などがあります。在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人が、日本国内で専門職として介護業務に就くために設けられた制度です。
人手不足が深刻な介護現場で外国人材を受け入れる場合、必ず就労が認められる適切な在留資格を有していることが必要です。不適切な資格で就労させた場合には、雇用者側にも罰則が科される可能性があるため、在留資格の確認と管理は、法令遵守の観点からも極めて重要です。
介護施設で働ける在留資格の種類
外国人材が日本の介護現場で就労するには、主に「技能実習」「特定技能」「介護」という3つの在留資格のいずれかが必要です。それぞれ取得要件や就労範囲、在留期間に違いがあり、採用目的や長期雇用の可否によって適切な選択が求められます。ここでは、それぞれの在留資格の特徴について解説します。
技能実習
技能実習制度は、開発途上国の人材が日本で実務を通じて技能を習得し、帰国後にその技能を活かして母国の発展に寄与することを目的とした制度です。2017年から介護分野も対象職種に加わり、主にアジア諸国から多くの実習生が来日しています。
この制度では、初期段階では見習いとしての立場で実務を行いながら、段階的に技能習得を進めます。期間は1年から最大5年で、実習計画に基づいて運用され、就労の自由度や転職の可否には大きな制約があります。長期的な雇用を前提とした制度ではないため、継続的な人材確保には向きません。
また、技能実習では受け入れ企業が監理団体を通じて計画や監督を行う必要があり、実務対応に手間と時間がかかる点も事業者にとっての課題です。さらに、介護業界特有の高いコミュニケーション能力が求められる業務に対して、技能実習制度では語学力や文化理解が十分でないまま就労が開始されるケースも多く、現場とのミスマッチが発生しやすいという指摘もあります。
特定技能
特定技能制度は、介護分野を含む14の分野で導入されている就労制度です。「特定技能1号」は、所定の技能評価試験と日本語能力試験に合格した外国人材が、即戦力として最大5年間、日本で就労できる制度です。
この制度では、介護福祉士の資格がなくても、試験によって一定のスキルを証明することで介護業務への受け入れが可能となっています。また、2025年4月の制度改正により一定の条件を満たせば、訪問介護業務にも従事できるようになりました。ただし、在留期間は通算5年が上限で、更新回数にも制限があるため、将来的な長期雇用を見据える場合には限界があります。
特定技能制度のメリットは、比較的短期間で即戦力の人材を採用できる点にあります。ただし、在留期間満了後は基本的に帰国を前提とする制度であるため、企業側は定期的に人材を入れ替える必要があります。その結果、採用や教育にかかるコストが再び発生し、職場の人材定着にも課題が残ることがあります。
このように、特定技能制度には即戦力の確保という利点がある一方で、在留期間の上限やキャリア形成の制約といった限界もあります。そのため、継続的な戦力としての雇用を検討する企業にとっては、外国人材が将来的に在留資格「介護」へ移行できるような支援体制を整えておくことが、制度活用の成功につながります。
介護
在留資格「介護」は、国家資格である「介護福祉士」を取得した外国人材に与えられる在留資格です。2017年に制度化され、外国人材が安定して介護職として日本で長期的に働くことが可能になりました。
この制度では、在留期間の上限がなく、更新も継続的に可能です。さらに、転職や永住権取得も視野に入れることができるため、企業にとっても本人にとっても将来設計をしやすいという大きな利点があります。制度の安定性や人材の定着率の高さから、多くの介護事業者が導入を進めています。
また、在留資格「介護」では、サービス提供責任者やユニットリーダーといった管理職的な立場への登用も可能となっており、事業所の人材育成・キャリアパス設計にも大きく寄与します。特定技能ではできなかった職種への配置や、訪問介護への対応も制度改正により可能になっており、外国人材の活用の幅が広がっていることが特徴です。
在留資格「介護」とは
外国人材が日本で介護職として長期的に働くために設けられた在留資格が、「介護ビザ」と通称される在留資格「介護」です。この資格は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人材に与えられるものであり、他の在留資格と比較しても、制度的な安定性や継続雇用のしやすさにおいて優れています。
かつて、日本の介護現場で外国人材が働くルートは限定されており、技能実習制度やEPA(経済連携協定)を通じた比較的短期の受け入れが中心でした。しかし、深刻な人手不足と高齢化社会の加速を背景に、外国人材を中長期的に活用するための制度的整備が急務となり、2017年に在留資格「介護」が正式に導入されました。
この資格は、単に就労を認めるだけでなく、外国人材本人が日本社会に定着し、地域の介護事業を担う中核人材へと成長するための制度的な基盤として設計されています。外国人材の生活支援や地域との関わりを考慮したうえで、日本の介護業界に根ざした働き方を実現できる制度です。
在留資格「介護」の制度概要と導入背景
在留資格「介護」制度の導入背景には、介護職の慢性的な人材不足があります。2025年問題として知られる高齢者人口の急増により、介護需要は右肩上がりで増加し続けており、厚生労働省の推計によれば、2040年には約280万人以上の介護人材が必要とされる状況です。
一方で、国内の労働人口は減少しており、若年層の介護職離れも続いています。こうした背景から、国としても外国人材の活用を本格的に推進せざるを得なくなり、単なる「人手」ではなく、職能を備えた「人材」として介護福祉士資格を持つ外国人材を長期的に受け入れる仕組みが整えられたのです。
在留資格「介護」は、他の在留資格に比べて就労範囲が広く、かつ永住許可申請への道も開かれていることから、外国人材本人にとっても魅力的な選択肢であり、多くの留学生がこの資格取得を目指しています。制度的には「専門的・技術的分野」に分類され、他の技術者ビザと同様の待遇・権利が認められます。
対象となる職種と業務内容の具体例
在留資格「介護」を持つ外国人材が従事できる職種は、主に施設系の介護業務が中心です。業務内容は多岐にわたり、介護福祉士としての専門的なスキルを活かした幅広い対応が求められます。
たとえば、利用者の食事・入浴・排せつの介助、移動支援、服薬の管理、認知症ケア、レクリエーションの企画・実施、介護記録の作成・報告などが業務内容には含まれます。
また制度上、在留資格「介護」は以前から訪問介護(いわゆるホームヘルプ)などの訪問系サービスにも従事することが可能とされており、地域の在宅介護分野においても活躍の場が広がっています。2025年4月には、特定技能や技能実習制度においても訪問系サービスへの従事が解禁され、外国人介護人材の活躍の場はますます多様化しています。
さらに、介護福祉士としての専門性を活かし、ユニットリーダーやサービス提供責任者といった役職に就くことも可能です。外国人材が単なる補助業務にとどまらず、職場の中核人材としてステップアップできる制度的環境が整っており、現場でもその成長が期待されています。
在留資格「介護」の特徴
在留資格「介護」の最大の特徴は、「無期限更新が可能であること」と「職業としての安定性」が両立していることです。在留資格「特定技能」では最長5年間の就労制限があり、「技能実習制度」では母国への帰国を前提とする設計であるのに対し、「介護」は長期雇用を前提に設けられているため、企業側にとっては人材の定着性を高めやすい仕組みといえます。
また、永住許可申請も一定の条件を満たせば可能であり、外国人材本人が日本での生活基盤を築き、長く働き続ける動機づけにもつながります。これにより、外国人介護人材が地域に根づき、利用者や職員との信頼関係を構築しやすくなるという好循環が生まれます。
さらに、「介護福祉士」という国家資格を有していることが大きなアドバンテージとなり、日本人と同等以上の業務遂行能力があることを示す証明にもなります。介護業務は単なる力仕事ではなく、高い専門性とコミュニケーション能力を要する仕事であるため、資格保有による信頼性は現場でも非常に重要な要素となります。
在留資格「介護」が最も安定的な選択肢とされる理由
介護業界における外国人材の在留資格のなかで、「介護」は最も長期的かつ安定的な雇用が可能な制度とされています。その背景には、制度設計の柔軟性と信頼性、そして外国人本人にとっても企業側にとっても高いメリットが存在することが挙げられます。ここでは、「介護」ビザが他の在留資格と比較して有利である理由について解説します。
- 在留期間や更新要件に制限が少ないから
- 介護福祉士としての国家資格による専門性が保証されるから
- 永住・転職・キャリアアップの自由度が高いから
在留期間や更新要件に制限が少ないから
在留資格「介護」は、更新回数に制限がありません。外国人材が介護福祉士としての職務に継続的に従事していれば、原則として在留資格の更新を何度でも行うことができ、実質的に無期限の滞在が可能となります。これは、技能実習(最長5年)、特定技能1号(最長5年)といった制度と比較すると、格段に柔軟で安定的な制度設計といえます。
また、在留資格の更新にあたっても、介護福祉士資格を保有していれば、大きな審査リスクも少なく、企業としては長期間の人材育成や戦力化を前提とした雇用計画が立てやすくなります。これは職場における人材の定着率向上や、採用コストの低減にもつながり、結果として経営上の大きなメリットをもたらします。
さらに、制度的に転職も可能であるため、外国人材本人がよりよい職場環境を求めてキャリア形成を進めることもでき、企業側も能力の高い人材を採用するチャンスが広がります。これは閉鎖的な制度では得られない、健全な人材の流動性を確保する上でも大きな意味を持ちます。
介護福祉士としての国家資格による専門性が保証されるから
在留資格「介護」の取得には、国家資格である介護福祉士の取得が必須です。この資格は、日本国内で約450時間の養成課程や実務経験、国家試験を経て取得するものであり、知識・技能・倫理観など多方面の能力が求められます。
外国人材がこの資格を取得するためには、日本語能力試験(JLPT)のN2相当以上が必要となるほか、専門用語を含む実技試験や学科試験への対応も求められます。これにより、日本人の同僚と同等レベルの介護技術と専門知識を有していることが制度的に保証されており、現場における即戦力としての信頼性が非常に高くなります。
また、国家資格保持者という社会的信用は、介護施設にとっても利用者にとっても安心材料となり、外国人材への抵抗感や不安を取り除く効果もあります。実際に、介護福祉士資格を有する外国人スタッフがリーダー業務や後輩指導を担うケースも増えており、介護の質的向上にも貢献しています。
永住・転職・キャリアアップの自由度が高いから
在留資格「介護」は、「専門的・技術的分野」に分類されており、将来的に永住権の取得が視野に入ります。一定の在留期間や収入水準、納税実績などを満たすことで、外国人材本人が「永住者」としての在留資格を申請することが可能になります。これは本人の生活基盤の安定だけでなく、企業側にとっても長期雇用を見据えた人材戦略を構築する大きな助けとなります。
また、「介護」ビザを持つ外国人材は、原則として転職も可能です。これは技能実習制度や特定技能制度とは異なり、柔軟なキャリア形成が許容されていることを意味します。つまり、本人の能力や適性に応じた職場選びができることで、モチベーションの維持や職場での定着率向上が見込まれます。
さらに、資格取得者であるがゆえに、介護業務のみにとどまらず、将来的にはケアマネジャーへの挑戦や、福祉系大学への進学など、より高度なキャリアを目指すことも可能です。これは外国人材自身の人生設計にとっても意義深く、優秀な人材の流入・定着を促す好循環を生み出しています。
在留資格「介護」を取得するための要件
ここまで解説したように、外国人材が日本国内で介護福祉士として就労するための専門的な在留資格が「介護」です。この資格を得るには、一定の学歴・資格・雇用契約といった複数の条件を満たす必要があります。特に高度な日本語能力や介護福祉士国家資格の取得が前提となるため、他の在留資格と比べても取得ハードルはやや高くなります。
しかし、それゆえに制度上の信頼性が高く、取得者は専門性の高い人材として評価される傾向にあります。ここでは、外国人が在留資格「介護」を取得するために必要となる4つの主な要件について解説します。
- 介護福祉士の資格を取得していること
- 日本の介護施設等と適正な雇用契約を締結していること
- 従事する業務が介護業務に該当すること
- 日本人と同等以上の報酬水準であること
介護福祉士の資格を取得していること
在留資格「介護」の最も基本的な要件は、日本で「介護福祉士」の国家資格を取得していることです。この国家資格は、一定の課程を修了し、国家試験に合格した者に対して厚生労働省が認定するものであり、日本人でも容易に取得できるものではありません。
外国人材が介護福祉士を目指す主なルートとしては、日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校や大学など)に2年以上通い、修了後に国家試験に合格するという方法が一般的です。これには留学ビザでの来日と滞在が必要となり、日本語能力試験N2以上の取得、専門用語への理解、実習など、多面的な準備が求められます。
なお、EPA(経済連携協定)や特定の送出し国での研修制度など、海外での資格取得ルートも一部認められており、それぞれで求められる条件や手続きは異なります。いずれのケースでも、介護福祉士として正式に登録されていなければ、「介護」ビザの申請は認められません。
日本の介護施設等と適正な雇用契約を締結していること
在留資格「介護」を取得するには、就職先がすでに決定しており、介護関連事業を営む日本の法人と雇用契約を締結している必要があります。契約書には、勤務地・職務内容・就業時間・給与額・福利厚生などが明記され、契約内容が適切であることが求められます。
特に重要なのが、業務内容が「介護福祉士としての業務」であることを明確に記載していることです。単なる清掃や配膳、洗濯といった補助業務のみの場合は対象外とされる可能性があるため、身体介護や生活支援を中心とした職務であることを示す必要があります。
また、雇用契約の内容は入国管理局(出入国在留管理庁)による審査の対象にもなるため、不適切な契約内容や不明瞭な表現がある場合、在留資格の認定が下りないケースもあります。そのため、慎重な契約書作成と審査対策が重要となります。
従事する業務が介護業務に該当すること
在留資格「介護」で許可される業務は、あくまで介護福祉士としての業務に限定されています。つまり、介護報酬の算定が可能な身体介護・生活援助・記録作成・家族対応・リーダー業務など、専門的かつ実務的な役割を担う必要があります。
また制度上、訪問介護業務についても、在留資格「介護」を持つ外国人材は従来から従事可能とされていました。2025年4月には特定技能や技能実習制度でも訪問介護が解禁されましたが、「介護」資格保持者についてはすでに在宅介護への従事が認められており、訪問系サービスにおいても活動の幅を広げることができています。
ただし、いずれの業務においても、一定の研修や体制整備が必要とされる場合があり、すべての介護ビザ保持者が自動的に訪問介護を行えるわけではありません。事業所側にも、適切な指導や同行支援体制の構築が求められます。
逆に、洗濯、清掃、調理といったいわゆる「単純作業」のみを担当させることは制度上認められておらず、もしそれらの業務に偏った配置を行った場合は、在留資格違反と見なされる可能性があります。企業側には、業務内容の適正な設定と運用が求められます。
日本人と同等以上の報酬水準であること
外国人材に対して在留資格「介護」を付与する条件として、その雇用条件が日本人と同等以上であることが求められます。これは、外国人差別や不当な労働搾取を防ぐ目的で設けられた制度的な基準であり、実際の雇用契約書には賃金水準の適正性が反映されている必要があります。
たとえば、日本人介護福祉士と同等の業務に就いているにもかかわらず、著しく低い賃金を支払っている場合や、手当の未支給、残業代未払いなどがある場合は、制度違反と判断され、在留資格の取得・更新が認められなくなるリスクがあります。
また、労働条件に関するトラブルは外国人材の早期離職にも直結し、企業にとっても信頼の低下や行政からの指導対象となることがあります。そのため、給与規定の整備や就業規則の適正化も、採用前の重要な準備項目として位置づけられます。
在留資格「介護」の外国人材の採用前に必要な手続き
外国人材を在留資格「介護」で受け入れるには、企業側が事前に整えておくべき法的・実務的な手続きが数多くあります。ただ単に「採用する」と決めるだけでは十分ではなく、在留資格の申請準備から労働契約の整備、就労後の生活支援体制まで、広範囲にわたる準備が求められます。
適切な段取りを踏まないまま進めてしまうと、申請が通らなかったり、就労後にトラブルが発生したりする恐れがあるため、企業担当者は制度の流れを正しく理解し、万全の準備体制を整えておく必要があります。ここでは、採用前に取り組むべき主要な手続き項目について解説します。
- 在留資格変更・認定申請の流れを把握する
- 雇用契約書に記載すべき法定項目を確認する
- 就労開始に向けた受け入れ体制を整える
在留資格変更・認定申請の流れを把握する
外国人材が在留資格「介護」で日本で働くには、主に2つのケースが想定されます。
1つ目は、日本国内で介護福祉士養成施設を修了し、国家試験に合格した外国人留学生が「留学」ビザから「介護」ビザへ在留資格を変更するケースです。この場合は、「在留資格変更許可申請」として、入国管理局に必要書類を提出し、審査を受けることになります。通常、在学中の卒業見込証明や国家試験合格通知などが必要です。
2つ目は、すでに海外で介護福祉士資格を取得している人材を、日本企業が現地から採用し、日本へ呼び寄せるケースです。この場合は「在留資格認定証明書交付申請」を企業側が行い、交付された認定証明書を本人に送付し、それを基に本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行います。来日後には在留カードが発行され、正式に就労が可能となります。
いずれの場合でも、申請書類の不備や記載ミスがあると審査が長引く、あるいは不許可となる可能性があります。そのため、専門家のサポートや経験者の確認を経て、確実な申請を心がけることが重要です。
雇用契約書に記載すべき法定項目を確認する
外国人材との雇用契約書は、単なる雇用の証明ではなく、入管審査において重要な判断材料となります。そのため、契約書の記載内容には法定項目が適切に網羅されている必要があります。具体的には、次の内容を明記することが求められます。
- 勤務地の名称・住所
- 職務の内容(介護福祉士としての業務であること)
- 労働時間・休憩時間・休日
- 賃金(基本給・手当等の内訳)
- 社会保険加入の有無
- 雇用期間と契約更新の有無
- 解雇・退職のルール
- その他福利厚生の内容(住宅支援、日本語教育、交通費など)
特に「職務内容」があいまいなままだと、「単純労働ではないか」「資格に見合わない業務ではないか」といった審査上の疑義を生むことがあります。正確かつ詳細に、介護福祉士として従事する職務であることを記載し、制度の趣旨に沿った契約書を作成しましょう。
就労開始に向けた受け入れ体制を整える
採用が決定した後は、本人の来日前後の生活や就労をスムーズにスタートさせるための「受け入れ体制」を整える必要があります。これは企業にとって重要な責任であり、制度上も職場定着やトラブル防止の観点から、厚生労働省や出入国在留管理庁が推奨している対応です。
まずは、住居の確保です。単身用の社宅、借り上げ住宅など、通勤可能なエリアにある住環境を提供することが望まれます。加えて、ゴミ出しのルールや電気・ガス・水道の契約、役所での手続きなど、生活インフラに関する案内も必要です。
次に、日本語研修や職場内OJTの体制を整備することが求められます。介護現場では高いコミュニケーション能力が求められるため、最低限の言語理解が必要です。業務マニュアルの多言語化や、ピクトグラム(図解)を用いた説明ツールの導入も有効です。
さらに、職員間の多文化理解を深めることも重要です。外国人介護人材が働きやすい職場環境を整えるためには、既存スタッフへの研修や、文化の違いに対する配慮を促すことも効果的です。人材を単に「雇う」のではなく、「共に働く仲間」として受け入れる姿勢が、長期的な職場定着につながります。
在留資格「介護」の申請・入社までの流れ
外国人材を在留資格「介護」で正式に採用し入社まで導くには、いくつかの法的・実務的な手続きを段階的に進めていく必要があります。特に在留資格の取得に関わる申請は、外国人本人の状況(国内在住か国外在住か)によって手続きが異なるため、企業側は事前にその違いを理解し、スムーズな入社スケジュールを組むことが求められます。
ここでは、よくある2つのケース(日本国内で介護福祉士資格を取得した外国人留学生の場合と、海外から人材を招聘する場合)に分けて、入社までの流れを解説します。
日本国内にいる留学生のケース:在留資格「留学」からの変更
日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校・短期大学・大学など)を卒業し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人留学生は、在留資格「留学」から「介護」への変更申請を行うことになります。
この申請は外国人材本人が主体となって出入国在留管理局に提出しますが、就職先企業が申請をサポートすることが一般的です。提出に必要な主な書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書
- 卒業証明書
- 介護福祉士登録証(または合格証書)
- 雇用先の日本人と同等以上の報酬を証明する書類
- 雇用先の登記簿謄本、事業内容資料
- 本人の在留カードとパスポート
通常、審査期間は1ヶ月から2ヶ月程度ですが、書類の不備や内容不明瞭な点があると審査が長引いたり、追加書類の提出を求められたりする場合があります。
スムーズな手続きのためには、学校・就職先・本人の三者間で緊密に連携し、必要書類の準備と申請タイミングを誤らないよう注意が必要です。また、就労開始日が卒業・資格取得とずれないよう、スケジュール調整にも留意しましょう。
海外から直接呼び寄せるケース:在留資格認定証明書の取得
すでに介護福祉士資格を有する外国人材を海外から採用する場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を企業側が行う必要があります。これは日本国内での代理申請となり、外国人本人が日本大使館でビザを申請するための重要な書類です。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類には、次のようなものがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書の写し
- 介護福祉士資格を証明する書類(登録証・合格証など)
- 会社の登記事項証明書、事業内容説明書、決算書
- 雇用先の介護サービス内容の説明資料(施設概要など)
入国管理局での審査期間は約1ヶ月半から2ヶ月が一般的ですが、最近ではオンライン申請も可能になっており、事前準備をしっかり行えばスムーズな審査が期待できます。
在留資格認定証明書が交付されたら、企業がそれを海外の本人に送付し、本人は現地の日本大使館・領事館で「就労ビザ(介護)」を申請します。ビザが発給されたら、来日後に入国審査を経て、在留カードが発行され、正式に就労開始となります。
雇用契約書の整備と必要書類の準備
申請手続きにおいて、最も審査で重視されるのが雇用契約書の記載内容と、付随する関連書類の整備です。
たとえば、雇用条件が日本人と同等以上であることを証明するためには、賃金規程や就業規則の抜粋などの提出が必要になるケースもあります。また、介護福祉士の登録証明書や、資格取得証明書、日本語能力を示す書類(日本語能力試験(JLPT)N2以上が望ましい)なども、審査において信頼性を高める要素となります。
申請書類の作成に不慣れな場合は、行政書士や外国人材支援サービスなどの専門家に相談することで、より確実に進められます。書類不備による不許可を避けるためにも、事前確認は入念に行いましょう。
入社に向けたスケジュールと受け入れ体制の整備
在留資格の取得が認められた後、いよいよ入社・就労開始となりますが、その前に企業としては次のような準備を済ませておく必要があります。
- 社内OJTの計画:初期研修、業務マニュアルの用意
- 多文化対応研修:既存スタッフ向けの異文化理解促進
- 社会保険加入手続き:健康保険、厚生年金、労災保険
- 生活サポート:住居案内、携帯契約、銀行口座開設支援
- 定着支援計画:定期面談、日本語学習支援、メンター制度
こうした受け入れ準備が整っていないと、入社直後から業務に支障が出たり、本人の不安やストレスが高まったりして、早期離職につながるリスクもあります。制度的には義務ではなくとも、企業の「定着支援力」が外国人介護人材の活躍を大きく左右します。
介護福祉士の試験対策は明光グローバルに任せください
外国人材を在留資格「介護」で採用するには、国家資格である「介護福祉士」の取得が必要です。しかし、介護分野で就労したい外国人の多くにとって、日本語での専門用語を含む国家試験を受験・合格することは非常に高いハードルとなります。そのため、制度的に受け入れ体制が整っていたとしても、介護福祉士資格取得までの学習・教育支援が不十分であれば、受験者の多くが挫折してしまう可能性があります。
このような課題に対し、明光グローバルでは、外国人介護人材に特化した国家試験対策講座や日本語教育、就労支援までを一貫して提供しています。介護現場で即戦力となる人材を安定的に育成するために、多くの企業や教育機関が明光グローバルのサポートを活用しています。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービス内容を紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
介護福祉士の試験対策講座
明光グローバルは、外国人向けに特化した介護福祉士の試験対策講座を提供しています。外国人受験者特有の課題に対応しており、効果的な学習方法を取り入れているのが特徴です。
介護福祉士の試験対策講座
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 段階的学習プラン | ・基礎日本語から専門知識まで、レベルに応じた学習 ・日本語能力試験(JLPT)N5からN2以上まで、幅広い日本語能力に対応 |
| 実践的な訓練 | ・語彙力、読解力強化の集中トレーニング ・実践的なケーススタディによる知識の定着 |
| 柔軟な学習形態 | ・講座の実施方法(オンライン・対面いずれかを選択可) ・受講人数:企業様のご要望に応じて柔軟に対応可能 |
| 専門性の高いサポート | ・介護現場経験のある日本語教師による指導 ・介護の日本語教育専門家による監修 〇特徴:高い合格実績 〇内容:日本人の合格水準にならぶ高い合格実績(81%) |
介護福祉士の試験対策講座は、日本語能力の向上と介護専門知識の習得を、同時に進められます。また、外国人材がつまずきやすいポイントも網羅されているので、不安なく試験に挑むことができるでしょう。
明光グローバルの強み
明光グローバルは、外国人向け介護福祉士試験対策において、次の強みを持っています。
| 強み | 内容 |
|---|---|
| 確かな実績 | ・日越EPA訪日前日本語研修事業を4年連続で受託 ・90%以上のEPA候補生がJLPT N3に1年で合格 |
| 教育ノウハウ | ・40年にわたる塾事業の経験を活かした試験対策カリキュラム ・過去問分析に基づく効率的な学習教材の開発 |
| 専門的な日本語教育 | ・2校の日本語学校を運営 ・年間2,000人以上の留学生受け入れ実績 |
| 現場に即した指導 | ・介護事業所での勤務経験を持つ日本語教師による研修 ・実践的な知識を活かした国家試験対策 |
| 専門家の監修 | ・東京都立大学名誉教授・西郡仁朗氏によるカリキュラム監修 |
日本語能力試験(JLPT)N3レベルの合格率が90%を超えていることからも、明光グローバルが開発した試験対策は多くの受験者に対して効果が見込めます。
まとめ
在留資格「介護」は、制度的な安定性と専門性を兼ね備えた、介護業界での就労を希望する外国人介護人材にとって最も現実的で将来性のある在留資格です。技能実習や特定技能といった他の制度と比較しても、更新制限がない、国家資格に基づいて就労できる、永住許可申請や転職が可能であるなど、数多くのメリットがあります。
一方で、この資格を活用するためには、企業側にも制度理解・申請準備・受け入れ体制構築など、段階的かつ実務的な対応が求められます。特に初めて外国人材を採用する企業にとっては、在留資格の違いや手続きの流れに戸惑うことも多いため、信頼できる支援機関との連携が成功の鍵を握ります。
明光グローバルでは、外国人材の採用前の教育から在留資格申請、試験対策、就労後の定着支援に至るまで、トータルのサポートを提供しています。外国人介護人材を「単なる人手」としてではなく、職場の仲間・長期戦力として迎え入れたいと考える企業にとって、最適なパートナーとなるでしょう。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。