特定技能「製造業」は、人手不足が深刻な日本の製造業にとって、専門技術を持つ即戦力外国人材を確保し、事業の持続的成長を支えるための重要な在留資格制度です。この制度を効果的に活用することで、企業は労働力不足の解消や技術力の維持・向上に期待できます。
しかし、特定技能「製造業」での外国人材受け入れには、制度への深い理解、採用時の注意点の把握、複雑な申請手続きへの対応など求められる事項は多いです。今回は、特定技能「製造業」の概要から申請要件や手順に至るまで、外国人材の採用・育成をスムーズに進めるためのポイントを解説します。製造業の経営者様、人事担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
特定技能「製造業」とは
人手不足が深刻な製造業において、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にするのが特定技能「製造業」です。この制度は、日本のものづくりを支える重要な仕組みとして注目されています。ここでは、特定技能「製造業」の基本的な概要や業務内容、特定技能活用の現状について詳しく解説します。
特定技能「製造業」の概要
特定技能「製造業」は、国内での人材確保が特に難しい製造業分野で、専門知識や技能を持つ外国人材に即戦力として活躍してもらうための在留資格です。2019年4月にスタートし、深刻な人手不足の解消と、日本の高い技術力の維持・発展を目的としています。
特定技能「製造業」で働く外国人材には、作業員としての能力に加え、次のような能力が求められます。
- 自律的な業務遂行能力:管理者の指示を正確に理解し、自らの判断で業務を進める力が必要になる。
- 監督・指導能力(特定技能2号の場合):複数の従業員を指導し、工程全体を管理する力が求められる。
- 製造プロセス全体への理解:自身の担当業務だけでなく、製造工程全体を把握する力が必要になる。
これらの能力を持つ人材が、日本の製造現場における生産性向上や品質管理に大きく貢献することを期待しています。
特定技能「製造業」の10つの業務内容
特定技能「製造業」では、外国人材の専門性や技能に応じて、従事する業務が10種類の区分に分類されています。
- 機械金属加工区分
- 電気電子機器組立て区分
- 金属表面処理区分
- 紙器・段ボール箱製造区分
- コンクリート製品製造区分
- RPF製造区分
- 陶磁器製品製造区分
- 印刷・製本区分
- 紡織製品製造区分
- 縫製区分
ここでは、それぞれの区分について詳しく解説します。
参照元:
機械金属加工区分
機械金属加工区分は、自動車部品から産業機械、精密機器に至るまで、あらゆる製品の基盤となる部品や部材を製造する、ものづくりの根幹を支える重要な分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- 鋳造
- 鍛造
- ダイカスト
- 機械加工
- 金属プレス加工
- 鉄工
- 工場板金
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 機械検査
- 機械保全
- 電子機器組立て
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
- 強化プラスチック成形
- 金属熱処理業
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事する区分となります。
電気電子機器組立て
電気電子機器組立て区分は、スマートフォンや産業用ロボットなど、現代社会に欠かせない電気電子機器の製造・組立工程に携わる分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- 機械加工
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 電子機器組立て
- 電気機器組立て
- プリント配線板製造
- 強化プラスチック成形
- 機械検査
- 機械保全
- 工業包装
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事する区分となります。
金属表面処理
金属表面処理区分は、金属製品の耐食性、耐摩耗性、美観などを向上させるための重要な技術分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理(アルマイト)
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、表面処理等の作業に従事します。
紙器・段ボール箱製造区分
紙器・段ボール箱製造区分は、日用品のパッケージから工業製品の輸送用ケースまで、私たちの生活や産業活動に不可欠な紙製の箱や容器を製造する分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- 紙器・段ボール箱製造
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事します。
コンクリート製品製造区分
コンクリート製品製造区分は、道路の側溝や縁石、建物の壁材や床材など、社会インフラの整備や建築に用いられるさまざまなコンクリート製品を工場で生産する分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- コンクリート製品製造
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事します。
RPF製造区分
RPF製造区分は、主に産業系の古紙や廃プラスチックといった廃棄物を原料として、高カロリーな固形燃料を製造する環境貢献型の分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- RPF製造
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事します。
陶磁器製品製造区分
陶磁器製品製造区分は、食器や花瓶、タイル、衛生陶器、美術工芸品など、日常生活や産業分野で広く利用される陶磁器製品を製造する分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- 陶磁器工業製品製造
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事します。
印刷・製本区分
印刷・製本区分は、書籍、雑誌、カタログ、チラシ、パッケージなど、情報伝達や製品の付加価値向上に貢献する印刷物を製造し、それらを最終的な形に仕上げる分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- 印刷
- 製本
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事します。
紡織製品製造区分
紡織製品製造区分は、衣料品やインテリア製品、産業資材など、私たちの生活やさまざまな産業で用いられる糸や布地、最終製品までを製造する幅広い分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- 紡績運転
- 織布運転
- 染色
- ニット製品製造
- たて編ニット生地製造
- カーペット製造
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事します。
縫製区分
縫製区分は、衣料品(婦人子供服、紳士服、下着類など)、寝具、カーテン、鞄、自動車のシートカバーといったさまざまな布製品を、デザインや仕様書に基づいて作り上げる分野です。従事する主な業務は次のとおりです。
- 婦人子供服製造
- 紳士服製造
- 下着類製造
- 寝具製作
- 帆布製品製造
- 布はく縫製
- 座席シート縫製
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、縫製工程の作業に従事します。
特定技能「製造業」における在留外国人数は増加傾向
特定技能制度を活用し、日本の製造業で活躍する外国人材の数は、制度開始から年々増加しています。出入国在留管理庁の最新データ(令和5年12月末)によると、製造業の分野だけでも、特定技能1号の在留外国人数は40,069人に達しました。
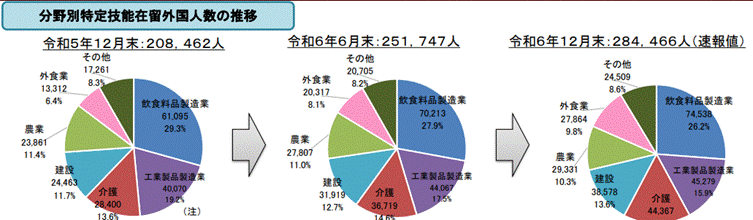
画像引用元:特定技能制度運用状況(令和6年12月末)(出入国在留管理庁)
特定技能「製造業」における在留外国人数が増加している背景には、次の要因が影響していると考えられています。
- 少子高齢化による生産年齢人口の減少している
- 若年層の製造業離れが進んでいる
- 即戦力となる外国人材への高いニーズが高い
これらの要因により、製造業における特定技能外国人材の受け入れは増加傾向にあります。今後もこの流れは続くと予想されており、日本のものづくり現場において、外国人材が果たす役割はますます重要になってくるでしょう。
特定技能「製造業」で外国人材が求められる主な理由
日本の製造業において、特定技能を持つ外国人材の受け入れが積極的に進められています。その背景には、国内の労働市場だけでは解決が難しい、構造的な課題が大きいです。ここでは、特定技能「製造業」で外国人材が求められる主な理由を解説します。
- 少子高齢化による深刻な労働力不足を補うため
- 即戦力人材を確保できるため
- 長期的に人材を抱え込めるため
- 受け入れ人数に制限がないため
- 教育コストを最小限に抑えられるため
少子高齢化による深刻な労働力不足を補うため
日本の製造業が特定技能外国人材に期待を寄せる理由の一つには、国内の深刻な労働力不足が関係しています。下のグラフは、生産年齢人口のこれまでの推移と将来の推計を表したものです。
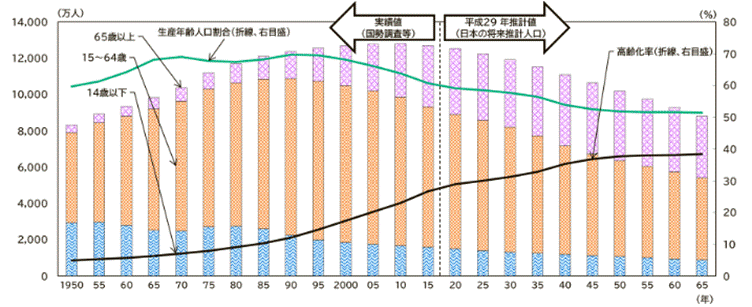
画像引用元:第2-(1)-1図 我が国の生産年齢人口の推移と将来推計(厚生労働省)
生産年齢人口は右肩下がりに減少を続け、2065年には50%近くまで減少すると予測されているほどです。
少子高齢化が進み生産年齢人口が減少し続けると、国内の求職者だけでは必要な人員を確保することが困難になっています。特定技能制度を活用すれば、一定のスキルを持つ外国人材を安定的に受け入れられるため、事業の継続と発展を支える重要な手段として注目されています。
即戦力人材を確保できるため
特定技能「製造業」で外国人材が求められる理由の一つに、即戦力として活躍が期待できる点が挙げられます。外国人材は、特定技能の在留資格取得にあたり、次の試験に合格しているため、一定の能力が保証されています。
- 専門的な技能試験:「製造分野特定技能1号評価試験」など
- 一定レベルの日本語能力を測る試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上 など
そのため、受け入れ企業は採用後すぐに現場で活躍できる人材を確保でき、一から専門技術や日本語を教育する手間や時間を大幅に削減できるというメリットがあります。
長期的に人材を抱え込めるため
外国人材を長期間雇用できる点も、特定技能「製造業」の外国人材が求められる理由です。これにより、安定した人員計画の策定や採用コストの削減が期待できます。特定技能1号・2号の在留期間は次のとおりです。
- 特定技能1号:通算上限5年(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新)
- 特定技能2号:上限なし(3年、1年または6ヶ月ごとの更新)
特に熟練した技術の習得に時間を要する製造業において、長期的な視点で人材を育成し、企業の技術力向上に貢献してもらえる点が大きなメリットといえるでしょう。その結果、採用活動や人材の入れ替えに伴うコストと手間を削減することにもつながります。
受け入れ人数に制限がないため
特定技能「製造業」分野の大きなメリットには、企業ごとの受け入れ人数に上限がない点です。企業は次のような状況に応じて、必要な数の外国人材を柔軟に採用できます。
- 事業規模に応じた人材確保
- 大規模工場など、多くの人手が必要
- 特定の専門スキルを持つ人材を複数名確保が必要
このように、人材不足の状況や企業の成長戦略に合わせて、必要な人材を必要なだけ確保できる柔軟性は、事業拡大や生産体制の強化を目指す企業にとっては大きな魅力です。
教育コストを最小限に抑えられるため
特定技能外国人材の活用は、教育にかかるコストと時間を大幅に削減できる点も魅力の一つです。なぜなら、外国人材は既に関連業務の一定技能と日本語能力を備えているからです。
たとえば、国内で未経験の人材を採用する場合、次のような教育コストがかかります。
- 基礎的な技術指導
- 安全衛生教育
- 専門知識の習得
しかし、特定技能外国人材の場合、これらの教育負担を大幅に軽減・省略できる可能性があります。結果として、採用した人材を迅速に現場へ配置でき、生産性向上も期待できるでしょう。
特定技能「製造業」で外国人材を採用する際の注意点
特定技能「製造業」で外国人材を採用することは、人手不足解消の有効な手段ですが、注意点もあります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて、具体的な内容と対策を解説します。
- コミュニケーション不足によるトラブルが発生しやすい
- 申請手続のミスや不備がないようにする
- 煩雑な受け入れ体制を整備する
コミュニケーション不足によるトラブルが発生しやすい
特定技能「製造業」で外国人材を受け入れる際、最も注意すべき点の一つがコミュニケーション不足によるトラブルです。言語や文化の違いから、次のような問題が発生する可能性があります。
- 業務上のミスマッチ:指示や報告が正確に伝わらず、作業ミスや製品不良、納期遅延につながる
- 契約・労働条件の誤解:雇用契約の内容や日本の労働慣行、社会保険制度などを十分に理解できていない場合、不満や不信感につながる
- 職場での孤立:日本人従業員との意思疎通がうまくいかず、孤立感やストレスを抱え、定着率の低下を招く
トラブルを防ぐには、多言語対応の作業マニュアルの作成、翻訳アプリの導入、母国語を話せるスタッフの配置など、コミュニケーションの工夫が重要です。また、定期的な面談を通じて、外国人材が抱える不安や疑問を早期に把握し、解決に努める姿勢も大切です。
申請手続のミスや不備がないようにする
特定技能外国人材の受け入れには、複雑な申請手続きが伴います。書類のミスや不備は、申請不受理や審査遅延、最悪の場合は不許可につながるため注意が必要です。
申請する際は、外国人材本人だけでなく、受け入れ企業側の体制や雇用条件に関する詳細な情報も求められます。提出書類の種類が多く、記載内容も複雑なため、制度を正確に理解し、細心の注意を払って手続きを進めることが重要です。
不備があると、時間と労力を無駄にするだけでなく、人材確保の計画にも影響が出かねません。
煩雑な受け入れ体制を整備する
特定技能外国人材の受け入れ企業には、彼らが日本で安心して就労・生活できるよう、多岐にわたる支援体制の整備が義務付けられています。そのため、外国人材の受け入れ担当者には、専門知識や多大な時間・労力が必要とされています。
具体的には、住居の確保、銀行口座の開設や携帯電話の契約といった生活に必要な契約のサポート、日本の生活習慣やルールを教える生活オリエンテーションの実施も必要です。また、日本語学習機会の提供、定期的な面談や相談・苦情への対応などが求められます。
さらに、経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入も必須です。これらの準備は、専門的な知識やノウハウが必要となる場合も多く、企業にとっては大きな負担となるでしょう。
申請手続きの複雑さや受け入れ体制整備の負担を軽減するには、専門知識を持つ「登録支援機関」に業務を委託することも有効な選択肢の一つです。登録支援機関は、煩雑な業務を代行し、企業がスムーズに外国人材を受け入れられるよう支援してくれます。
特定技能「製造業」の取得要件
特定技能「製造業」の在留資格を得て日本で働くには、外国人材と受け入れ企業の双方が、定められた基準をクリアする必要があります。ここでは、外国人材自身に求められる要件と、受け入れ企業が満たすべき主な条件についてそれぞれ詳しく解説します。
参照元:
外国人材側の要件
特定技能「製造業」で外国人材が就労するには、外国人材自体が満たすべき要件があります。ただし、「特定技能1号」と「特定技能2号」では、求められる技能水準や在留期間、家族帯同の可否などが異なります。違いを理解することは、受け入れ企業にとっても適切な人材育成や配置を考える上で重要です。
特定技能1号と特定技能2号の主な違いをまとめると、下の表のようになります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 1年を超えない範囲内で指定された期間ごとの更新(通算で上限5年) | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし)上限なし |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 対象業務区分 (2号のみ) | ー | 機械金属加工区分 電気電子機器組立て区分 金属表面処理区分 |
| 技能試験 | 各分野の製造分野特定技能1号評価試験に合格する | ・各分野の製造分野特 以下の2ルートの内、1ルートの取得及び合格が必要になる 【ルート1】 ①ビジネス・キャリア検定3級取得 (生産管理プランニング区分、生産管理オペ レーション区分のいずれか) ②製造分野特定技能2号評価試験の合格 (機械金属加工区分、電気電子機器組立て 区分、金属表面処理区分のいずれか) 【ルート2】 ①技能検定1級取得 (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス 加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極 酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子 機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製 造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか) |
| 日本語能力試験 | 一定水準以上(試験合格または技能実習2号修了など) | 不要 |
| 実務経験 | 必要なし | 日本国内における3年以上実務経験 |
これらの要件を満たすことで、外国人材は特定技能「製造業」の在留資格を取得し、日本の製造現場で働くことができます。
受入れ企業側の要件
特定技能「製造業」で外国人材を受け入れる企業には、満たすべき要件があります。受け入れ企業側の要件は、法令遵守はもちろんのこと、外国人材の権利保護やスムーズな社会生活の実現を目的としています。主な要件は次のとおりです。
- 該当する製造分野で継続的に事業を行っていること:「対象となる産業分類一覧」に掲載されている事業所のみが対象となっている
- 事業所で所有している原材料で製造していること:原則として、受け入れ企業が所有する原材料を用いて製品を製造し、それを出荷している必要がある
- 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に既に入会していること:経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員であることが求められる
上記は一例ですが、要件を遵守することは、外国人材との良好な関係を築き、長期的な雇用につながるでしょう。
特定技能「製造業」の資格ごとの要件
特定技能「製造業」には、「特定技能1号」と、より高度な「特定技能2号」の2つの資格区分があります。それぞれ求められるスキルや経験が異なり、取得ルートも複数あります。
ここでは、外国人材が資格を取得するための具体的な要件を、資格・ルートごとに解説します。自社に必要な人材像と照らし合わせながらご確認ください。
参照元:
- 特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針(法務省)
- 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)(出入国在留管理庁)
- 製造分野特定技能評価試験(特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト)
特定技能1号を取得する場合
特定技能1号は、製造業分野で即戦力として活躍するために必要な基礎的な知識や技能、日本語能力を有する外国人材向けの在留資格です。資格を取得するには、「試験ルート」と「技能実習ルート」の2つの方法があります。ここでは、それぞれのルートにおける具体的な要件を解説します。
試験ルート
試験ルートで特定技能1号「製造業」の在留資格を取得するには、日本語能力と専門技能の両方で、国が定める試験に合格する必要があります。合格しなければならない試験は次のとおりです。
| 試験の種類 | 試験名 |
|---|---|
| 日本語能力試験 | 次のいずれか一方に合格する ・日本語能力試験(JLPT) N4以上 ・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) |
| 専門技能試験 | 製造分野特定技能1号評価試験(学科・実技)に合格する ※各業区分に応じた試験に合格する |
試験ルートでは、技能評価試験+日本語試験に合格→雇用契約→在留資格申請の順番で外国人材の採用を進めます。
技能実習ルート
技能実習制度を活用することも、特定技能1号「製造業」の在留資格を取得するための有効なルートの一つです。一定の条件を満たせば、技能試験や日本語試験が免除されるため、よりスムーズな移行が期待できます。
技能実習生から特定技能1号に移行する際の条件と試験免除の要件は次のとおりです。
移行の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 技能実習2号を良好に修了している | ・実習計画を2年10ヶ月以上終え、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること ・技能実習生に関する評価調書があること ※技能実習2号・3号の実習計画を中断して、特定技能への変更は認められない |
| 業務との関連性がある | 技能実習で行った職種・作業内容と、特定技能1号で従事する業務に関連性が認められること |
技能実習ルートでは、技能実習2号を良好に修了→雇用契約→在留資格変更申請の順番で外国人材の採用を進めます。
特定技能2号の取得する場合
「製造業」の特定技能2号を取得する方法には次の2つのルートがあり、各ルートの条件をすべて満たす必要があります。ここでは、それぞれのルートにおける具体的な要件を解説します。現在特定技能2号を取得できるのは、機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のみとなります。
特定技能1号から特定技能2号に移行するルート
特定技能1号として製造業で実務経験を積んだ方が、さらに高度な専門性を目指すための一般的なルートです。このルートで特定技能2号を取得するには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 日本国内に拠点を持つ企業の製造現場で、3年以上の実務経験を有していること |
| 技能試験の合格 | 次の2つの要件を満たす ・各分野で定められた特定技能2号評価試験に合格する ※機械金属加工区分、電気電子機器組立て 区分、金属表面処理区分のいずれか ・ビジネス・キャリア検定3級を取得する ※生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか |
特定技能1号から特定技能2号に移行するルートは、特定技能1号就労→実務経験→特定技能2号試験合格→資格変更申請の順番で外国人材の採用を進めます。
特定技能1号を経由せずに特定技能2号を取得するルート
特定技能1号の在留資格を経ることなく、直接特定技能2号の取得を目指すルートもあります。このルートは、既に国内外で高い技能レベルと実務経験を持つ人材が対象となります。主な要件は、次の2点です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 日本国内に拠点を持つ企業の製造現場で、3年以上の実務経験を有していること |
| 技能試験の合格 | 日本の国家資格である「技能検定1級」に合格していること ※対象職種:技能検定1級取得 (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか) |
特定技能1号を経由せずに特定技能2号を取得するルートでは、実務経験証明→特定技能2号試験合格→資格認定/変更申請の順番で外国人材の採用を進めます。
特定技能「製造業」の申請手順
特定技能「製造業」の申請手続きは、対象となる外国人材が海外に在住しているか、既に日本国内に他の在留資格で滞在しているかによって、進め方が大きく異なります。どちらのケースにおいても、複数の書類準備と段階的な手続きが求められるため、事前に全体の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。
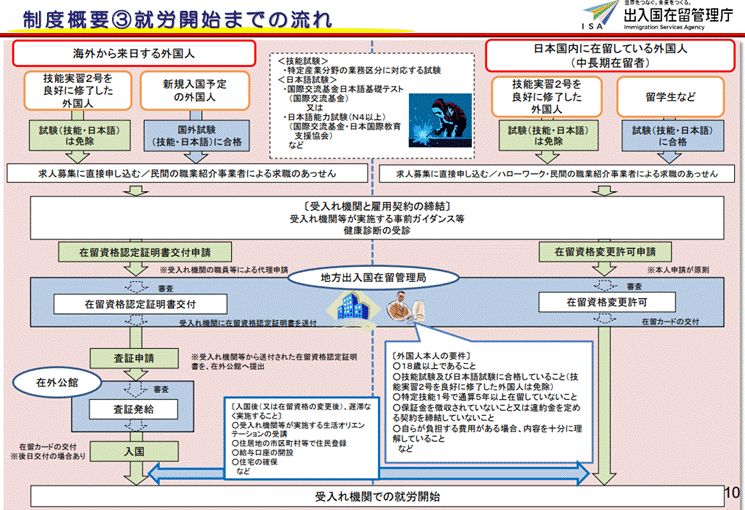
画像引用元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
大まかな流れとして、海外から新たに外国人材を雇い入れる場合は、まず受け入れ企業が日本国内の出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。この証明書が無事に交付された後、外国人材本人が自国の日本大使館または領事館でビザ(査証)を申請し、発給を受けてから来日するという段取りになります。
一方、既に日本国内に他の在留資格で滞在している外国人を雇用する場合は、受け入れ企業と外国人材が協力して、地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。審査を経て許可されれば、特定技能としての就労が可能です。
ただし、これらの申請手続きは、準備すべき書類が多岐にわたり、審査にも一定の期間を要します。初めて特定技能外国人材の受け入れを検討される企業様にとっては、専門的な知識も必要となり、相応の時間と労力がかかることを念頭に置く必要があります。
そのため、専門的な知識やサポートが必要な場合は、明光グローバルの「製造分野 ビジネス・キャリア検定・特定技能2号評価試験合格講座」がおすすめです。次の章では、明光グローバルのサービスについて紹介します。
特定技能「製造業」の外国人材の採用は明光グローバルに任せください
特定技能「製造業」の外国人材採用は、制度の複雑さや言語・文化の壁など、企業様にとって多くの課題が伴います。課題解決をサポートし、貴社の製造現場を支える優秀な外国人材の確保から定着までをトータルで支援するのが明光グローバルです。最後に、明光グローバルの強みと、製造業に特化したサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の日本国内での就労機会の創出と育成を通じて、国内企業の持続的な成長を支援する教育系の人材サービスです。長年にわたる個別指導で培った教育ノウハウと、10年以上に及ぶ日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見をもとに、外国人材育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
特に、外国人材の教育・育成に強みを持ち、日本語学校(JCLI日本語学校、早稲田EDU日本語学校)運営で培った質の高い教育プログラム提供の実績があります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
また、外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。人材紹介はもちろん、日本語教育や資格取得支援、企業文化への適応支援まで、外国人材の活躍と企業の成長をトータルでサポートするサービスです。
明光グローバルの特定技能人材紹介サービス
明光グローバルの「特定技能人材紹介サービス」は、製造業をはじめとする各分野で、特定技能を持つ外国人材の採用から入社後の活躍・定着までを支援するサービスです。特定技能1号人材の支援を行う「登録支援機関」としても正式に認定されており、企業様が外国人材受け入れに伴う煩雑な業務や法的な義務をスムーズに遂行できるようサポートします。
明光グローバルの特定技能人材紹介事業の概要
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
| 充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
| 効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
明光グローバルは、特定技能人材を企業が安心して採用し、能力を最大限に引き出せるよう支援することで、各業界の人材不足解消に貢献しています。
製造分野 ビジネス・キャリア検定・特定技能2号評価試験合格講座の概要
明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号(製造業)試験対策講座」を提供しています。本講座の主な特徴は、次の3つに集約されます。
- 独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
- 基礎から応用まで網羅した対象講座ごとのカリキュラムで構成されている
- 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる
また、受講者の日本語レベルや学習状況に合わせ、次の3つのコースを用意しています。
| コース名 | 内容 |
|---|---|
| 講座①ビジネス キャリア検定 | ・講座回数:全25回 ・講座時間:50時間 ・講座時間:15万円/1名 ・Japany:無料利用 |
| 講座②特定技能2号評価試験 | ・講座回数:全8回 ・講座時間:16時間 ・講座時間:5万円/1名 ・Japany:無料利用 |
| 講座①+講座② | ・講座回数:全34回 ・講座時間:66時間 ・講座時間:20万円/1名 ・Japany:無料利用 |
「特定技能2号(製造業)試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。
まとめ
特定技能「製造業」は、深刻化する人手不足に悩む日本の製造業にとって、即戦力となる専門技術を持った外国人材を確保し、事業の継続と発展を目指す上で有効な制度です。この制度を活用することで、企業は労働力不足の解消に加え、教育コストの削減や、場合によっては長期的な人材確保といったメリットにも期待できます。
しかし、特定技能外国人材を受け入れるためには、言語や文化の違いによるコミュニケーションへの配慮や複雑な申請手続きなど、企業側には相応の努力が求められます。そのため、多くの課題を自社だけで解決するのは難しいと考える企業も多いです。
特定技能制度の活用、特に専門性の高い特定技能2号の取得や試験対策でお困りの際には、ぜひ明光グローバルにご相談ください。外国人材の円滑な受け入れと育成、さらには企業の持続的な成長に貢献させていただきます。
特に、「特定技能2号(製造業)試験対策講座」は、多くの企業様にご利用いただき、高評価をいただいています。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。





