近年、人手不足の解消やグローバル化への対応などを背景に、外国人労働者を雇用する企業が増えています。採用数の増加に伴い、外国人労働者に関する企業内のトラブルも増加傾向にあります。これから外国人労働者を採用する企業の中には「外国人労働者を雇用する際にはどのようなトラブルが起こりやすい?」「防止するためにはどのような点に注意すべき?」といった疑問や不安をお持ちの担当者の方も多いです。
今回は、外国人労働者の雇用に関する主なトラブル事例とその発生原因、企業側が取るべき対策や注意点について解説します。外国人労働者の採用に伴うトラブルの防止に関心のある企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
外国人労働者を雇用する企業が増えている
近年、外国人労働者を雇用する企業が増加傾向にあります。厚生労働省の調査によると、2024年10月末時点で、日本で働く外国人労働者の総数は2,302,587人、外国人を雇用する事業所の総数は342,087ヶ所となっています。コロナ禍の収束以降、外国人労働者数・事業所数ともに、外国人労働者の届出が義務化された2007年以降、過去最多の数値を更新し続けています。
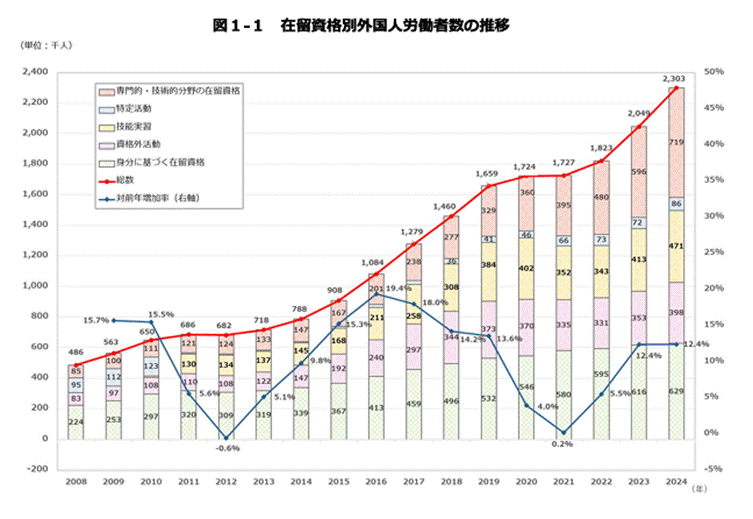
画像引用元:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(厚生労働省)
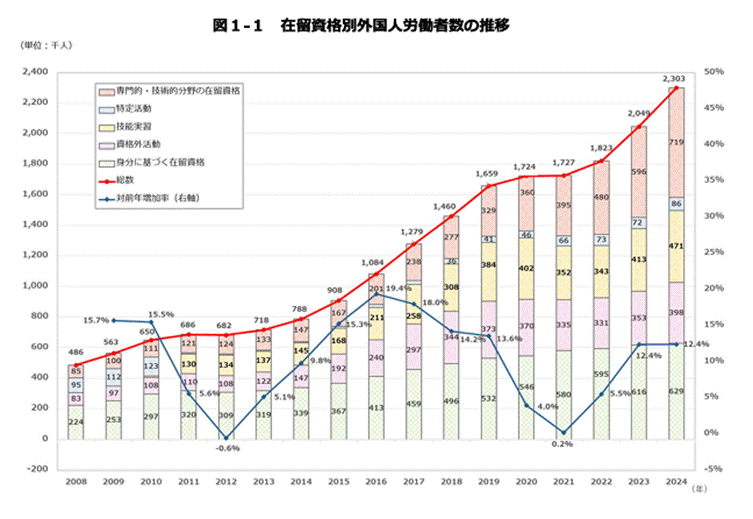
画像引用元:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(厚生労働省)
ここでは、日本で外国人労働者を雇用する企業が増えている背景やトラブルの危険性について解説します。
外国人労働者を雇用する企業が増えている背景
企業が外国人労働者を雇用する最も大きな理由の一つが、人手不足の解消です。
近年、日本では少子高齢化の影響で生産年齢人口が減少し、さまざまな業界・業種で人材不足が発生しています。外国人労働者の雇用は、日本人の労働者を新たに雇い入れることができない企業における人材難を解消する手段の一つとなっています。
また、外国人労働者が持つ知識や技能の獲得も、狙いの一つとなっています。外国人労働者の中には、日本ではまだ普及していない最先端技術に関する知見を有している人材もいます。このような外国人労働者を採用することで、事業・サービスの質を高めることができます。企業の海外進出や販路開拓の場面でも活躍が期待できます。
ダイバーシティの確保という観点でも、外国人労働者の雇用には意義があります。日本人とは異なる価値観や考え方を有する外国人材を採用することで、職場の古い常識や慣習が見直され、業務の質や生産性の向上などが期待できます。
外国人労働者を雇用する際には労働関係のトラブルに注意が必要
外国人労働者を雇用する際には、トラブルの発生に注意しなければなりません。外国人労働者を雇用する場合、日本人社員を雇用する場合とは異なる点で注意すべき点があります。
たとえば、日本語能力の不足によるミスコミュニケーションや、在留資格関連の申請・手続きの不備などが挙げられます。
トラブルを未然に防ぐためにも、まずは日本でどのような労働関係のトラブルが発生しているのかを把握することが必要です。そのうえで、自社で気を付けるべきポイントを明確化し、スムーズな受入れに向けて社内の体制を整備するようにしましょう。
外国人労働者の雇用に関するトラブルの発生状況
日本では外国人労働者の雇用に関して、どのようなトラブルが発生しているのでしょうか?
厚生労働省が公表している「令和5年外国人雇用実態調査」によると、外国人労働者のうち14.4%が就労上のトラブルを経験しています。特に多くの外国人労働者が経験したトラブルとしては「紹介会社(送出し機関を含む)の費用が高かった」「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」「事前の説明以上に高い日本語能力が求められた」などが挙げられます。
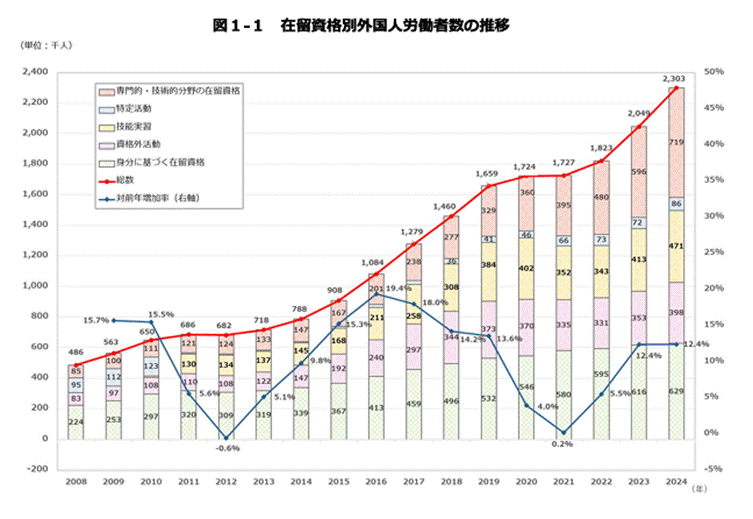
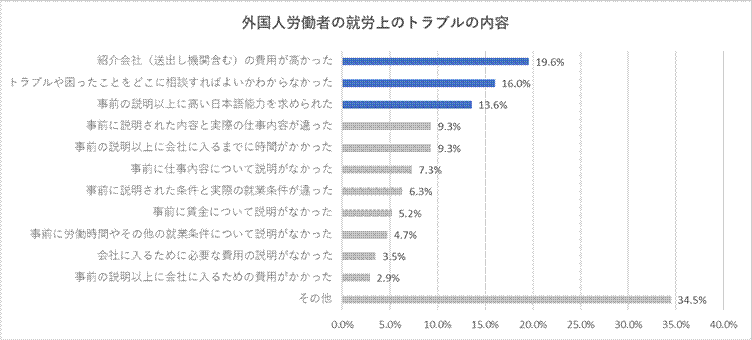
また、同調査では、外国人労働者を受け入れている企業側に対しても、外国人労働者の雇用に関する課題を聴取しています。
多くの企業で課題となっている項目としては「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も高く44.8%となっています。次いで、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」「在留資格によっては在留期間の上限がある」「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」「生活環境の整備にコストがかかる」といった項目が挙がっています。
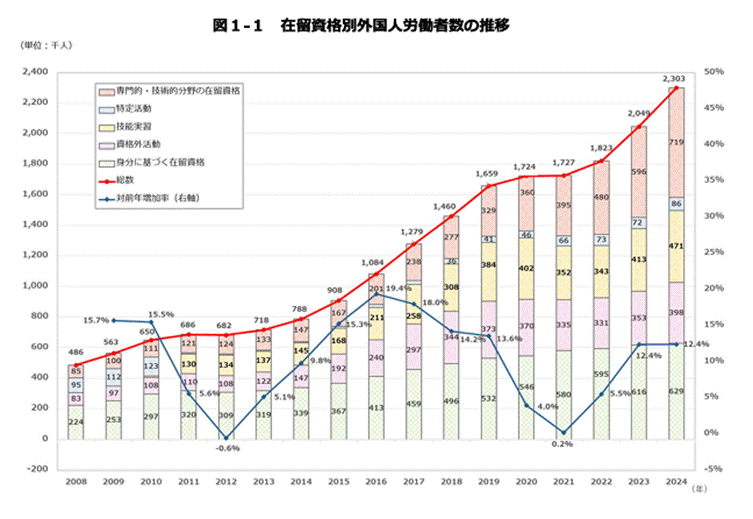
参照元:令和5年外国人雇用実態調査 調査結果の概況(厚生労働省)
外国人労働者の雇用に関するトラブル事例
外国人労働者の雇用に関するトラブルとして、具体的にはどのような事例が発生しているのでしょうか?ここでは、外国人労働者の雇用に際して注意したい具体的なトラブル事例を紹介します。
参照元:
在留資格に関するトラブル
まず注意したいのが、在留資格に関するトラブルです。
外国人労働者の在留資格によっては、就労が認められていないものや、就労可能な業務に制限がかかっているものがあります。また、外国人労働者が在留資格の変更や更新を行わず、在留可能な期間を満了した場合には、在留資格を喪失し、帰国しなければならないことになります。
本来就労が認められていない在留資格の外国人労働者を雇用してしまった場合や、外国人労働者の在留資格が既に切れているにも関わらず雇用を継続した場合、企業側は不法就労助長罪の対象となります。
たとえば、2025年には、千葉県で在留期限を過ぎたタイ人を農作業に従事させたとして、農事組合法人の理事に懲役刑・罰金刑が課されています。
2025年6月以降、制度の見直しに伴い、不法就労助長罪は厳罰化しています。具体的には「拘禁刑3年以下または罰金300万円以下」から「拘禁刑5年以下または500万円以下」まで罰則が引き上げられています。
参照元:在留期限過ぎたタイ人に農作業させる 不法就労助長罪の千葉・旭市議に地裁が有罪判決(産経新聞)
報酬や労働条件に関するトラブル
報酬や労働条件に関するトラブルにも注意が必要です。
近年、外国人労働者に対して、雇用契約で定めた内容よりも低い賃金で働かせるなどの悪質なトラブルが多く発生しています。特に、原則として転職が認められていない技能実習生に対して、残業代を出さないことにより結果的に最低賃金以下で働かせているケースが多く、問題となっています。
たとえば、2022年には、愛媛県の縫製工場で働いていたベトナム人の技能実習生11人に対して残業代の未払いが発覚しています。このケースでは労働基準監督署による指導が行われましたが、企業側が2ヶ月後に倒産し、技能実習生は残業代を取り返せず解雇されています。
また、企業としては雇用契約の通りに給与を支給しているつもりでも、外国人労働者側が契約内容を正しく理解できておらず、トラブルになることもあります。この場合、外国人労働者の母国語や伝わりやすい日本語を用いた雇用契約の説明が行われていなかったため、理解のすれ違いが発生していることが多いです。
参照元:「未払い残業代返して」相談できず最低賃金以下で残業続けた技能実習生(TBS)
業務の遂行に関するトラブル
業務の遂行の際にも、さまざまなトラブルが発生しています。
厚生労働省の2024年の調査によると、外国人労働者の労働災害発生率である死傷年千人率(以降「千人率」)は、日本人を含むすべての労働者より高くなっています。近年、外国人労働者に対して、安全教育が十分に行われず、就業中に労働災害が発生する事例が多く発生しています。
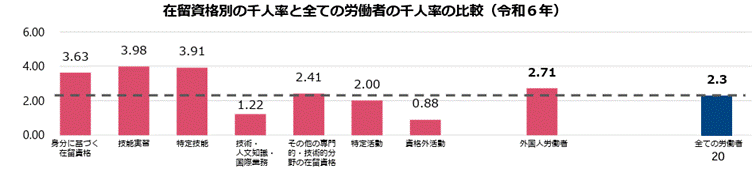
画像引用元:外国人労働者の労働災害発生状況(厚生労働省)
また、外国人労働者の日本語能力が不十分であるために、顧客や取引先とのコミュニケーションに齟齬が生じ、ミスやトラブルにつながることもあります。
このように、外国人労働者側の日本語能力の乏しさや、外国人労働者に対する企業側の受入れ体制や配慮の不足が、円滑な業務遂行を妨げる原因となる場合があります。
職場の人間関係に関するトラブル
職場の人間関係についても、外国人労働者を雇用する場合は特に注意すべき点があります。
日本人社員によっては、外国人労働者の受け入れに否定的・消極的な考えを持っていることがあります。このような環境では、外国人労働者に対して教育指導が十分に行われず、職場での孤立や差別が発生するリスクがあります。
また、外国人労働者の受入れ経験が少ない職場では「外国人労働者に対してどのように声をかければ良いかわからない」「日本人社員と同じように対応すれば良いだろう」といった考えから、無自覚のうちにハラスメントが行われていることがあります。
NPO法人移住者と連帯する全国ネットワークの調査では、身体的な攻撃や精神的な攻撃など、外国人労働者から寄せられたさまざまなハラスメントの実態が明らかにされています。
参照元:外国人労働者が遭遇するパワーハラスメント(レイシャルハラスメント)事例(特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク)
解雇に関するトラブル
外国人労働者の解雇については、慎重に進める必要があります。
まず注意したいのが不当解雇の問題です。近年、外国人労働者の妊娠が発覚したタイミングで企業側から不当に解雇させられ、労働争議に発展した事例が相次いでいます。
たとえば、東海地方で派遣労働者として製造業に従事していた女性のケースでは、妊娠を派遣元企業に報告した結果、派遣先企業から当月末での契約解除の通告を受けています。このケースでは、労働局による派遣先企業・派遣元企業への事情聴取・指導などが行われ、女性を派遣元企業で雇用することで決着しています。
また、外国人労働者が企業で働く際のルールやその重要性を十分に理解していないことにより、解雇につながる問題が発生する事例もあります。
たとえば、英会話教室で非常勤講師として勤務していた外国人労働者のケースでは、教材作成の際に他社の教材著作権違反を行っており、企業側から解雇を通達したところ、トラブルに発展した事例などが挙げられます。
外国人労働者の雇用に関するトラブルの発生原因
外国人労働者の雇用に関するトラブルは、なぜ発生してしまうのでしょうか?ここでは、外国人労働者の雇用に関するトラブルが発生してしまう主な原因について解説します。
- 外国人労働者の受入れに関する企業側の知見・ノウハウが不足しているから
- 職場の日本人社員が外国人労働者の適切な受入れ方法を理解していないから
- 外国人労働者の日本語能力が不足しているから
- 外国人労働者が日本の企業文化や働き方のルールを理解していないから
外国人労働者の受入れに関する企業側の知見・ノウハウが不足しているから
一つ目の要因は、外国人労働者の受入れに関する企業側の知見・ノウハウの不足です。
自社で就労可能な在留資格の種類や、在留資格の取得・更新・変更などの手続き、外国人労働者の受入れフローなど、企業側が対応すべき内容について十分に理解できていないと、法令違反を引き起こしてしまうことがあります。
また、職場のルールや働き方に関する説明が十分でないために、外国人労働者がミスやトラブルを引き起こしてしまうこともあります。特に、安全教育が不十分な場合は、労働災害につながるおそれがあるため注意が必要です。
職場の日本人社員が外国人労働者の適切な受入れ方法を理解していないから
職場の日本人社員が外国人労働者の適切な受け入れ方法を理解していないことも、トラブル発生の原因となります。
経営層や人事担当者が外国人労働者の受入れに関する適切な知見・ノウハウを持っていたとしても、現場の日本人社員は理解していない可能性があります。外国人労働者との協業に消極的な社員や、外国人材の文化や価値観、生活習慣を理解していない社員が多い場合、差別やハラスメントの温床となります。
外国人労働者の日本語能力が不足しているから
外国人労働者の日本語能力が不足していることがトラブルの発生につながっていることも多いです。
同じ日本語試験に合格していたとしても、個々の外国人材によって日本語能力は異なります。たとえば、学習歴が短い場合や来日まで日本語のネイティブスピーカーが周囲にいなかった場合には、来日時点での日本語レベルが想定よりも低くなる可能性があります。
また、多くの日本語試験では「話す」「書く」といった項目は出題されません。そのため、熱心に日本語を学習してきた外国人労働者の中でも、スピーキングやライティングに苦手意識を持つ外国人労働者は多いです。
このように、外国人労働者の日本語能力の不足が原因となり、職場での業務指示や教育研修の内容を理解できず、ミスやトラブルにつながることも多くなっています。
外国人労働者が日本の企業文化や働き方のルールを理解していないから
外国人労働者が日本の企業文化や働き方のルールを理解していないためにトラブルが発生してしまうこともあります。
日本の企業文化は国際的に見て独特だといわれています。たとえば、組織やチームで仕事を進めることは日本特有の文化であり、報告・連絡・相談や稟議・承認といった働き方のルールについても海外ではそこまで重要視されていないことがあります。そのため、日本で初めて働く外国人労働者は、来日時点で、日本の企業文化や働き方のルールを理解していない可能性が高いです。
日本人にとっては当たり前と思われるような内容も、外国人労働者にとっては非常識であることが多いです。トラブルを未然に防ぐためには、職場での文化やルールをしっかり明文化して説明することが重要です。
外国人労働者の雇用に関するトラブルを抑止するための対策・ポイント
外国人労働者の雇用に関するトラブルを防止するために、企業側はどのような対策に取り組むことができるのでしょうか?ここでは、外国人労働者の雇用に関するトラブルを抑止するための対策・ポイントについて解説します。
- 雇用する前に在留資格の内容や期限を確認する
- 採用選考の前に外国人労働者の日本語でのコミュニケーション能力を確認する
- 職場でのルールや働き方のポイントをわかりやすく説明する
- 雇用後の外国人労働者に対して継続的な日本語教育を実施する
- 職場の日本人社員に対して外国人受入れ研修を実施する
雇用する前に在留資格の内容や期限を確認する
在留資格関連のトラブルを防ぐためには、採用選考のタイミングで在留資格の内容や期限を確認することが必要です。
前述のとおり、在留資格によっては、就労可否や就労可能な業務内容・時間に制限がかかるものがあります。まずは自社で就労できる在留資格の種類や内容を把握することが重要です。そのうえで、選考のタイミングで在留カードなどを目視で確認するようにしましょう。
また、在留資格によっては、在留できる期間の上限があるものや、定期的な資格の更新が必要なものがあります。外国人労働者を雇用したら、今後の在留資格の更新・移行のスケジュールを把握し、前もって準備を進めるようにしましょう。
採用選考の前に外国人労働者の日本語でのコミュニケーション能力を確認する
日本語能力が重視される職場では、面接選考のタイミングで日本語での会話力を確認することも必要です。
個々の外国人労働者によって、日本語のコミュニケーション力は異なります。事前に日本語能力のチェックリストや評価基準などを準備し、対話を通して外国人労働者の会話力を確認するようにしましょう。また、自社で求める日本語レベルが明確である場合は、テストやレポート課題など、日本語に関する選考課題を準備することもおすすめです。
ただし、日本語能力の高い人材であればあるほど競合他社との採用競争が発生するため、内定率が低くなる傾向にあります。特に、海外から外国人労働者を雇い入れる場合、来日後に日本語能力が急激に伸びることが多いので、ポテンシャルも含めて採用することが必要です。
職場でのルールや働き方のポイントをわかりやすく説明する
外国人労働者に対して職場でのルールや働き方のポイントをわかりやすく説明することも重要です。
まずは労働災害を防止するために、労働安全に関する教育を充実させる必要があります。また、備品の管理方法や出退勤のルール、コンプライアンス研修など、職場で働くうえで必須となる研修については一通り揃えるようにしましょう。「報告・連絡・相談」や「5分前行動」といった、日本独特の企業文化についても細やかに説明する必要があります。
これらの内容については、外国人労働者にとってわかりやすい資料になるよう工夫する必要があります。そのため、日本人社員向けの資料とは別に、「やさしい日本語」版や母国語版の資料を作成するのがおすすめです。図やイラストなどを用いて視覚的にわかりやすく説明するのもポイントです。
雇用後の外国人労働者に対して継続的な日本語教育を実施する
雇用した外国人労働者に対して企業側が継続的な日本語教育機会を提供することもポイントです。
日本の職場でスムーズに働くためには、外国人労働者が日本語能力を高め続ける必要があります。外国人労働者が自力で日本語教材にアクセスするのは困難であるため、企業側が教材を提供するのが一般的になっています。一方で「近隣に日本語学校や日本語教室がない」「外国人労働者のための日本語教育機会の提供にかける予算が捻出できない」など、お悩みを抱えている企業も多いです。
明光グローバルでは、スマートフォンやタブレット端末からも学べる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」を提供しています。
外国人労働者が通勤中やランチ休憩中などのスキマ時間を活用して学ぶことができ、継続しやすくなっています。また、「IT導入補助金2025」の対象ツールにも選定されているため、教育コストを最小限に抑えたい中小企業や小規模事業者の方でも導入しやすくなっていることもポイントです。
職場の日本人社員に対して外国人受入れ研修を実施する
外国人労働者に対する差別・ハラスメントを抑止するためには、職場の日本人社員に対して外国人受入れ研修を実施することが必要です。外国人受入れ研修としては、次のような内容を提供することが一般的です。
- 異文化理解研修:生まれ育った環境によって異なる文化や価値観を尊重しあい、理解しようと努力する「異文化理解」について学ぶ研修
- 異文化コミュニケーション研修:生まれ育った環境によって異なるコミュニケーションの特徴を理解し、相手にとってわかりやすい表現を学ぶ研修
- 「やさしい日本語」研修:難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語である「やさしい日本語」の使い方を学ぶ研修
明光グローバルでは、外国人労働者と共に働く日本人社員向けの外国人受入れ研修サービスを提供しています。企業側の手間やコストを最小限にしながら、質の高い研修を提供することが可能です。気になる方はぜひ明光グローバルまでお問い合わせください。
外国人労働者のスムーズな雇用を実現するなら明光グローバルにお任せください
外国人労働者を雇用することで、企業側は安定的な人材確保を実現することができます。一方、外国人労働者を雇い入れる際には、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
トラブルを防止するためには、企業側が外国人労働者の受入れに関する正しい知見・ノウハウを持ち、職場の日本人社員に適切な受入れ教育をする必要があります。また、外国人労働者の日本語能力を向上させることも重要です。
明光グローバルでは、外国人材に特化した人材紹介事業に加えて、外国人労働者の採用に伴う多様な教育研修事業を手掛けています。特に、外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」は「IT導入補助金2025」の対象ツールにも採択されており、中小企業や小規模事業者の方でも始めやすいサービスとなっています。
最後に、外国人労働者の雇用に際するトラブルの防止に向けた教育研修にお悩みの経営者や人事、教育担当者の方に向けて明光グローバルのサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
外国人社員向け各種教育・研修サービス
明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,300本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |
| オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |
| 各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |
| 各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,300本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
まとめ
外国人労働者を雇用することで、企業は人手不足を解消できるだけでなく、海外の最先端技術の獲得やダイバーシティの確保など、さまざまなメリットを得ることができます。一方、はじめて外国人労働者を雇用する企業では、在留資格関連の手続きや日本語教育、職場の日本人社員に対する教育指導などの知見・ノウハウが蓄積されていないために、トラブルが発生してしまうリスクがあります。
外国人労働者の雇用に関するトラブルを防止するためには、選考時点で適切なスクリーニングを行い、受入れ手続きを進めることが重要です。また、雇い入れる外国人労働者・日本人社員の双方に対する充実した教育研修に取り組むことが必要です。
明光グローバルなら、外国人の雇用に関する採用・教育・定着を一貫してお任せいただくことが可能です。外国人労働者向けの日本語教育や日本企業におけるビジネスマナー研修に加え、日本人社員向けの外国人受入れ研修も提供しています。外国人労働者の雇用に関するお悩みは、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。









