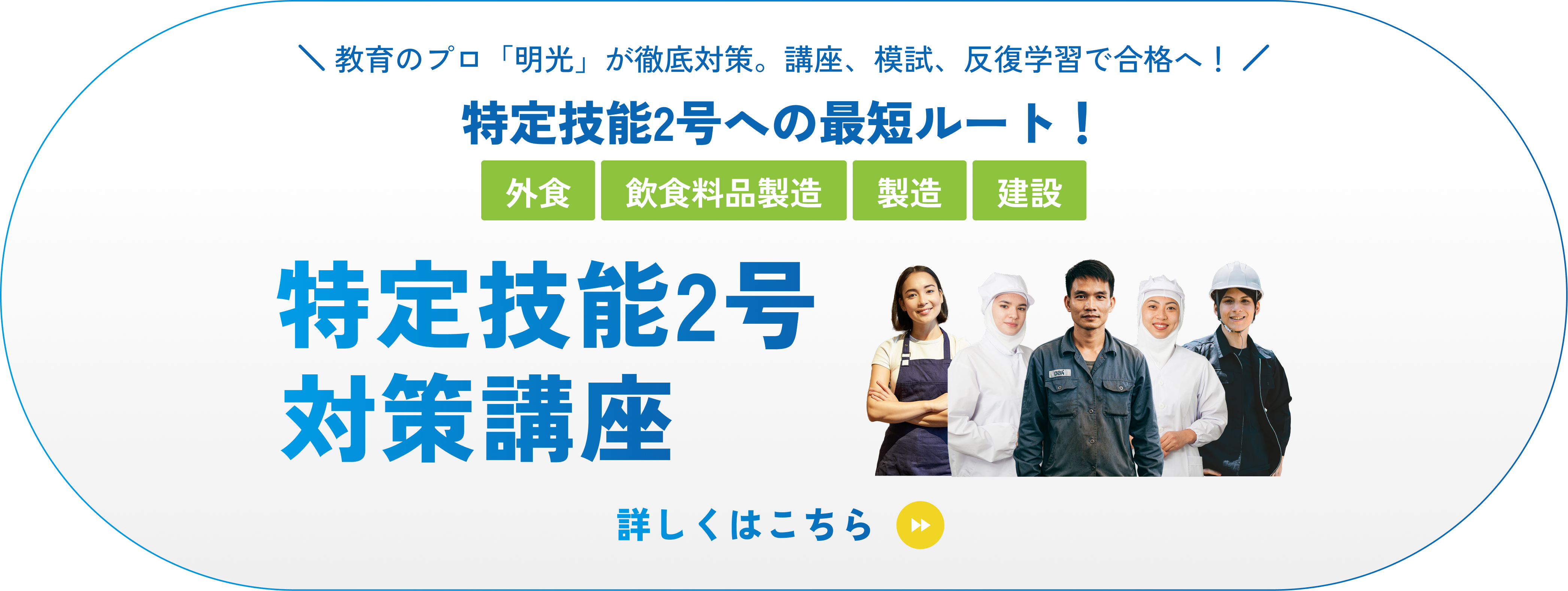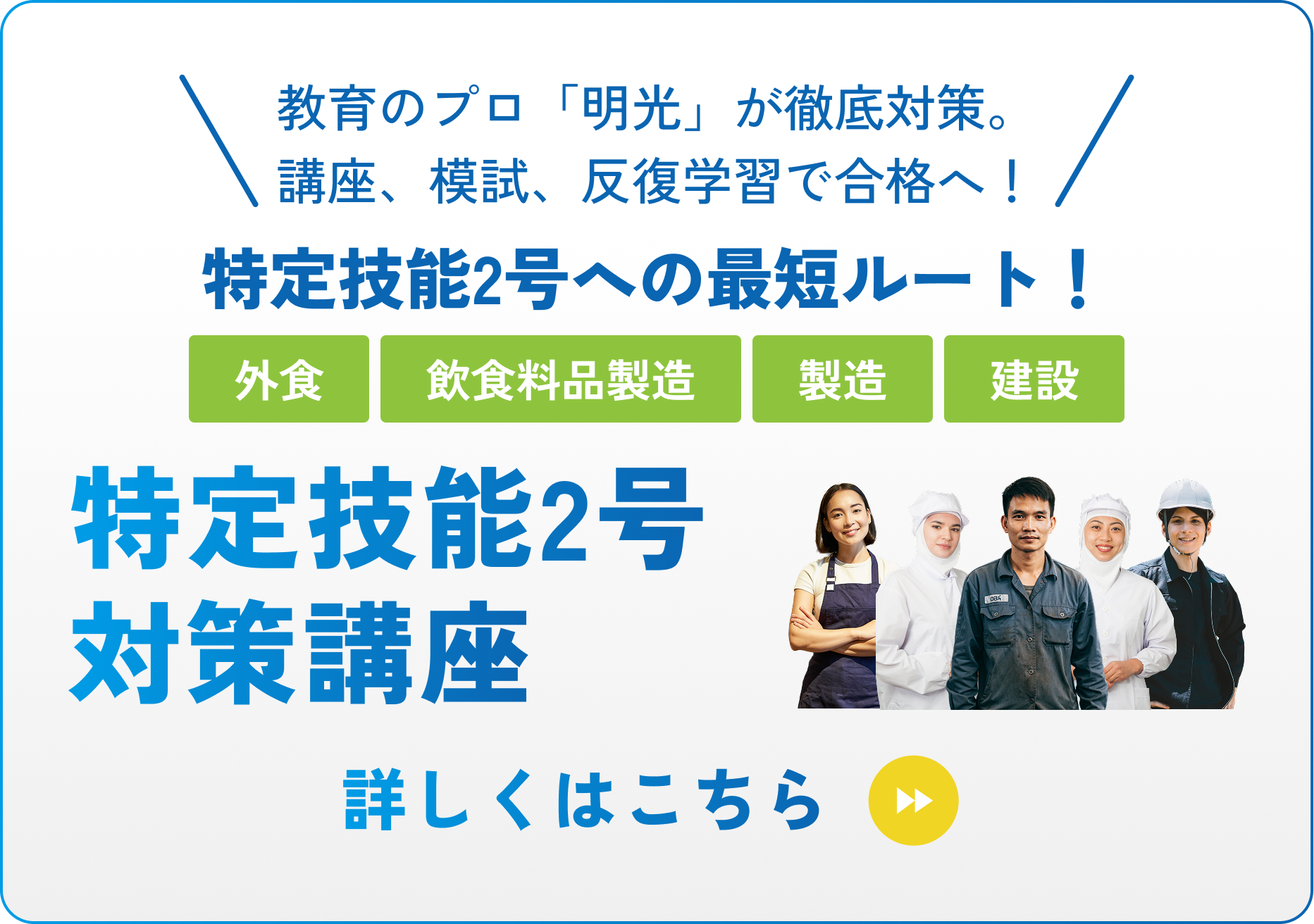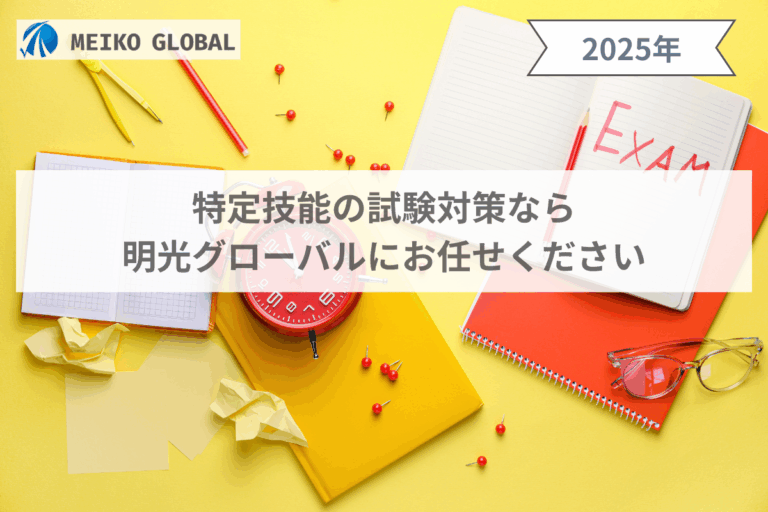特定技能2号「飲食料品製造業分野」の試験対策には、専門的かつ実践的な内容を網羅したテキストの活用が重要です。しかし、テキストをただ読むだけでは合格は難しく、効果的な学習方法を実践する必要があります。
今回は、特定技能2号「飲食料品製造業分野」の試験対策テキストの内容や入手方法、効果的な活用法、そして明光グローバルの試験対策講座を詳しく解説します。
特定技能2号「飲食料品製造業分野」の基礎知識
特定技能2号は、飲食料品製造業分野において、より高度な技能を持つ外国人材を取得できる在留資格です。この資格を保有していれば、現場のリーダーや管理者として、より幅広い業務に携わることが可能になります。
ここでは、特定技能2号「飲食料品製造業分野」の概要や取得要件、試験内容、合格率を詳しく解説します。
「飲食料品製造業分野」の概要
特定技能2号「飲食料品製造業分野」は、酒類を除く飲食料品の製造・加工、および安全衛生管理業務全般に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号よりも高度な技能が求められ、製造工程の管理や従業員の指導といった、より責任のある業務を担うことができます。
この制度が設けられた主な目的は、次のとおりです。
- 人手不足が深刻な飲食料品製造業界で、熟練した技能を持つ外国人材を確保する
- 外国人材の長期的な就労を促進し、業界の安定化を図る
- 外国人材により高度な業務を任せることで、生産性向上に貢献してもらう
つまり、特定技能2号は、飲食料品製造の現場でリーダーシップを発揮し、品質向上や効率化に貢献できる、即戦力となる外国人材を対象とした資格といえます。
参照元:
取得要件
特定技能2号「飲食料品製造業分野」の資格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
取得要件
| 技能水準 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格すること。 |
| 実務経験 | ・飲食料品製造業分野において、複数の作業員(2名以上の技能実習生、アルバイト従業員、特定技能外国人など)を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上必要。 ※「指導する」とは、作業員に対し、作業工程などについて主導すること(直接・間接は問わない)を指す。 ※「工程を管理する者」とは、担当部門長、ライン長、班長などの役職が想定されている。 ・特例:2023年6月10日から数えて在留期限上限(5年)まで2年6ヶ月未満の場合は、残余期間から6ヶ月を差し引いた期間の管理等実務経験でも認められる。 |
これらの要件を満たせば、特定技能2号の在留資格を申請できます。
参照元:
取得するとできること(メリット)
特定技能2号「飲食料品製造業分野」を取得すると、外国人材本人だけでなく、受け入れ企業にとっても多くのメリットがあります。
外国人材にとってのメリット
| メリット | 概要 |
|---|---|
| 在留期間の更新上限がない | 長期的に日本で働くことができ、キャリアプランを立てやすくなります。 |
| 家族の帯同が可能になる | 配偶者や子を日本に呼び寄せることができ、家族と一緒に生活できます(特定技能1号では原則不可)。 |
| 永住権取得の可能性がある | 一定期間日本に滞在し、所定の要件を満たすことで、永住権を申請できます。 |
| 転職が可能 | 特定技能1号と比較して、転職の自由度が高いです。 |
受け入れ企業にとってのメリット
| メリット | 概要 |
|---|---|
| 即戦力人材を確保できる | 飲食料品製造業に関する高度な知識・技能を持つため、教育コストを抑え、すぐに現場のリーダーとして活躍を期待できます。 |
| 長期的に働いてくれる人材を確保できる | 在留期間の更新上限がないため、長期にわたって安定した労働力を確保できます。 |
| 幅広い業務を任せられる | 製造工程の管理、従業員の指導(特定技能1号や技能実習生のマネジメント、日本人従業員との橋渡し役など)といった、幅広い業務を任せられます。 |
| 人材定着によるコスト削減を見込める | 長期就労が可能になるため、採用コストや教育コストの削減につながります。 |
| 生産性が向上する | 専門的なスキルを持っているため、生産性向上を期待できます。 |
このように、特定技能2号は外国人材と受け入れ企業双方にとって、Win-Winの関係を築ける制度といえるでしょう。
「飲食料品製造業分野」の技能測定試験について
特定技能2号を取得するには、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格する必要があります。「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の概要は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受験資格 | ・試験日において、満17歳以上であること。 ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。 ・試験の前日までに飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という)を2年以上有すること。 ・試験の前日までに管理等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6ヶ月以内に管理等実務経験を2年以上有することが見込まれること(飲食料品製造業2号技能測定試験受験者のみ)。 |
| 試験科目 | 学科試験 ・飲食料品製造業での管理 ・安全・安心な食品製造 ・安全・安心の管理 ・品質管理 ・納期管理 ・コスト管理 ・より良い管理のために 実技試験 ・安全・安心な食品製造 ・安全・安心の管理 ・品質管理 ・納期管理 ・コスト管理 |
| 実施方法 | ・学科試験と実技試験(2科目合わせて70分50問) ・ペーパーテスト(マークシート)方式 ・日本語で実施(漢字にルビなし) 学科試験 35問 125点満点 実技試験(判断・計画立案試験等) 15問 75点満点 ・合格基準:満点(200点)の65%以上 |
| 受験スケジュール | ・企業登録申請締め切り:2025年2月19日(一部、2025年2月14日) ・受験者登録申請期間:2025年1月31日~2025年2月21日 ・試験申込:2025年3月13日~2025年3月19日まで ・試験期間:2025年5月19日~2025年6月3日(全国13箇所で開催) ・合格発表:6月下旬(予定) |
試験の詳細については、OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)のホームページよりご確認ください。
参照元:
試験の実施状況(受験者数・合格者数)
特定技能2号「飲食料品製造業分野」の技能測定試験は、比較的新しい試験であり、受験者数は増加傾向にあります。2024年に実施された全3回分の試験の実施状況は下の表のとおりです。
| 試験回 | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|
| 第1回 | 181 | 94 |
| 第2回 | 1,463 | 817 |
| 第3回 | 1,619 | 927 |
| 第1~3回 | 3,263 | 1,838 |
合格率は50%台後半で推移しており、難易度は高めといえます。そのため、十分な試験対策が不可欠です。次に、合格者の国籍と合格者数は次のとおりです。ベトナムからの受験者が圧倒的に多いことがわかります。
| 国籍 | 合格者数(人) |
|---|---|
| ベトナム | 1,506 |
| 中国 | 144 |
| ミャンマー | 90 |
| インドネシア | 49 |
| ネパール | 10 |
参照元:2024年度外⾷業及び飲⾷料品製造業の特定技能測定試験 国内試験実施状況(⼀般社団法⼈外国⼈⾷品産業技能評価機構)
特定技能2号「飲食料品製造業分野」の技能測定試験用テキスト
特定技能2号「飲食料品製造業分野」の技能測定試験は、管理者としての知識・技能を問う試験です。そのため、試験対策には、より専門的で実践的な内容を網羅したテキストの活用が欠かせません。ここでは、試験用テキストの入手方法や内容について詳しく解説します。
テキストの入手方法
特定技能2号「飲食料品製造業分野」の技能測定試験用テキストは、日本能率協会コンサルティング(JMAC)のウェブサイトからダウンロードできます。農林水産省の「外国人材受入総合支援事業」の一環として作成されたテキストであり、無料でダウンロード可能です。
また、下のページから、テキストの内容を紹介するYouTubeの無料セミナー動画を見ることもできます。ただし、サイトからの登録が必要です。
テキストの内容
テキストは、特定技能2号として飲食料品製造業で働く上で必要な知識、特に工程管理者にとって必要な知識と技能を学ぶために構成されています。特定技能1号のテキストで触れられている基本的な内容に加え、より高度な管理業務に関する内容が盛り込まれています。ここでは、テキストの各章で解説されている学習内容について解説します。
参照元:飲食料品製造業特定技能2号 技能測定試験学習用テキスト(日本能率協会コンサルティング)
①飲食料品製造業での管理
この章では、飲食料品製造業における管理の基本的な考え方を学びます。具体的には、次のとおりです。
| 学習内容 | 概要 |
|---|---|
| 安全・安心な食品を作るための全体像 | 食品工場では、安全・安心な食品製造が最優先です。そのための基本を、特定技能1号のテキスト内容(食品衛生など)と合わせて確認します。 |
| 食品製造に関する法律 | 食品の安全確保に関する基本的な法律(食品安全基本法、食品衛生法、食品表示法など)について理解を深めます。 |
| 健康障害 | 食品が原因で起こる健康被害(食中毒など)について、その症状や原因、防止策を学びます。 |
| 安全な職場環境 | 労働安全衛生法に基づき、ソフト面(作業手順、ルール、教育など)とハード面(設備、機器など)の両面を学びます。 |
| 作業者と管理者の違い | それぞれの役割と責任を明確にし、管理者に求められる知識(QCD、PDCAサイクル、3Mなど)を習得します。 |
これらを学ぶことで、飲食料品製造業の管理者として必要な基礎知識を身につけ、日々の業務に活かせるようになります。
②安全・安心な食品製造
この章では、食中毒などの事故を防ぎ、消費者に安心して食べてもらえる食品を作るための、実践的な衛生管理手法を解説します。学習する内容は、次のとおりです。
| 学習内容 | 概要 |
|---|---|
| 一般衛生管理 | 原材料の受け入れから、製造、製品の取り扱いまで、各段階での衛生管理を学びます。また、従業員の健康管理、5S(整理・整頓・清掃・清潔・習慣)も重要な学習項目です。 |
| HACCP(ハサップ) | 危害要因分析に基づき、重要管理点を特定して重点的に管理するシステムを学びます。 |
| その他 | 交差汚染防止や、フードディフェンス(食品防御)についても理解を深めます。 |
以上の知識は、食中毒予防の3原則(つけない・増やさない・殺す)の実践に欠かせません。
③安全・安心の管理
この章では、労働者の安全と健康を守るための管理について学びます。具体的には、次のとおりです。
| 学習内容 | 概要 |
|---|---|
| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と健康を確保するための法律であり、事業者と労働者双方に守るべき義務があります。安全管理者や衛生管理者の役割、作業環境の整備(ソフト面・ハード面)などを学びます。 |
| 正しい服装と手順 | 危険を避け、安全に作業するための正しい服装(ファスナーをしっかり締める、インナーを外に出さない、ポケットに物を入れない、清潔な手袋の着用など)と、標準作業手順について学習します。 |
| 労働災害 | 飲食料品製造業で多い労働災害(はさまれ・巻き込まれ、転倒、切れ・こすれ、熱中症、腰痛症など)とその防止策を学びます。 |
| 安全意識 | 異常事態の管理、5S活動などを通して、安全意識を高めることの重要性を学びます。 |
労働安全衛生法に基づき、正しい服装と手順、労働災害の防止策、そして安全意識の向上を通じて、労働者の安全と健康を守るための具体的な管理方法を習得します。
④品質管理
飲食料品製造業における品質管理は、安全・安心な製品を安定して作るために重要です。この章では、次の内容を学びます。
| 学習内容 | 概要 |
|---|---|
| 作業の標準化と徹底 | 作業者全員が正しい作業方法を理解し、手順書に基づき作業を学びます。 |
| 記録の徹底と活用 | 作業前、作業中、作業後の記録を正確に行い、問題発生時に原因を追究できるように学びます。 |
| 検査と校正の実施 | 検査機器の定期的な校正を行い、正確な検査結果を得ることを目的とし、受入検査、工程内検査、出荷検査、環境検査など、適切な検査を学びます。 |
| トレーサビリティの確保 | 製品の製造履歴を追跡可能な状態にし、問題発生時に迅速に対応できるようにします。 |
| 歩留まり管理 | 不良品の発生を抑制するため、良品の割合(歩留まり)を常に把握し、改善できるようにします。 |
| 消費者からの意見の活用 | クレーム等、消費者からの意見を真摯に受け止め、品質改善につなげる方法を学びます。 |
これらの活動を通して、品質の維持・向上に努め、顧客からの信頼を得ることが重要です
⑤納期管理
飲食料品製造業では、製品の鮮度を保ち、適切なタイミングで供給することが重要です。そのため、生産スケジュールの計画と効率的な納期管理が求められます。この章では、次の内容を学びます。
| 学習内容 | 概要 |
|---|---|
| 生産計画の重要性 | 大日程計画、中日程計画、小日程計画の3つの区分を理解し、特に小日程計画と作業指示について現場管理者が理解し、作業者に共有・指示することの重要性を学びます。 |
| 3M(原材料、作業者、設備)の管理 | 原材料・作業者・設備の3Mについて、計画的に管理できる手法を学びます。 |
| 作業中の進捗管理 | 進捗管理表で、目標達成と生産速度の維持状況を把握・調整する方法を学びます。 |
| 作業後の管理 | 計画と実績を比較し、問題発生時は、順序変更や増員等で対応する方法を学びます。 |
上記を通じて、納期遅延を防ぎ、効率的な生産を実現するための管理方法を習得します。
⑥コスト管理
コスト管理は、適切な価格で製品を提供し、継続的な製造を続けるために重要です。この章では、次の内容を学びます。
| 学習内容 | 概要 |
|---|---|
| コスト管理の基本と標準の把握 | 製造費用を原材料費、労務費、経費に区分し、不良品防止が最重要と学びます。 |
| 作業中の管理 | 各作業者が標準時間通りに作業できているか確認し、早すぎ・遅すぎの原因を究明する方法を学ぶ。原材料、人、設備の生産性を理解し、それぞれの計算方法を習得します。 |
| 作業後の管理 | 良品数と原単位から合計コストを計算し、予算と比較して評価(原価差異分析)する方法を学ぶ。企業が定めたコスト関連数値に基づき、必要な費用データを正確に収集する方法を学びます。 |
コスト管理を学ぶことで、製造現場における無駄(材料のロス、作業の遅延、設備の停止など)を発見し、改善につなげられます。
⑦より良い管理のために
より良い管理のためには、製造部門の役割を理解し、部門間の連携を強化して、会社全体の目標達成を目指すことが重要です。この章では、次の内容を学びます。
| 学習内容 | 概要 |
|---|---|
| 製造プロセスの最適化 | QCD・3Mを軸に各部門と連携し、食品ロス削減、各種マネジメントシステム活用、リスクアセスメントによる食品事故防止を学びます。 |
| 3Mの徹底管理 | 作業者の労働時間・意欲・スキル管理、設備の稼働率維持、原材料の品質・効率管理を学びます。 |
| 改善とコミュニケーション | 「改善(KAIZEN)」活動による作業手順の見直し、職場内外での良好な関係構築によるスムーズな業務遂行を学びます。 |
特定技能2号「飲食料品製造業分野」のテキストでは、以上の7つの項目を学ぶことができます。ただし、学習範囲が広いため、効率的に勉強しなければなりません。そこで、次の章では、技能測定試験用テキストを活用するためのポイントを解説します。
技能測定試験用テキストを活用するポイント
技能測定試験のテキストは、合格に必要な知識を網羅しています。しかし、ただ読むだけでは効果は薄いため、実務と結びつけ、計画的に学習することが大切です。ここでは、テキストを最大限に活用し、試験合格に近づくための具体的な方法を解説します。
- 学習計画を立てる
- 実務と関連付けて学習する
- グループ学習を活用する
- 苦手な部分を繰り返し復習する
学習計画を立てる
まず、試験日から逆算して、いつまでに何を学習するか具体的な計画を立てましょう。計画がないと、学習の進捗を把握できず、試験直前に焦ってしまうなど本来の実力を発揮できない可能性があるからです。具体的な計画の立て方のポイントは次のとおりです。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 試験範囲を確認する | 受験する試験の範囲を正確に把握します。 |
| 教材を選ぶ | 試験範囲を網羅しているテキストを選びます。 |
| 学習期間を設定する | 試験日までの期間を考慮し、無理のない学習期間を設定します。 |
| 1日の学習量を決める | 1日に学習するページ数や章を決め、無理なく継続できる量を設定します。 |
| 復習時間を確保する | 週に一度、または月に一度、学習内容を振り返る時間を設けます。 |
これらのように、計画的に学習を進めることで、知識が定着しやすくなり、自信を持って試験に臨めるでしょう。
実務と関連付けて学習する
テキストの内容を、実際の仕事と結びつけて理解を深めましょう。実務と関連付けることで、知識が単なる暗記ではなく、実践的なスキルとして身につくからです。テキストの知識と実務経験が結びつけば、理解度が格段に向上し、試験での応用問題にも対応できる力が養われます。具体的には、次のような方法で学習を進めるのがおすすめです。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 業務での活用を意識する | テキストで学んだ内容を、日々の業務でどのように活用できるか常に考えます。 |
| 疑問点を職場に持ち込む | テキストで理解できなかったことや、疑問に思ったことは、職場の先輩や同僚に積極的に質問します。 |
| 事例を参考にする | テキストに掲載されている事例を、自分の業務に当てはめて考えます。 |
このように、実務と学習を結びつけることで、より効果的に知識を習得し、試験合格へと繋げられます。
グループ学習を活用する
仲間と一緒に学習することで、モチベーションを維持し、理解を深めることができます。一人で学習するよりも、疑問点を解消しやすく、多角的な視点を得られるからです。反対に、孤独な学習は、モチベーションの低下や、理解不足に繋がる可能性があります。グループ学習の具体的なメリットとしては、次のような点が挙げられます。
| メリット | 概要 |
|---|---|
| 疑問点をすぐに解消できる | わからないことがあれば、すぐに仲間に質問し、解決することができます。 |
| 多様な視点で学習できる | 自分とは異なる視点や考え方に触れることで、理解が深まります。 |
| モチベーションを維持できる | 同じ目標を持つ仲間と励まし合うことで、学習意欲を高く保てます。 |
| 知識が定着する | 互いに教え合うことで、学習内容が記憶に残りやすくなります。 |
たとえば、定期的に勉強会を開き、互いに教え合ったり、問題を出し合ったり、模擬試験形式で実践練習をしたりすることも効果的です。また、仲間との学習は知識の定着だけでなく、試験への不安を軽減し、精神的な支えとなる効果も期待できます。
苦手な部分を繰り返し復習する
テキストで苦手だなと感じた部分は、重点的に復習しましょう。苦手な部分を放置すると、試験本番で同じような問題が出題された場合に対応できず、合格が遠のいてしまいます。苦手な部分こそ、合格への伸びしろです。具体的には、次のような方法で、苦手克服に取り組みましょう。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 間違えた問題をわかりやすくまとめる | ・間違えた問題や理解が曖昧な部分に付箋を貼る ・苦手な項目をノートにまとめる ・間違えた回数を記録する |
| 反復練習をする | ・付箋を貼った箇所を毎日見返す ・ノートにまとめた内容を定期的に読み返す ・同じ問題を時間を空けて繰り返し解く |
繰り返し復習することで、知識が定着し、苦手意識を克服できます。
ただし、独学での学習だけでは不安が残る場合もあるでしょう。特に「飲食料品製造業分野」の試験対策は、専門的な知識も多く、範囲も広いため、効率的な学習が求められます。そのような場合は、明光グローバルの「特定技能2号(飲食料品製造)試験対策講座」がおすすめです。
「飲食料品製造業分野」の試験対策なら明光グローバルにおまかせください
飲食料品製造業分野の特定技能2号試験は、専門性が高く、広範囲な知識が求められます。独学での対策に限界を感じている。確実に合格を目指したい企業担当者様は、ぜひ明光グローバルの試験対策講座をご検討ください。
最後に、長年の教育実績と外国人材育成のノウハウを持つ明光グローバルの強みと、試験対策講座の内容を紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。外国人材の育成と日本企業の成長支援を使命とし、教育と人材のプロフェッショナルとして、質の高いサービスを提供しています。
明光グローバルの主なサービスは次のとおりです。
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
長年の実績に裏打ちされた教育ノウハウと、外国人材に特化したサポート体制が強みです。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、国からも高い評価を受けています。
特定技能2号(飲食料品製造)試験対策講座の概要
飲食料品製造分野の「特定技能2号試験対策講座」を受講すれば、高い合格実績を出すことも可能です。具体的には、次のような特徴があります。
| 特徴 | 概要 |
|---|---|
| 全8回のカリキュラムを受けられる | 専門知識を持つ日本語講師が、試験範囲を網羅したカリキュラムを作成し、基礎から応用まで丁寧に指導します。 |
| 模擬試験を受けられる | 本番を想定した模擬試験で、時間配分や苦手分野を把握し、弱点克服につなげられます。 |
| 日本語eラーニングを併用できる | 講座時間外も、eラーニングシステム「Japany」で、日本語と専門知識の学習をサポートします。 |
講座はオンライン形式(全8回、各120分)で2ヶ月間行われ、「安全・安心な食品製造」「品質管理」「コスト管理」など、試験に必要な知識を体系的に学び、最終回に模擬試験を行います。無料相談も受け付けていますので、試験対策でお悩みの企業担当者様は明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。
まとめ
特定技能2号「飲食料品製造業分野」の試験合格には、公式テキストを活用し、計画的かつ実践的な学習が欠かせません。試験は専門性が高く、広範囲な知識が求められるため、計画的な学習と実務経験との連携が重要だからです。独学での対策に不安がある場合は、専門機関のサポートを活用することも有効な手段となります。
明光グローバルは、長年の教育実績と外国人材育成のノウハウを活かし、特定技能2号試験対策講座を提供しています。飲食料品製造業分野での人材不足解消、外国人材のキャリアアップをお考えの企業様は、明光グローバルまでお気軽にご相談ください。